�y�f�Î��ԁz�~���g�_�ˉ@ 9:00-20:00/�_�˃}���C�@ 11:00-20:00�y�x�f���z���E�j

���@�́A�����ɂ��č����Ă�������̒ɂ݂��ꍏ��������菜���A�Љ�ɍv�����邱�Ƃ��ő�̎g���ɂ��Ă���܂��B
�������u�����Ɠ��Ӂv��厖�ɂ��A�u���Ɏ��Áv��S�����Ă��܂��B
���Ȃ����ɂ݂̏Ǐ���
�ǂ�ł����H
���̒ɂݏ�ʂR�Q
�����̒ɂ݂̑S�Ă������܂�
���̒�����Y������Ǐ���N���b�N���ĉ�������
�˂��̏ꍇ�́A������4�l�����܂�
�����P ���������̐_�o�܂Ői��ł���ꍇ(������)
�����Q �_�o���������i�������A���Ԃ����Ȃǁj��A
�@�@�@�_�o������ł��܂������ɂ��ۂ��������Ĕ^��ł�ꍇ
�����R �����a�̏ꍇ
�����P�F ���������̐_�o�܂Ői��ł���ꍇ(������)
�����̑傫���ɂ͒i�K������܂����A�b�R�ƌ����Ē��������̐_�o�܂ōs���Ă��܂��ƁA���Ȃ�ɂ݂܂��B
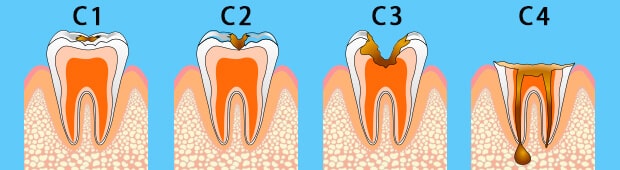
���������̐_�o�܂ōs���ƁA�_�o�������̂��ۂɂ���ċ������ǂ��N�����܂��B
�����āA���Ȃ苭���ɂ݁i�Y�L�Y�L�A�ǂ�����ǂ�����etc�j���o�Ă������܂��B
�ɂݎ~�߂������ɂ����Ȃ�܂��B
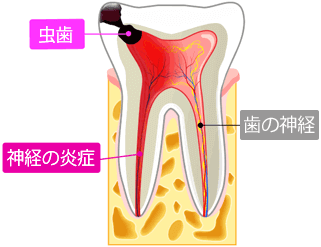
���Ö@
�ʏ�A�����̒ɂ݂ɂ͒i�K������܂����A���������̐_�o�܂ōs���Ă��܂��ƁA���Ȃ�ɂ݂܂��B
���̏ꍇ�́A���̐_�o����菜�����Â����Ȃ��Ƃ����܂���B�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����Ɏ��܂�܂��B
�ˁi���Ӂj�������A���̐_�o�͂Ȃ�ׂ����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͂Ȃ�ׂ��_�o���c���悤�w�͂����Ă��܂��B
��̓I�Ȏ��Ö@
�@�܂��A�ɂ�ł鎕�ɖ��������܂��B
���@�ł͖����͒ɂ��Ȃ��ł��܂��B�ɂ��Ȃ����R�͂������B
�A���������������������A����������Ď��A���̌㎕�̐_�o��j�̂悤�Ȋ����g���Ď��܂��B
������������������Ă�̂Œɂ݂͑S������܂���B
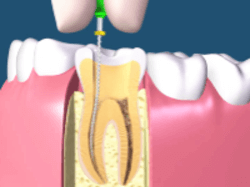
�B�_�o�����I�������A���̓����ɏ��ł̖�����āA�ӂ������ĂP��ڂ̎��Â͏I���ł��B
�C���̐_�o���������ɁA��U���ǂ��N���܂����A���ꂪ�P�`�Q�T�ԂŎ��܂�����_�o�̑���ɂȂ����l�߂܂��B

�������ʂ��Ă�̂��A�_�o�̑���ɂȂ��ł��B
���@�̖������ɂ��Ȃ����R
1�F�����̒��˂̐j���h�������ɂ݂��Ȃ���
���ƌ����Ă��A�j���h�����̒ɂ݂�h�����Ƃ��厖�ł��B
�����ɍׂ̐j���g���Ă���
�ːj�����ׂ��̂ŁA�����̒��Ɏh�������ɂ��킩��ɂ����B
���ɂ݂�������זE(�ɓ_)�̏��Ȃ��ӏ��ɍŏ��ɑł�
�˒ɓ_�����Ȃ��̂Œɂ݂ɂ����ł��B
���j���h���u�Ԃ́A�������̔S���ۂ̊v�̂悤�ɁA�s���ƒ����Đj����C�Ɏ������ɓ���悤�ɂ���B
�˂��̂悤�ɂ���Ɛj���h�������Ƃ��킩�炸�A���҂���ɂ́A�u�ŋ߂̖����͒��˂���Ȃ���ł����H�v�ƕ�����邱�Ƃ������ł��B

�Q�F������𒍓�����Ƃ����ɂ݂��Ȃ���

������͉t�̂Ȃ̂ʼn��x���Ⴂ�̂ł����A�������鎞�ɉ��x���Ⴂ�ƁA�̂��₽�������Ă��܂��Ɠ����ɒɂ������Ă��܂������ƂȂ�܂��B
���@�ł͂��炩�����������̉����炢�ɉ��߂Ē������܂��̂��A���җl�͋C�t����܂���̂ŁA�ɂ݂������܂���B
����ƁA�����ւ������̃X�s�[�h�����Ȃ������肵�Ă��܂��B�}���Œ�������ƁA���������Ă��܂��ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
���@�ł́A�P�H���P�b���炢�̂������Ƃ����X�s�[�h�ōs�����ŁA�����̑��ݎ��̂ɋC�t����܂���B
�����Q�F �_�o���������i�������A���Ԃ����Ȃǁj��A�_�o������ł��܂������ɂ��ۂ��������Ĕ^��ł�ꍇ
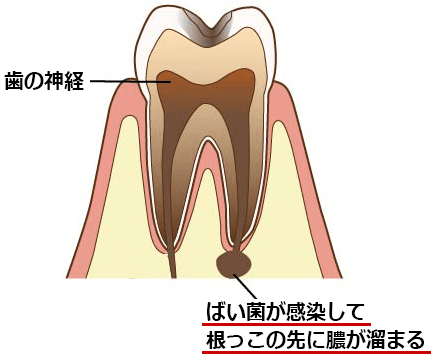
�� ���̏ꍇ�̌���
�_�o�̖������͖Ɖu�͂��Ȃ��Ȃ��Ă邽�߁A���ۂɊ������₷���Ȃ�A��������ƍ������̐悪�^��ł��܂��A���ɂ��N���邱�Ƃ�����܂��B
���Ö@
���̍������̐�ɗ��܂����^���o������A�������̓�����|�����ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B
���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B
���R�́A
�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA
�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA
�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

�����̕����ɔ^�����܂��Ă܂��B
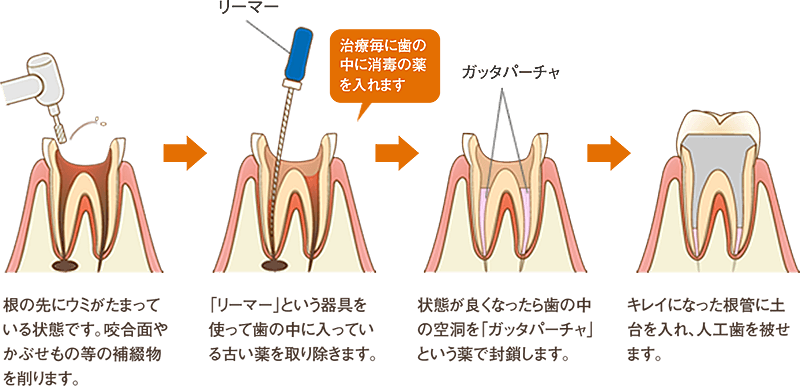
�i���Ӂj�����a�̎������l�̏ǏN���邱�Ƃ�����܂��B�܂��A���Ƀq�r���������芄��Ă�ꍇ�ɂ��N����܂��̂ŁA���Ȉ�@�Ō�����f�f���Ă�����ĉ������ˁB
����3�F �����a�̏ꍇ
�����a�ɂȂ��Ă��܂��ƁA���s�����Ă��܂��B
�܂��A���̂܂��̍����n���Ă��܂��B
�����a�ɂ͒i�K������܂����A�����炢�ȏ�ɐi�s���������a�̏ꍇ�A���Ă��܂������s���������肳������肷��ƒɂ݂��ł܂��B
�܂��A�����炢�ȏ�̎����a�ł͍���������x�n���Ă��܂��܂��̂ŁA���̏�ԂŎ����w���ʼn����Ă��܂��ƁA�ɂ݂��o�Ă��܂��܂��B

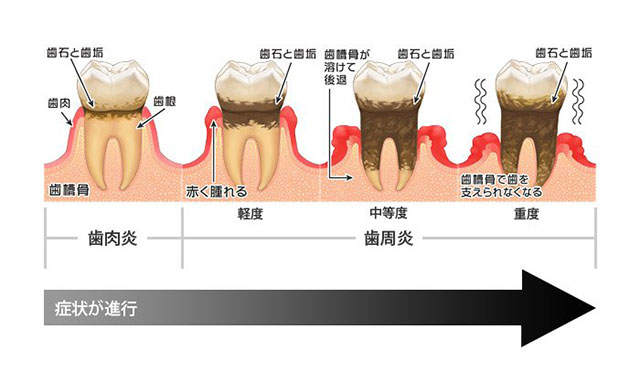
���Ö@
�����a�̎��ÂɂȂ�܂��B
�����a�͓��{�l�����������ő�̌����ł��B
���߂Ȃ玡��܂��B�K�����߂Ɏ����ĉ������B�i�s����Ǝ���ɂ����Ȃ�܂��B
����4�F ���̍������Ƀq�r�������Ă��芄�ꂽ�肵�Ă�
���Ƀq�r������Ƃ����܂�C���[�W�ł��Ȃ���������܂��A���͌��\�q�r������܂��B�Ⴂ���ł��悭�N����܂��B �q�r������̂́A�_�o�̖������̂��Ԃ����ɋN���邱�Ƃ��唼�ł��B
�����́A�_�o�̖����������Ɍ����ʂ��ĂȂ����߁A������ʂ��Ď��ɉh�{�����Ȃ��̂ŁA���̋��x�������Ă�����ł��B �i�_�o���������́u�����v�ƌ����āA�_�o�ƌ��ǂ��ʂ��Ă��܂��B�j
���x�������Ă鎕�Ŗ����ł����̂�H�ׂ�킯�ł�����A�q�r�������Ă��܂���ł��B
�����āA�q�r�����������Ŋ��ނƓ��R�ɂ���ł��B
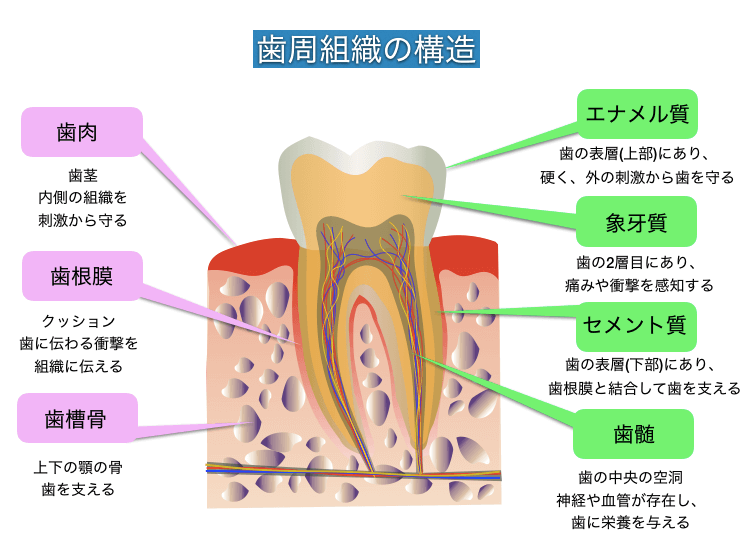
�� ��̓I�ȃq�r�̗�
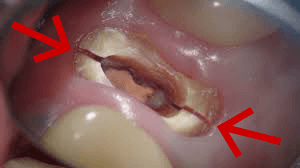
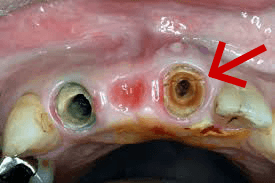
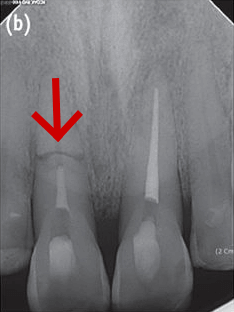

���Ö@
���̍������Ƀq�r���������ꍇ�́A�q�r�̈ʒu�ɂ���Ď��Ö@���ς��܂��B
�@�q�r���������̏�̕��ɏ������������Ă�ꍇ�̓q�r��ڒ��܂̂悤�ȕ⋭�܂Ŗ��߁A�������̒��ɏ�v�ȓy������Ă��炩�Ԃ��������������x����܂��B
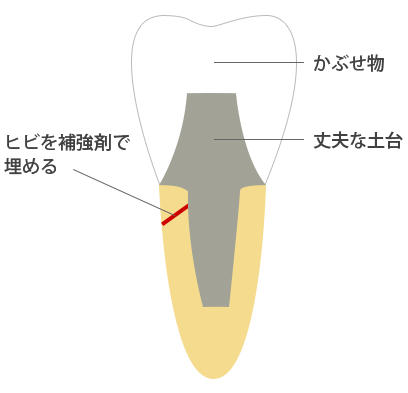
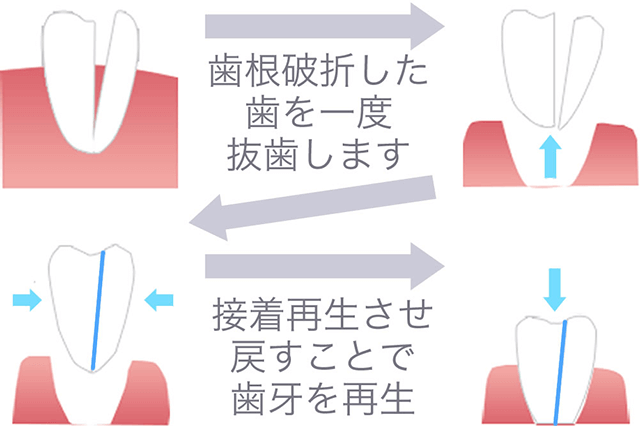
�A�q�r���������̐[���ʒu�ɓ������ꍇ�́A��x�����ăq�r��⋭�܂Ŗ��߂āA�܂����ɖ߂����Ái�ĐA�p�j�����܂��B�����A�ĐA���Ă��������Z���Ȃ邱�Ƃ������ł��B�i�ĐA�ł��Ȃ���������܂��j
�����A�q�r���[���ꍇ�̑����͎c�O�Ȃ��甲���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������ł��B
�q�r���g�勾�i�}�C�N���X�R�[�v�j���g���Ď��Â���Ǝ���m����������܂��̂ŁA�ǂ����Ă����������Ȃ����ɂ͂������߂̎��Âł��B

�����u���ɂ����ɒɂ��v�Ƃ��Ȃ�炢�ł���ˁI
�܂��A����Ȏ��̓��L�\�j���Ƃ��ɂݎ~�߂������Ȃ��ł��B
�����ƑΏ��@���킩��₷�����������܂��ˁB
�����̌��ɂ̌����͑傫��2����܂�
�����P�F
���̍������̐�ɔ^�����܂�A�^�����̒��ɂ������Ă��܂����ꍇ
�����Q�F
�������傫������ꍇ
�����̌��ɂōł������p�^�[���ł��B
�_�o����������A�_�o�����R�Ɏ���ł��܂������͖Ɖu�͂��Ȃ����߁A���ۂ��������邱�Ƃ������A���ʔ^�����܂�̂ł����A���̔^�͎��R�ɔr�o����邱�Ƃ������̂ł����A�r�o���ꂸ�ɍ��̒��ɂ��������ꍇ�͑����������ɂ݂��o�܂��B
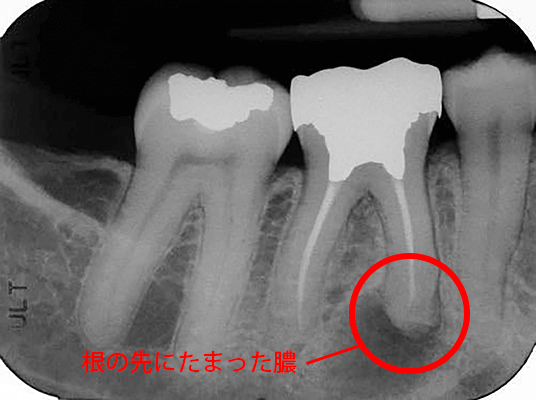
���̍������̐�ɗ��܂����^���o������A�������̓�����|�����ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B
���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B
���R�́A
�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA
�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA
�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

�����̕����ɔ^�����܂��Ă܂��B
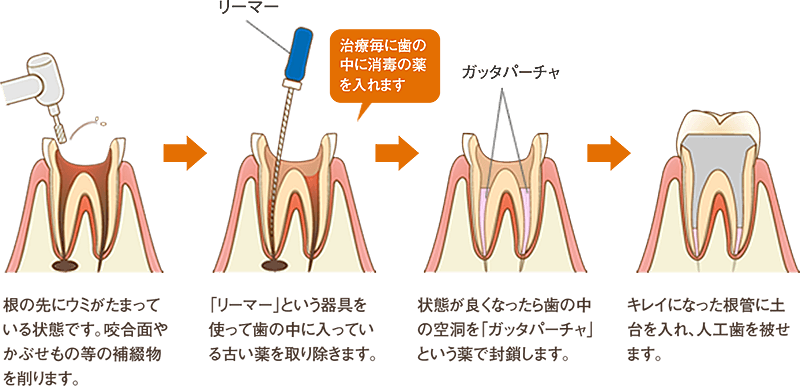
�i���Ӂj�����a�̎������l�̏ǏN���邱�Ƃ�����܂��B�܂��A���Ƀq�r���������芄��Ă�ꍇ�ɂ��N����܂��̂ŁA���Ȉ�@�Ō�����f�f���Ă�����ĉ������ˁB
�������_�o�܂Ői��ł��܂��ƁA���������������l�Ȍ��ɂ��N����܂��B
�������܂Œ������i�s���Ă��܂��ƁA���̐_�o����炴��܂���B
�_�o������Ă��܂��A���̎�̒ɂ݂͒����Ɉ����܂��B
�_�o����邱�Ƃ��i�����j�ƌ����܂��B

�ʏ�A�����̒ɂ݂ɂ͒i�K������܂����A���������̐_�o�܂ōs���Ă��܂��ƁA���Ȃ�ɂ݂܂��B
���̏ꍇ�́A���̐_�o����菜�����Â����Ȃ��Ƃ����܂���B�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����Ɏ��܂�܂��B
�ˁi���Ӂj�������A���̐_�o�͂Ȃ�ׂ����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͂Ȃ�ׂ��_�o���c���悤�w�͂����Ă��܂��B
��̓I�Ȏ��Ö@
�@�܂��A�ɂ�ł鎕�ɖ��������܂��B
���@�ł͖����͒ɂ��Ȃ��ł��܂��B�ɂ��Ȃ����R�͂������B
�A���������������������A����������Ď��A���̌㎕�̐_�o��j�̂悤�Ȋ����g���Ď��܂��B
������������������Ă�̂Œɂ݂͑S������܂���B
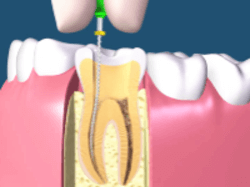
�B�_�o�����I�������A���̓����ɏ��ł̖�����āA�ӂ������ĂP��ڂ̎��Â͏I���ł��B
�C���̐_�o���������ɁA��U���ǂ��N���܂����A���ꂪ�P�`�Q�T�ԂŎ��܂�����_�o�̑���ɂȂ����l�߂܂��B

�������ʂ��Ă�̂��A�_�o�̑���ɂȂ��ł��B
���ƌ����Ă��A�j���h�����̒ɂ݂�h�����Ƃ��厖�ł��B
�����ɍׂ̐j���g���Ă���
�ːj�����ׂ��̂ŁA�����̒��Ɏh�������ɂ��킩��ɂ����B
���ɂ݂�������זE(�ɓ_)�̏��Ȃ��ӏ��ɍŏ��ɑł�
�˒ɓ_�����Ȃ��̂Œɂ݂ɂ����ł��B
���j���h���u�Ԃ́A�������̔S���ۂ̊v�̂悤�ɁA�s���ƒ����Đj����C�Ɏ������ɓ���悤�ɂ���B
�˂��̂悤�ɂ���Ɛj���h�������Ƃ��킩�炸�A���҂���ɂ́A�u�ŋ߂̖����͒��˂���Ȃ���ł����H�v�ƕ�����邱�Ƃ������ł��B


������͉t�̂Ȃ̂ʼn��x���Ⴂ�̂ł����A�������鎞�ɉ��x���Ⴂ�ƁA�̂��₽�������Ă��܂��Ɠ����ɒɂ������Ă��܂������ƂȂ�܂��B
���@�ł͂��炩�����������̉����炢�ɉ��߂Ē������܂��̂��A���җl�͋C�t����܂���̂ŁA�ɂ݂������܂���B
����ƁA�����ւ������̃X�s�[�h�����Ȃ������肵�Ă��܂��B�}���Œ�������ƁA���������Ă��܂��ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
���@�ł́A�P�H���P�b���炢�̂������Ƃ����X�s�[�h�ōs�����ŁA�����̑��ݎ��̂ɋC�t����܂���B
�P�C�Q�̏ꍇ�Ƃ��A�[�閰��Ȃ����炢�ɂ��킯�ł��̂ŁA������łł���Ώ��@�����������܂��B
�i����������}���u�ł��̂ŁA�����ɂ͎��Ȉ�@�ɍs���Ă��������ˁj
���s�̂������́A�莝���̒ɂݎ~�߂�����
�[��ł��J���Ă�h���b�O�X�g�A������A�����Œɂݎ~�߂��邩���m��܂���B
�����A��t�����̎��ɂ��Ȃ��ꍇ�͔����Ȃ��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B
�܂��A�̖�ǂŔ�������A����҂���Ȃł���������ɖ����������ނƗǂ��ł��傤�B
�L���ȃ{���^�����A���L�\�j���͂������A�C�u�A�o�t�@�����Ȃǂ��L���ł��B
�܂��A���I�ۂ𒎎��̌��ɋl�߂���@���^�ۂ͂���܂����A�����͒��Ɍ��ʂ͂���܂��B
���ɂ��ӏ����₷
��₷�����߂邩�͖����Ƃ����Ǝv���܂����A�����͂����ł��B
���ǂ��i�s���̎��͗�₵�A���̎��͉��߂�A�Ƃ������Ƃł��B
����Ȃ����炢�����ɂ��킯�ł�����A�������₷�̂��ǂ��ł��B
��₵���́A�^�I���ɂ���ۗ�܂�A���ꂪ������ΕX���ŗ�₵���^�I���Ȃǂłق��������炠�Ăė�₵�܂��B
��₷�ƁA����������A�ɂ݂������ł����y������\��������܂��B
����ԋ~�}�Z���^�[��A���Ȉ�t��̖�ԋ~�}�O���𗘗p����
�����A�n��⎞�ԑтɂ���Đf�Â��ĂȂ���������܂��̂Ŋm�F���K�v�ł��B
�����ɂɌ����c�{������
�� �ڂ����͂������������݂�̂͂��H�������ɂ������A�������������ł���ˁB

�������݂�ꍇ�͑傫���Q�̏Ǐ���܂��B
�Ǐ�P�F �₽���������݂�E�ɂ��ꍇ
�Ǐ�Q�F �M���������݂�E�ɂ��ꍇ
�ł��B���ꂼ�������Ǝ��Ö@���S�R�Ⴂ�܂��̂ŁA���J�ɂ��������܂��ˁB
�Ǐ�P�F�₽���������݂�E�ɂ��ꍇ
�₽���������݂�E�ɂ��ꍇ�͌����͂Q����܂��B
�����P �m�o�ߕq�̏ꍇ
�����Q �����炢�̑傫���̒���
����1 �m�o�ߕq�̏ꍇ
�₽�������P���ɂ��݂邱�Ƃ��u�m�o�ߕq�v�ƌ����܂��B
�_�o�ɉ��ǂ���������A����������킯�ł͂Ȃ��A�P�ɗ₽�����̂╗������������A���u���V��������Ƃ��݂��肷��Ǐ�ł��B
���̍����������茸�����A�����Ɏh���������ƋN����܂��B
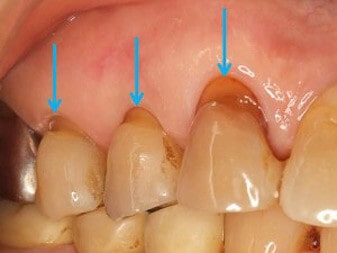
���̍����������茸�錴���͑傫��3����܂��B
���̍����������茸�錴���P�F �����͂ł̃u���b�V���O
���̍����������茸�錴���Q�F ��������E�H������
���̍����������茸�錴���R�F �����a�Ŏ��������������Ď��̍��������I�o����
���̍����������茸�錴���P�F �����͂ł̃u���b�V���O
���̓G�i�������Ƃ����d���w�ŕ����Ă��܂����A���̍������̓G�i���������_�炩���Z�����g���ɕ����Ă��܂��B
�����a�⋭���͂Ńu���b�V���O���s���ƁA���s�̈ʒu��������A�{�����s�ŕ����Ă��������Z�����g�����I�o���Ă��܂��܂��B
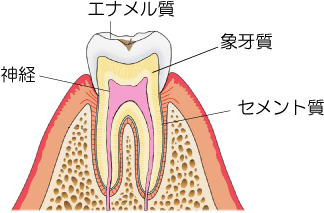
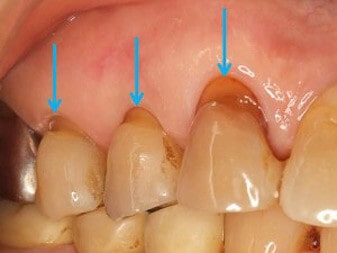
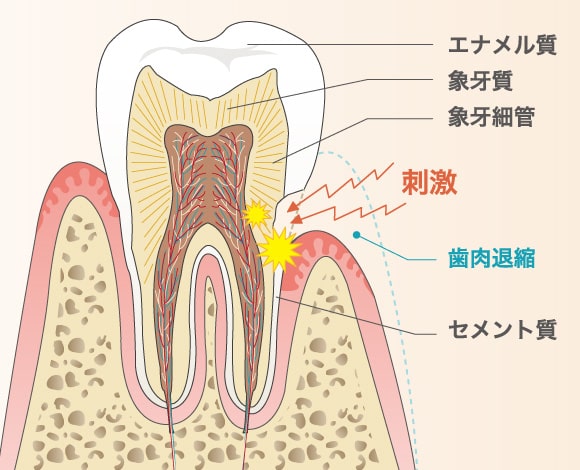
���̃Z�����g���͎��u���V�Ȃǂ��������������ƒP���ɃZ�����g�������茸���āA�ʐ^�̂悤�Ȏ��Ǝ��s�̊Ԃ����ڂ悤�ȏ�ԁi�����я��j�ɂȂ�܂��B
���̌��ʁA���̓����̏ۉ县�ɂ���ۉ�ǂƂ����_�o�ɂȂ���ׂ��������I�o���Ă��܂��A���̖����̌�����_�o�֎h�����`��邱�Ƃɂ���Ēm�o�ߕq���N����܂��B
�������������̕��@���s��Ȃ��ƏǏ������܂��B���@�ł͒��J�Ɏ������̎d�������������܂��B

���̍����������茸�錴���Q�F ��������E�H������
���������H�����������ƁA�G�i���������_�炩���Z�����g���Ɏ�������̗͂��W�����邱�Ƃɂ��A�Z�����g�������茸���Ă��܂��܂��B
���̏ꍇ�́A�l�߂�Ƃ��������Âňꎞ�I�ɉ��P����܂����A���{�I�Ȍ��������P����Ȃ��ƁA�m�o�ߕq�̏Ǐ���Ĕ����Ă��܂��܂��B
���ׁ̈A���s���Ď��������H������̎��Ái�i�C�g�K�[�h�̍쐻�j���s�Ȃ��Ă������Ƃ����X����܂��B

���Ö@
�� �l�߂���@�F���茸���Ă���Ƃ���Ɏ������l�߂�Ȃǂ��Ď����܂��B

�� �R�[�e�B���O�F��p�̃R�[�e�B���O�܂����茸���������ɓh���āA�I�o�����ۉ县�ɉ����O������̎h����}���܂��B

�� �����̏����F���������̌������������߂ɁA���݂����w���A��������h�~���u�̃i�C�g�K�[�h�i�}�E�X�s�[�X�j���g���܂��B
���̍����������茸�錴���R�F �����a�Ŏ��������������Ď��̍��������I�o����
�����a�ɂ�����ƁA�����a�ۂɂ�莕���x���鎕�������n������A�����ɂ��̏�ɂ��鎕��������ނ��A���̍����̏ۉ县���I�o���܂��B

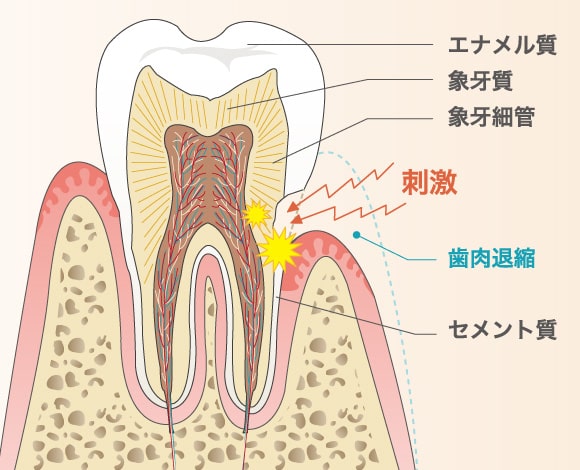
��������h�����_�o�ɓ`����Ă��݂邱�Ƃ�����܂��B���̏ꍇ�͎��C�A���̏����⎕�݂����w���Ȃǂ̎����a���Â����ĉ��P���Ă����܂��B
������菜�����ƂŁA�������Ƃ��Ƃ������Ă������̏ۉ县�̘I�o�������Ĉꎞ�I�ɒm�o�ߕq�̏Ǐ����Ă��܂����Ƃ�����܂����A���t�Ɋ܂܂��ĐΊD�������ɂ��A�ۉ�ǂ��ӂ�����A���X�ɉ��P����܂��B
���{�I�ȉ������ł��Ă��Ȃ��ƏǏi��ł��܂�������������܂ꂽ��A���������Ă��܂��Ƃ����[���ȏ�ԂɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����܂��̂ő��߂ɂ����k���������ˁB
�����Q �����炢�̑傫���̒���
�������݂�ꍇ�́A�����炢�̑傫���̒����iC2�j�������ł��邱�Ƃ������ł��B
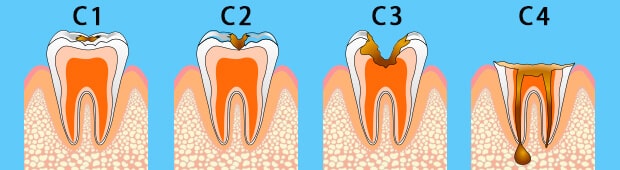
���Ö@
�b�Q�̒����̏ꍇ�́A���������������A���̕������l�߂�Ƃ����A��r�I�ȒP�ȏ��u�Ŏ���܂��B�l�ߕ��͎����Œ��ڋl�߂�ꍇ�ƁA�^�������Ă���l�ߕ�������ꍇ������܂��B
�����AC2������Ă�����C3�Ƃ����傫�������ɂȂ��Ă��܂��ƁA�_�o�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ�܂��̂ŁA�����ɂł����Ȉ�@����f����ĉ������ˁB
�N���[�o�[���Ȃ͒����̎��Â͖��Ɏ��Âōs���Ă���܂��̂ŁA���S���Ă��������B
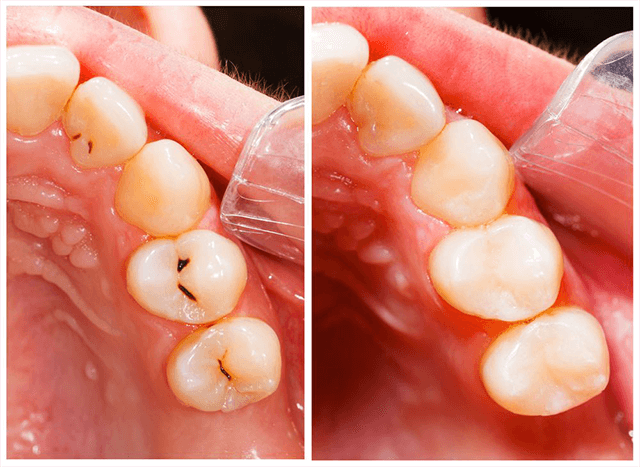
�� �����������Œ��ڋl�߂��ꍇ

�� �������^�������č�����l�ߕ��ŋl�߂��ꍇ
�Ǐ�Q�F�M���������݂�E�ɂ��ꍇ
�M�����̂�H�ׂ����ɂ��݂�ꍇ�́A�₽���������݂�ꍇ���d�ǂł��B
�˔M���������݂�E�ɂ������͂Q�l�����܂�
����1 ���������Ȃ�i�s���Ď��̐_�o�����ǂ��N�������ꍇ�i�������j
���������������́A�₽�����̂ŏ������݂���x�ł����A���������Ȃ�i�s����Ɛ_�o���傫�ȉ��ǂ��N�����A�M�����̂ł��݂���ɂ肵�܂��B
�M�����̂Œɂ��ꍇ�͉��ǂ������̂ŁA���̏ꍇ�͎c�O�Ȃ���A�_�o�����Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ƃ������ł��B
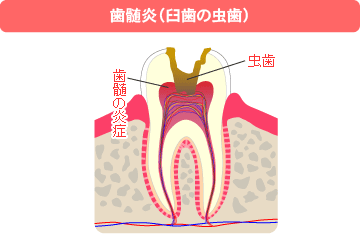
�����Q �����̋l�ߕ��₩�Ԃ��������Ă���ꍇ
�⎕�Ȃǂ����Ă�ꍇ�́A�����͔M��ʂ��₷���̂ŁA�M�����̂̎h�����`���₷���ł��B
�_�o�������Ă��鎕�̋����̋l�ߕ��̏ꍇ�́A�������M�����x��ʂ��Ă��܂��A�_�o�܂ŔM���͂��₷���Ȃ�܂��B
�����A���Ò���ŔM�����̂��ɂ��ꍇ�͂P�T�Ԃ��炢�Ŏ��邱�Ƃ������ł��B

�M�����̂Œɂ��ꍇ�́A�ً}���������̂ő�������҂ɍs���������ǂ��I
�M�����̂��ɂ��ꍇ�́A���R�͂���������܂����A��������d�ǂ̎��������ł��B
�d�ǂ���u����ƁA����Ɉ������Č��ɂ��N������A�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�\���������̂ŁA�����ɂł�����҂ɍs���������ǂ��ł��B
�˂��̏ꍇ�́A�Ǐ�5�l�����܂�
�Ǐ�P�F �_�o���������Ŋ��ނƒɂ�
�Ǐ�Q�F �_�o�������A�_�o���Ò��Ɋ��ނƒɂ�
�Ǐ�R�F �������傫���ꍇ�⒎���̎��Ì�A���ނƒɂ�
�Ǐ�S�F ����������Ċ��ނƒɂ�
�Ǐ�T�F ���ނƎ��⓪���ɂ�
�Ǐ�P�F�_�o���������Ŋ��ނƒɂ�
�˂��̏ꍇ�́A�������Q�l�����܂�
�����P�F �_�o���������̍������̐�ɔ^�����܂��Ă���
�����ɒɂ��̂́A�������₩�Ԃ����ɋN���邱�Ƃ������ł��B�������₩�Ԃ����͐_�o���������ɂ��鏈�u�ł����A�_�o�̖������́A���ۂɊ������₷���̂ł��B
�Ȃ��_�o�̖��������������₷�������������܂��ˁB
�܂������Ȗ��O�������i�������j�ƌ����܂��B
�����āA�����̒��ɂ͖{���ɐ_�o���ʂ��Ă邵�A���ǂ��ʂ��Ă܂��B
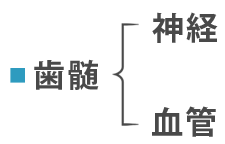
����ł��Ă��܂��B
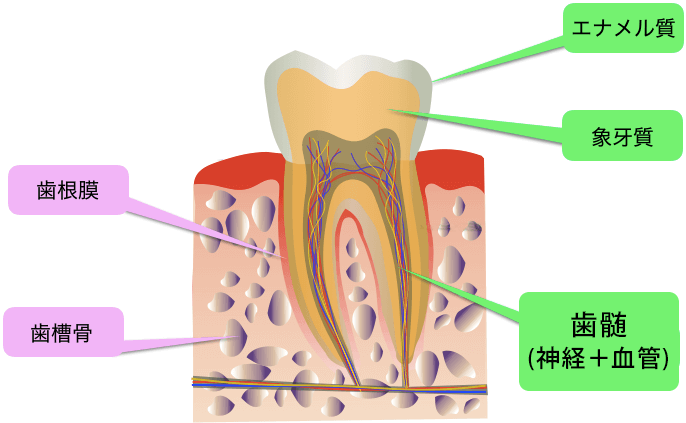
�ł��̂ŁA��������������Ƃ����̂́A���̒�����A�_�o�����łȂ����ǂ��Ȃ��Ȃ��Ă��ł��B
���ǂ̒��ɂ͔������Ȃǂ̖Ɖu�זE������A���ۂ�������Ă��܂��B
�Ƃ��낪�A�������Ă��܂��ƁA���̒�����Ɖu�זE�����Ȃ��Ȃ�A���̒��ɂ��ۂ������ė��Ă�������邱�Ƃ��ł����ɁA�������ĉ��ǂ��N�����Ă��܂���ł��B
��������Ď��̓����ɋN���������ǂ͍������̐���ۂ��獜�̒��ɐi��ōs���܂��B
�����āA���̍������̐���ۂɔ^�����܂��Ă��āA����A�@�����肵�����ɒɂ��̂ł��B
���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B
���R�́A
�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA
�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA
�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B
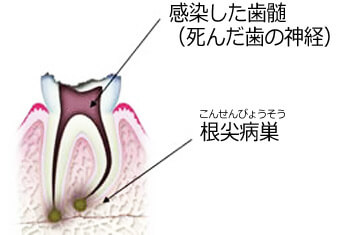

���Ö@
���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B
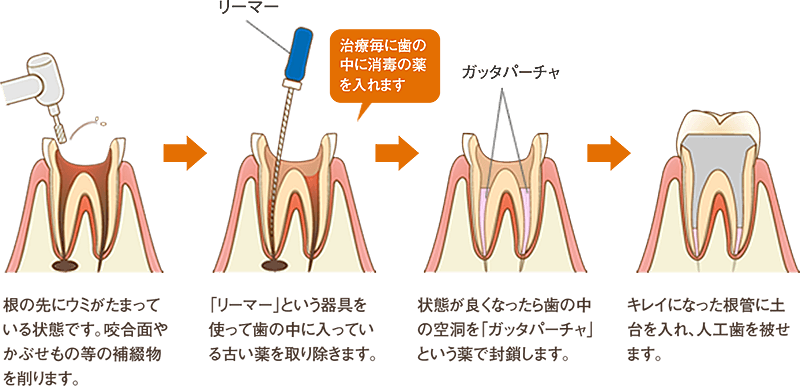
�����Q�F ���̍������Ƀq�r�������Ă��芄�ꂽ�肵�Ă�
���Ƀq�r������Ƃ����܂�C���[�W�ł��Ȃ���������܂��A���͌��\�q�r������܂��B�Ⴂ���ł��悭�N����܂��B �q�r������̂́A�_�o�̖������̂��Ԃ����ɋN���邱�Ƃ��唼�ł��B
�����́A�_�o�̖����������Ɍ����ʂ��ĂȂ����߁A������ʂ��Ď��ɉh�{�����Ȃ��̂ŁA���̋��x�������Ă�����ł��B �i�_�o���������́u�����v�ƌ����āA�_�o�ƌ��ǂ��ʂ��Ă��܂��B�j
���x�������Ă鎕�Ŗ����ł����̂�H�ׂ�킯�ł�����A�q�r�������Ă��܂���ł��B
�����āA�q�r�����������Ŋ��ނƓ��R�ɂ���ł��B
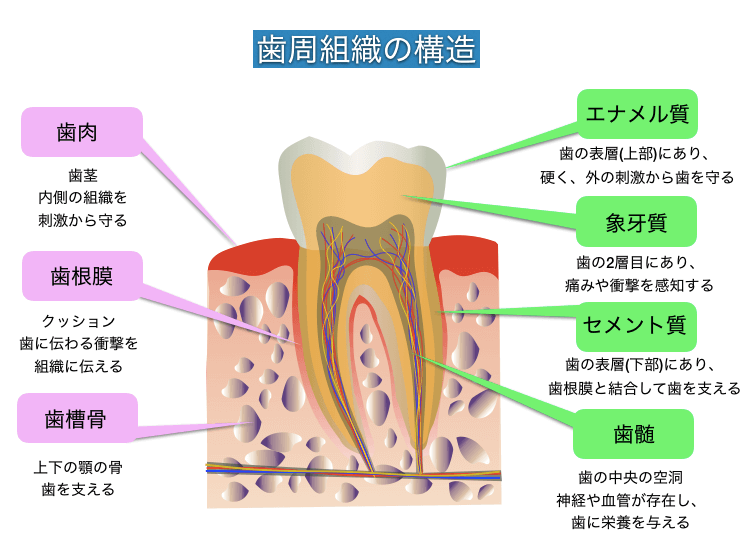
�� ��̓I�ȃq�r�̗�
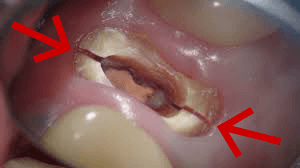
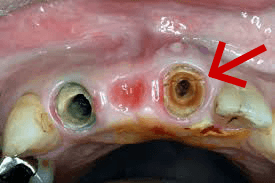
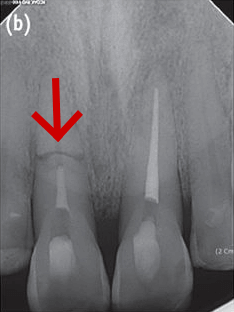

���Ö@
���̍������Ƀq�r���������ꍇ�́A�q�r�̈ʒu�ɂ���Ď��Ö@���ς��܂��B
�@�q�r���������̏�̕��ɏ������������Ă�ꍇ�̓q�r��ڒ��܂̂悤�ȕ⋭�܂Ŗ��߁A�������̒��ɏ�v�ȓy������Ă��炩�Ԃ��������������x����܂��B
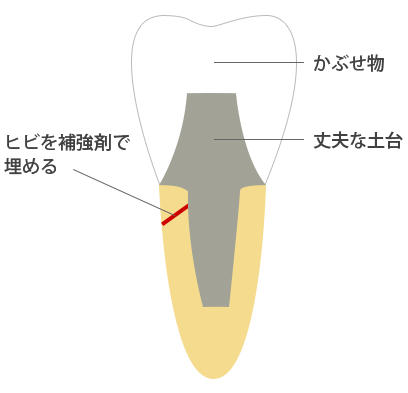
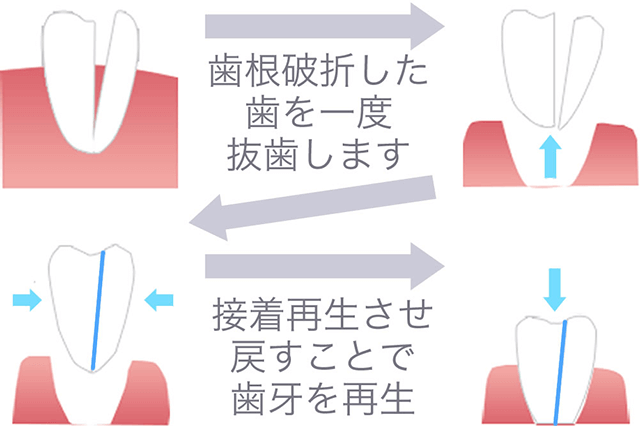
�A�q�r���������̐[���ʒu�ɓ������ꍇ�́A��x�����ăq�r��⋭�܂Ŗ��߂āA�܂����ɖ߂����Ái�ĐA�p�j�����܂��B�����A�ĐA���Ă��������Z���Ȃ邱�Ƃ������ł��B�i�ĐA�ł��Ȃ���������܂��j
�����A�q�r���[���ꍇ�̑����͎c�O�Ȃ��甲���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������ł��B
�q�r���g�勾�i�}�C�N���X�R�[�v�j���g���Ď��Â���Ǝ���m����������܂��̂ŁA�ǂ����Ă����������Ȃ����ɂ͂������߂̎��Âł��B

�Ǐ�Q�F�_�o�������A�_�o���Ò��Ɋ��ނƒɂ�
�˂��̏ꍇ�́A�������Q�l�����܂�
�����P�F ���̐_�o�����Â��������A�_�o�������Ǝ��ꂸ�Ɏc���Ă���
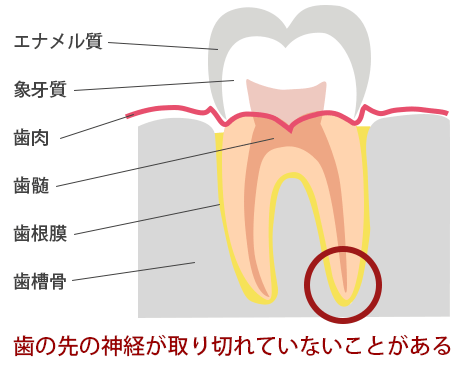
���Ö@
���̏ꍇ�́A��x���Ԃ������Ԃ�����P�����A���c���ꂽ�_�o�����S�Ɏ�菜�����Â��s���܂��B
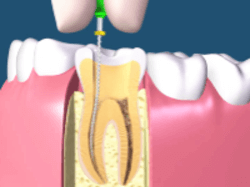
�����Q�F ���̐_�o�͔��ɍׂ����}�����ꂵ�Ă���A���̍������̊������}������̕����܂Ői��ł���ꍇ
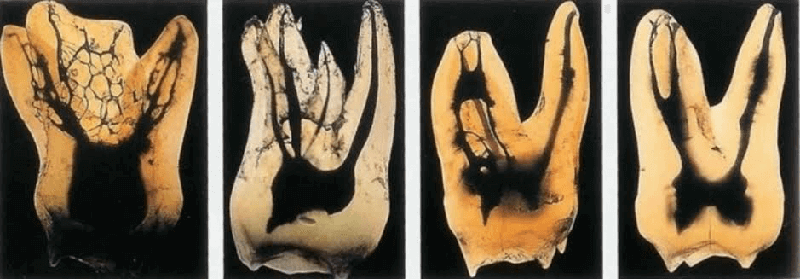
��}�̂悤�ɁA���̐_�o�ׂ͍��Ē����āA�}�����ꂵ�Ă��āA���������ۂŊ������Ă��܂��ƁA�����ɒɂ݂��o����A�_�o���������������ɂ݂��������肵�܂��B
�����Ȃ�ƁA���ʂ̐_�o���Âł͎���Â炭�Ȃ�܂��B
���Ö@
�}�C�N���X�R�[�v�Ƃ������̓��������錰�������g���Ē��J�Ɏ��Â��邱�Ƃ��厖�ł��B
�}�C�N���X�R�[�v�Ƃ͈�×p�̌������̎��ł��B�]�O�Ȃ�S���O�Ȃł͌������Ȃ��ŐV�@��ł��B���̓�����12�{����20�{�Ɋg�債�Ď������s���܂��B

�� �}�C�N���X�R�[�v���g���ƁA���̓������������悭�����܂��B
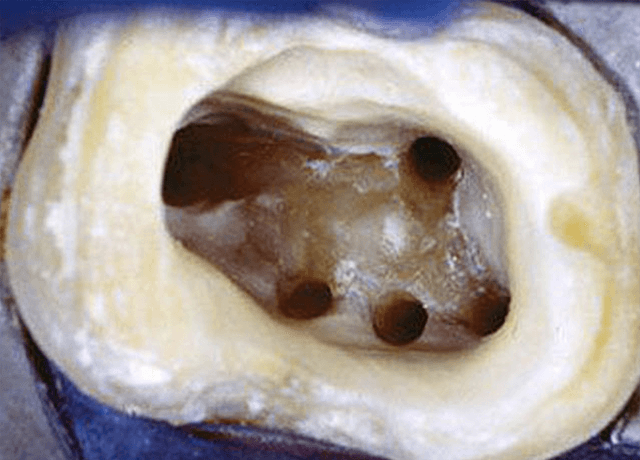
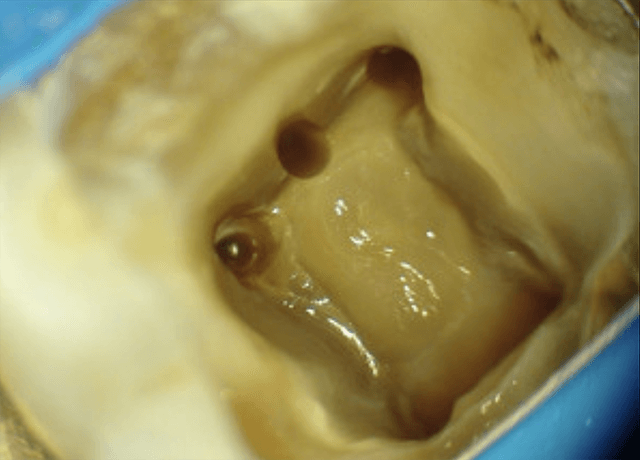
���ۂ��_�o�̊ǁi�����j�ׂ̍��Ƃ���ɂ����ꍇ�A���ʂɓ���Ŏ��Â��Ă����̂ł́A���c���\�������Ȃ荂���ł��B
�����Ȃ�ƁA�ɂ݂���̌����ɂȂ�A�������̐�ɔ^�݂����܂��Ă��܂��܂��B
���G�Ȏ��̐_�o�̓����̂��ׂĂ𐴑|���āA���ۂ�����Ȃ��Ƃ����Ȃ���ł��B
���{�ł́A�܂��܂��}�C�N���X�R�[�v���g�����Ȃ��鎕�Ȉ�t�͂��Ȃ菭�Ȃ��ł��B
�A�����J�ɂ͍��ǎ��Ð��オ�������܂����A���{�͂��̓_�͒x��Ă邩�Ǝv���܂��B
�� �}�C�N���X�R�[�v���g�����Ȃ����@
�Ǐ�R�F�������傫���ꍇ�⒎���̎��Ì�A���ނƒɂ�
�����̎��Ì�A����Œɂ��ꍇ�͈ȉ��̌������l�����܂��B
�����F ����������ċl�ߕ��������̂����A�������傫���Đ_�o�M���M���܂Ŏ�����������ʁA�_�o�Ɏh����^���Ă�����

�� �傫�Ȓ���

�� �傫�Ȓ����ɋl�ߕ��������Ƃ���
���Ö@
�@ ��x�l�߂��l�ߕ���P�����āA���������S�Ɏ�菜���ꂽ�̂����`�F�b�N���܂��B�����A�������c���Ă�������S�Ɏ�菜������ŁA�Ăыl�ߕ������܂��B
�A ��x�l�߂��l�ߕ���P�����āA���������S�Ɏ�菜���ꂽ�̂����`�F�b�N���܂��B�����A�������c���Ă��Ȃ��̂ɒɂ�ł�ꍇ�́A�_�o��ی삷����h������ŁA�Ăыl�ߕ������܂��B
�B �@��A�̎��Â��s�����̂ɒɂ݂����Ȃ��ꍇ��A�ɂݎ��̂����Ȃ苭���ꍇ�́A�d���Ȃ����̐_�o�����܂��B�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����܂�܂��B�����A���̐_�o�͂Ȃ�ׂ����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͋ɗ͎c���悤�ɂ��Ă��܂��B
�Ǐ�S�F����������Ċ��ނƒɂ�
�����O���O���̎��Ɋ���ɂ݂��o�₷���ł��̂ł����A���̏ꍇ�������a�������̂��Ƃ��唼�ł��B
�����F �����a
�����a�Ƃ����̂́A���̎���ɕt�������ۂɂ���Ď��s�����ǂ��N��������A�����n����a�C�ł��B
�����a�͏����̏ꍇ�́A����ł��ɂނ��Ƃ͂��܂肠��܂��A���̗n����ʂ�������x�̃��C�����Ă���ƁA�����ɒɂ݂��o�܂��B
�ł��̂ŁA�����a�������Ŋ���Œɂ݂��o��̂́A�����n����̂����Ȃ�i��ł������ƂɂȂ�܂��B
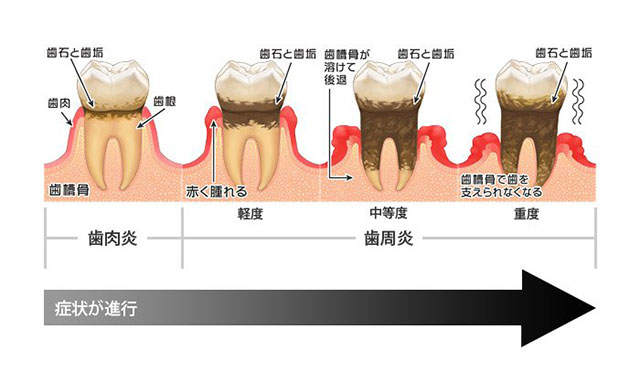
���Ö@
���Ö@�Ƃ��ẮA�ŏ��Ɋ��҂���Ɏ��ȉq���m���������w�����s���āA���҂����ɂȂ�A�����Ƃ�܂��i�X�P�[�����O�j�B
���̌�A���s�̒��̎����Ă��˂��Ɏ��܂��i���[�g�v���[�j���O�j�B
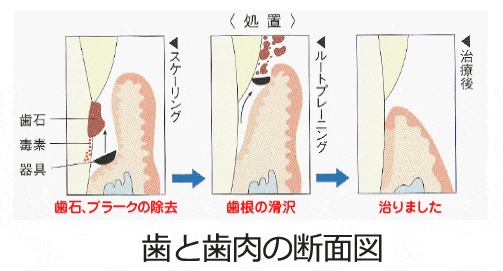
��������ƒ����炢�܂ł̎����a�Ȃ玡���Ă��܂����A����Ȃ��ꍇ�͎��s�̎�p�i�t���b�v��p�j���s���Ď����Ă����܂��B
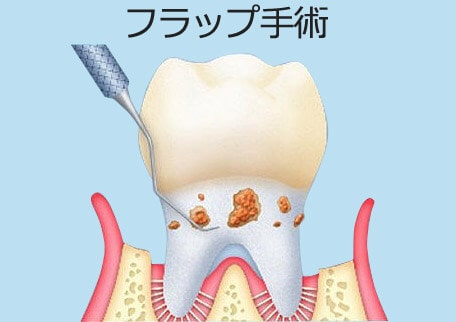
�Ǐ�T�F���ނƎ��⓪���ɂ�
�˂��̏ꍇ�́A�{�ߏ��������̏ꍇ���唼�ł�
�����Ɏ����ɂ��Ȃ�����A���@�Ȃɍs���̂����Ȃɍs���̂������܂���ˁI �ł��A���̏ꍇ�̓A�S�̊߂ɖ�肪�����{�ߏ��̂��Ƃ����ɑ����̂ŁA�܂������Ȉ�@�ɂ����̂������ł��B
�{�ߏǂ̎��́A�����ɁA���̕t������A���̉��A���̒���A����ɂނ��Ƃ�����܂��B�i�{�ߏǂ̒��Ȃ��悤�ł���Ύ��@�Ȏ�f���K�v�ɂȂ�܂��j
�{�ߏǂƂ́H
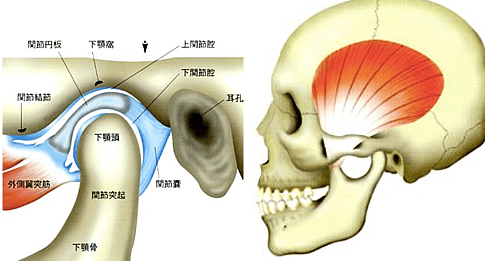
�A�S�̊߂ɂ́A�_�o�A�ؓ����W�����Ă��܂��B�܂��߂́A�߉~�Ƃ����N�b�V��������Ċ��|�i���{�|�j�Ɛڂ��Ă��܂��B�����̑g�D�Ɉُ킪�N����A�ɂ݂��o����A�����ɂ����Ȃ����肷��̂��{�ߏǂł��B
���Ö@
�@���퐶��
�d���������ׂ�̂��T����A�L�w��j�����߂�B
�㉺�̎������ӎ��ɐڐG���Ă�̂ɋC�t�������߂�A�X�g���X�������Ȃ��l�ɂ���A�Ȃǂ��厖�ł��B
�A�}�E�X�s�[�X����
���̊��ݍ��킹�������Ŋ{�ߏǂ��N���邱�Ƃ������̂ŁA���ݍ��킹�̒����i���Áj���܂��͂�����ŁA�}�E�X�s�[�X�������̒��ɓ���āA�߂ɂ�����h���╉�S���y�����Ď����Ă����܂��B
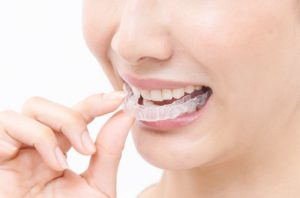
���͒ɂ��Ȃ����ǁA����������������Ƃ������Ƃ�����܂��B����́A�ǂ��������ۂ����������܂��B
���ƍ��̊Ԃɂ͎������Ƃ����g�D�������āA������n�����b�N�Ŏ����Ԃ牺�����Ă銴���ɂȂ��Ă��āA���ƍ��̊Ԃ̃N�b�V�����̖�ڂ����Ă��܂��B
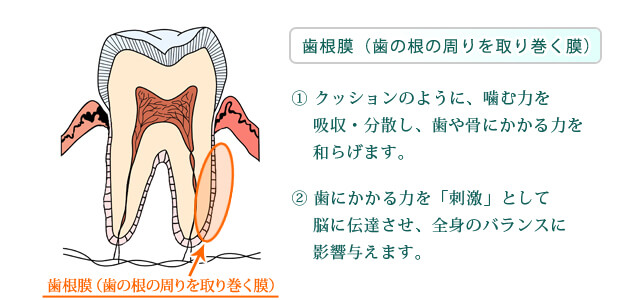
���ɋ����͂��������Ă��܂��Ď������ɕ��S����������A�����������s��Q���N��������A���ۂɊ��������肵�����ȂǂɁA����������ꂠ����A���ۂɂ͏����ł����A���������グ�Ă��܂��Ă�̂ł��B
���������Ēɂ��S�̑傫�Ȍ���
����1�F ���̐_�o����������A�_�o�����̂܂ɂ�����ł��܂������ɋN����₷��
�_�o�̖������͖Ɖu���Ȃ����߂ɁA���ۂ��������₷���ł��B
���ۂ���������ƁA���̍������̐�ɉ��ǂ��i��ł����A�������玕�����ɉ��ǂ��g�����Ď����������N�����A���������������ɂȂ�܂��B
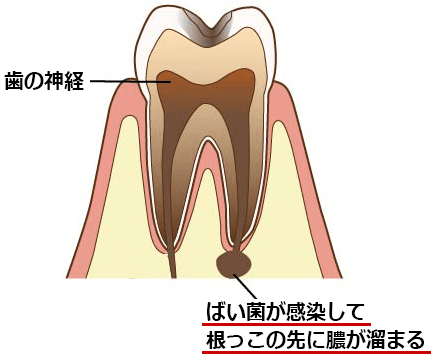
���Ö@
���̍������̐�ɗ��܂����^���o������A�������̓�����|�����ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B
���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B
���R�́A
�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA
�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA
�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

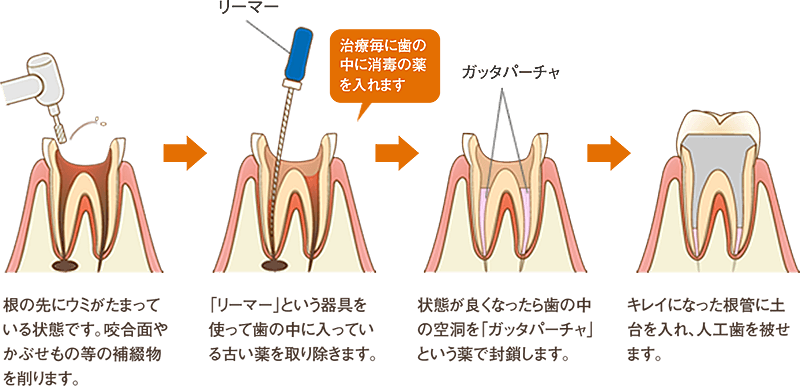
�����Q�F �����a�̏ꍇ
�����a�ɂȂ�ƁA���ۂɂ���Ď����������Ă�����A�o��������A�^���o���肵�܂��B������������ƁA�����オ�点�Ă��܂��̂ł��B
���̏ꍇ�́A���}�����a�̎��Â�����K�v������܂��B

����3�F ��������Ȃǎ��ɋ����͂����������ꍇ
���ƍ��̊Ԃɂ͎������Ƃ����N�b�V����������̂ł����A���������H������̂悤�Ɏ��ɋ����͂��������Ă��܂��ƁA���̗͂�����h���Ԃ�A�����������������Ă��܂��A���������悤�Ɋ����邱�Ƃ�����܂��B
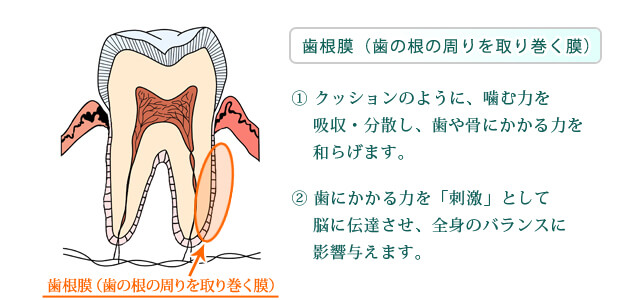
���Ö@
�������肪�Ђǂ��ꍇ�́A�}�E�X�s�[�X�����܂��B
�}�E�X�s�[�X�ɂ���āA���ɒ��ڂ�����͂�}������A���U������ł��A�������ɗ^����͂����炵�Ă����܂��B
�H������̏ꍇ�́A�����ł�������ӎ����ĐH����������Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ���ł��B
����4�F �X�g���X���J����������
�X�g���X���J�����������́A�g�̖̂Ɖu�זE�̗͂������܂��B��������ƁA���������ӂɂ������ۂ��\�ꂾ���A�������ɉ��ǂ��g���Ă��܂��܂��B
�܂��A�X�g���X�A��J�͌�������p�̗�����������܂��B��������p�̗��ꂪ�����Ȃ�ƁA�������������łȂ��A���ɁA������A���ӊ��Ȃǂ��N���邱�Ƃ������ł��B
���Ɏ����ア���́A�X�g���X��J�����������Ƃ����Ǐ�ɂȂ��ĕ\��₷���ł��B
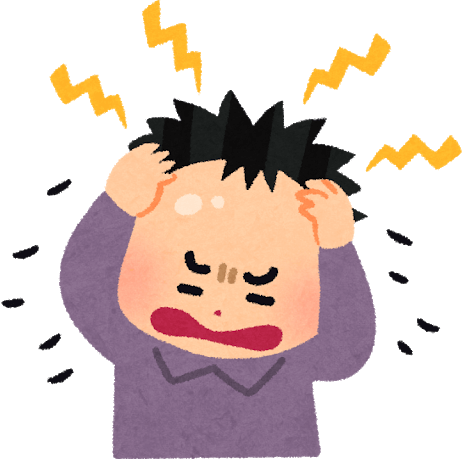
���Ö@
�������A�X�g���X����菜�����Ƃ��厖�ł��B�X�g���X�͖��a�̌��ł�����܂��B
�܂��A��J�Ɋւ��ẮA�ߓx�Ȃ��d��������A�O��͔����A��ꂽ�炷���Q��Ȃǂ̑������Ă��������B
�܂��A�S�g�̌��s��ǂ����邽�߁A�K�x�ȉ^����X�g���b�`���L���ł��B


�˂��̏ꍇ�́A�������S�l�����܂��B
�����P ��Ԃ悭����̂́A�����a�ł�
�����Q ���̍������̐�ɔ^�����܂��Ă���
����1�F ��Ԃ悭����̂́A�����a�ł�
�����a�ɂȂ��Ă��܂��ƁA���s�����Ă��܂��B
�܂��A���̂܂��̍����n���Ă��܂��B
�����a�ɂ͒i�K������܂����A�����炢�ȏ�ɐi�s���������a�̏ꍇ�A���Ă��܂������s���������肳������肷��ƒɂ݂��ł܂��B
�܂��A�����炢�ȏ�̎����a�ł͍���������x�n���Ă��܂��܂��̂ŁA���̏�ԂŎ����w���ʼn����Ă��܂��ƁA�ɂ݂��o�Ă��܂��܂��B

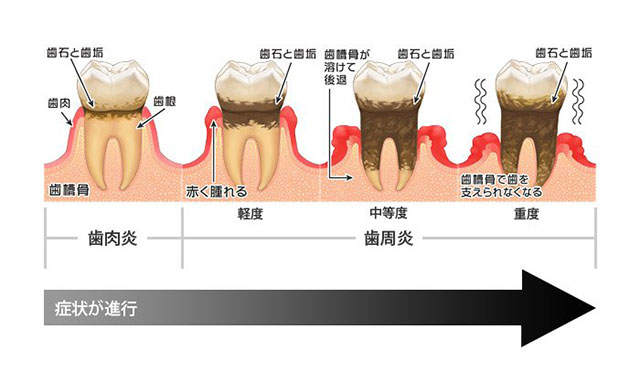
���Ö@
�����a�̎��ÂɂȂ�܂��B
�����a�͓��{�l�����������ő�̌����ł��B
���߂Ȃ玡��܂��B�K�����߂Ɏ����ĉ������B�i�s����Ǝ���ɂ����Ȃ�܂��B
�����Q�F ���̍������̐�ɔ^�����܂��Ă���
�� ���̏ꍇ�̌���
���̏Ǐ�́A�������₩�Ԃ����ɋN���邱�Ƃ������ł��B�������₩�Ԃ������_�o���������ɂ��鏈�u�ł����A�_�o�̖������́A�Ɖu�͂������̂ł��ۂɊ������₷���̂ł��B
�������N����ƁA���̍������̐���ۂɔ^�����܂�A���⎕�̍������̂�����������ƒɂނ�ł��B
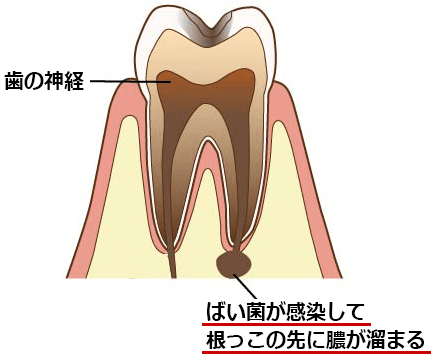
���Ö@
���̍������̐�ɗ��܂����^���o������A�������̓�����|�����ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B
���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B
���R�́A
�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA
�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA
�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

�����̕����ɔ^�����܂��Ă܂��B
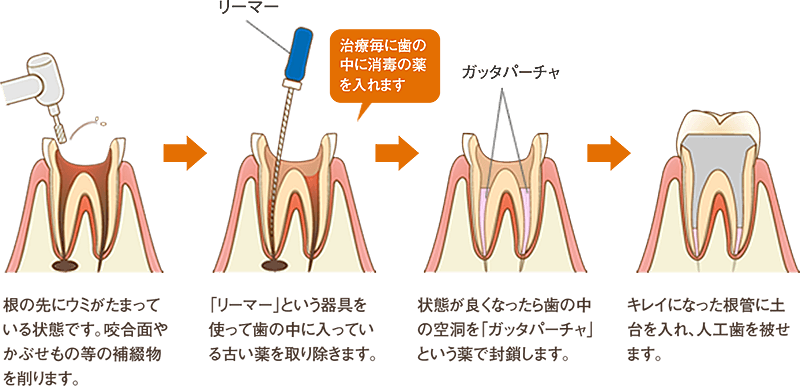
����3�F ���̍������Ƀq�r�������Ă��芄�ꂽ�肵�Ă�
���Ƀq�r������Ƃ����܂�C���[�W�ł��Ȃ���������܂��A���͌��\�q�r������܂��B�Ⴂ���ł��悭�N����܂��B �q�r������̂́A�_�o�̖������̂��Ԃ����ɋN���邱�Ƃ��唼�ł��B
�����́A�_�o�̖����������Ɍ����ʂ��ĂȂ����߁A������ʂ��Ď��ɉh�{�����Ȃ��̂ŁA���̋��x�������Ă�����ł��B �i�_�o���������́u�����v�ƌ����āA�_�o�ƌ��ǂ��ʂ��Ă��܂��B�j
���x�������Ă鎕�Ŗ����ł����̂�H�ׂ�킯�ł�����A�q�r�������Ă��܂���ł��B
�����āA�q�r�����������Ŋ��ނƓ��R�ɂ���ł��B
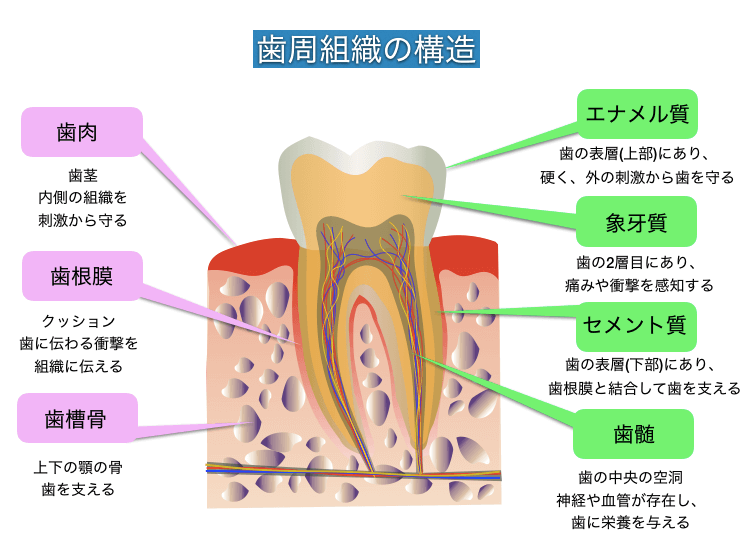
�� ��̓I�ȃq�r�̗�
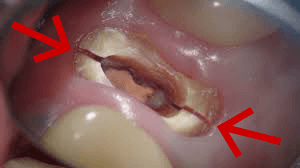
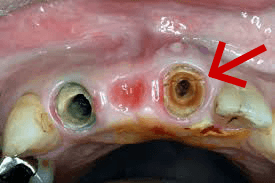
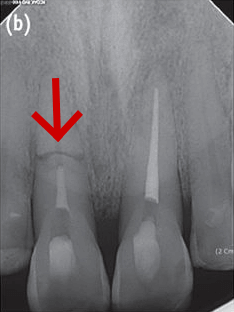

���Ö@
���̍������Ƀq�r���������ꍇ�́A�q�r�̈ʒu�ɂ���Ď��Ö@���ς��܂��B
�@�q�r���������̏�̕��ɏ������������Ă�ꍇ�̓q�r��ڒ��܂̂悤�ȕ⋭�܂Ŗ��߁A�������̒��ɏ�v�ȓy������Ă��炩�Ԃ��������������x����܂��B
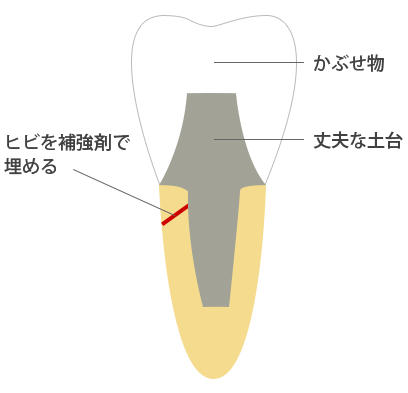
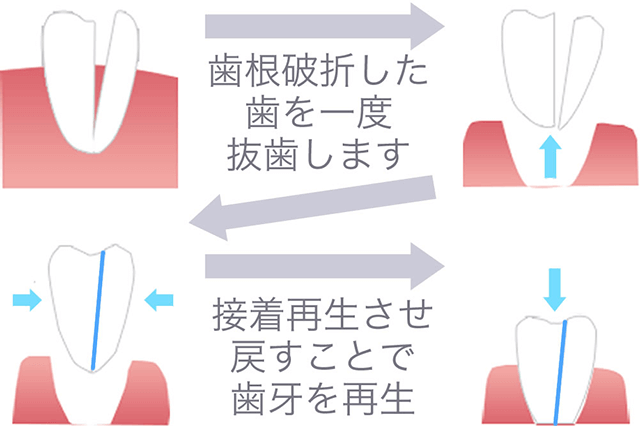
�A�q�r���������̐[���ʒu�ɓ������ꍇ�́A��x�����ăq�r��⋭�܂Ŗ��߂āA�܂����ɖ߂����Ái�ĐA�p�j�����܂��B�����A�ĐA���Ă��������Z���Ȃ邱�Ƃ������ł��B�i�ĐA�ł��Ȃ���������܂��j
�����A�q�r���[���ꍇ�̑����͎c�O�Ȃ��甲���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������ł��B
�q�r���g�勾�i�}�C�N���X�R�[�v�j���g���Ď��Â���Ǝ���m����������܂��̂ŁA�ǂ����Ă����������Ȃ����ɂ͂������߂̎��Âł��B

����4�F ��������Ȃǎ��ɋ����͂����������ꍇ
���ƍ��̊Ԃɂ͎������Ƃ����N�b�V����������̂ł����A���������H������̂悤�Ɏ��ɋ����͂��������Ă��܂��ƁA���̗͂�����h���Ԃ�A�����������������Ă��܂��A�������ɕ��S������������ԂɂȂ�܂��B
����Ȏ��Ɏ��������ƒɂ݂������邱�Ƃ�����܂��B
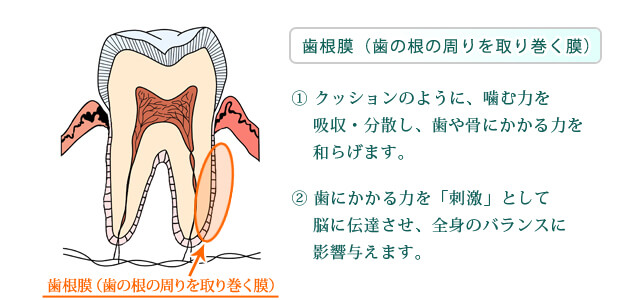
���Ö@
�������肪�Ђǂ��ꍇ�́A�}�E�X�s�[�X�����܂��B
�}�E�X�s�[�X�ɂ���āA���ɒ��ڂ�����͂�}������A���U������ł��A�������ɗ^����͂����炵�Ă����܂��B
�H������̏ꍇ�́A�����ł�������ӎ����ĐH����������Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ���ł��B
�˂��̏ꍇ�́A�������R�l�����܂�
�����P�F ���̍������̂܂��ɔ^�����܂��Ă���
����҂Ő̎��Â��Ă��Ԃ��������������ɂ��Ƃ������Ƃ́A���\�悭����܂��B
���̌����̂قƂ�ǂ́A���ۂɂ�銴���ł��B
�����������Ԃ���������Ƃ������Ƃ́A���̐_�o��������ꍇ�Ȃ�ł��B
���̐_�o����邽�߂ɂ́A����傫�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł����A���ׂ̈ɁA�_�o���������ŁA���̎��͂����ۂ�Ƃ��Ԃ��邩�Ԃ����ɂ���킯�ł��B�i�O���̏ꍇ�̂��Ԃ����͍������Ƃ��Ăт܂��j
�����āA�_�o�������Ƃ������Ƃ́A���ɖƉu�������Ȃ��Ă��܂��܂��̂ŁA�������N����킯�ł��B
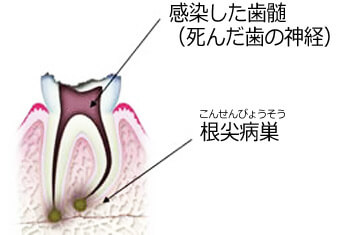

�������i�ނƁA�������̐�ɔ^�����܂�܂��B
���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B
���R�́A
�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA
�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA
�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B
���Ö@
���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B
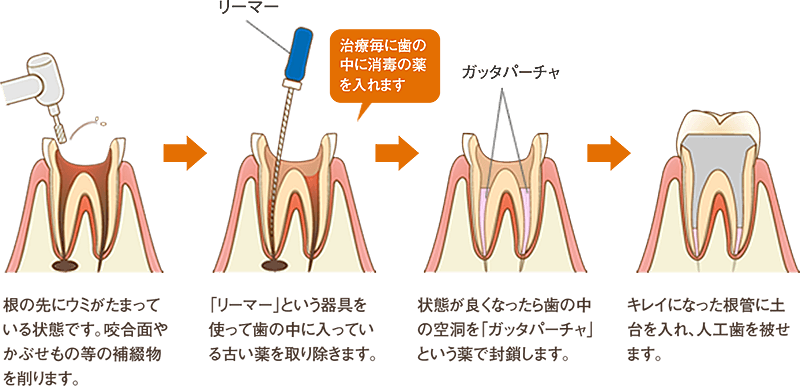
�����Q�F ���̍������Ƀq�r�������Ă��芄�ꂽ�肵�Ă�
���Ƀq�r������Ƃ����܂�C���[�W�ł��Ȃ���������܂��A���Ԃ����́A���\���̍������Ƀq�r������܂��B
�Ⴂ���ł��悭�N����܂��B
���R�́A���������Ȃ�ł��Ԃ��������邩�ƌ����Ǝ��̐_�o���������́A���x�I�ɂ��Ԃ��Ȃ��Ǝ����Ȃ��̂ł��Ԃ���킯�ł��B
�܂�A���Ԃ����͐_�o���Ȃ��̂ł��B
�_�o�̖����������Ɍ����ʂ��ĂȂ����߁A������ʂ��Ď��ɉh�{�����Ȃ��̂ŁA���̋��x�������Ă���ł��B �i�_�o�́A�������́u�����v�ƌ����āA�_�o�ƌ��ǂ��ʂ��Ă��܂��B�j
���x�������Ă鎕�Ŗ����ł����̂�H�ׂ�킯�ł�����A�q�r�������Ă��܂���ł��B
�����āA�q�r�����������Ŋ��ނƓ��R�ɂ���ł��B
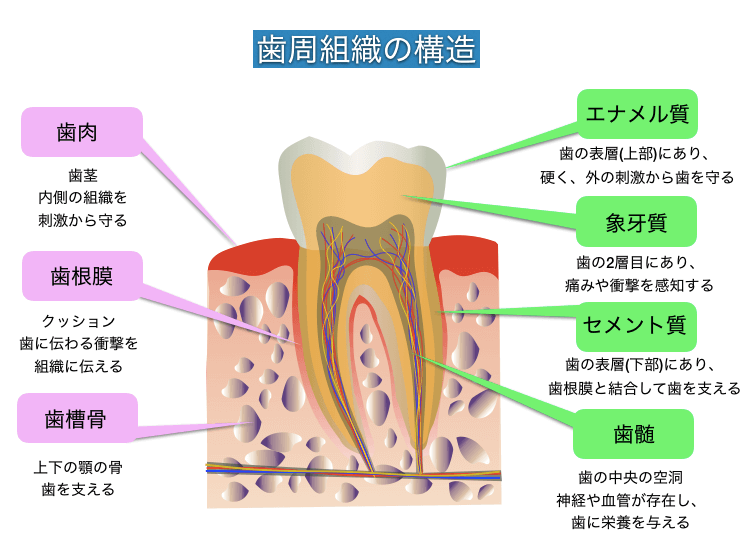
�� ��̓I�ȃq�r�̗�
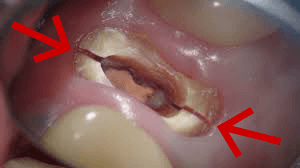
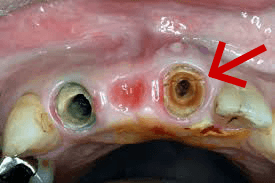
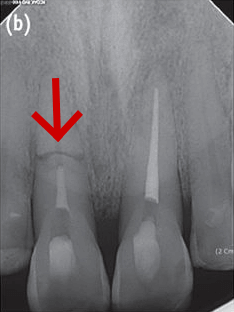

���Ö@
���̍������Ƀq�r���������ꍇ�́A�q�r�̈ʒu�ɂ���Ď��Ö@���ς��܂��B
�@�q�r���������̏�̕��ɏ������������Ă�ꍇ�̓q�r��ڒ��܂̂悤�ȕ⋭�܂Ŗ��߁A�������̒��ɏ�v�ȓy������Ă��炩�Ԃ��������������x����܂��B
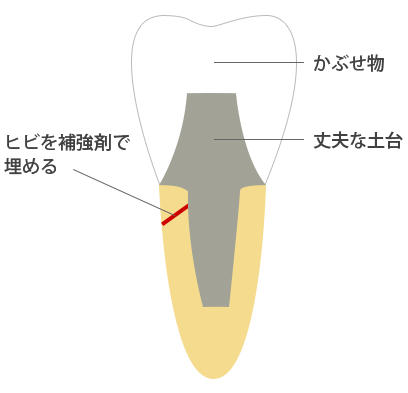
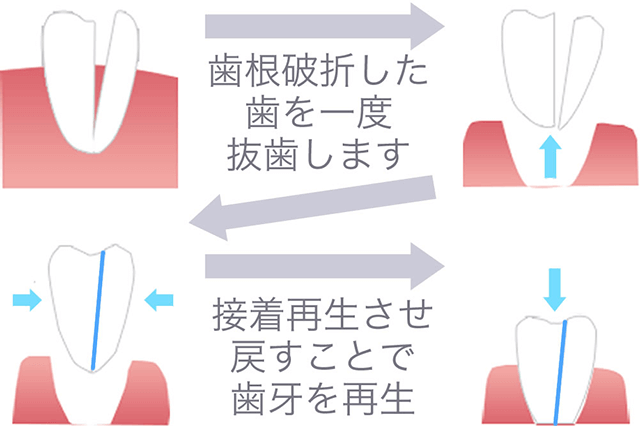
�A�q�r���������̐[���ʒu�ɓ������ꍇ�́A��x�����ăq�r��⋭�܂Ŗ��߂āA�܂����ɖ߂����Ái�ĐA�p�j�����܂��B�����A�ĐA���Ă��������Z���Ȃ邱�Ƃ������ł��B�i�ĐA�ł��Ȃ���������܂��j
�����A�q�r���[���ꍇ�̑����͎c�O�Ȃ��甲���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������ł��B
�q�r���g�勾�i�}�C�N���X�R�[�v�j���g���Ď��Â���Ǝ���m����������܂��̂ŁA�ǂ����Ă����������Ȃ����ɂ͂������߂̎��Âł��B

�����R�F �����a�̏ꍇ
���Ԃ������ɂ����A�����a�������̂��Ƃ�����܂��B�����a�Ƃ����̂́A���̎���ɕt�������ۂɂ���Ď��s�����ǂ��N��������A�����n����a�C�ł��B
�����a�͏����̏ꍇ�́A����ł��ɂނ��Ƃ͂��܂肠��܂��A���̗n����ʂ�������x�̃��C�����Ă���ƁA�����ɒɂ݂��o�܂��B
�ł��̂ŁA�����a�������Ŋ���Œɂ݂��o��̂́A�����n����̂����Ȃ�i��ł��邱�ƂɂȂ�܂��B
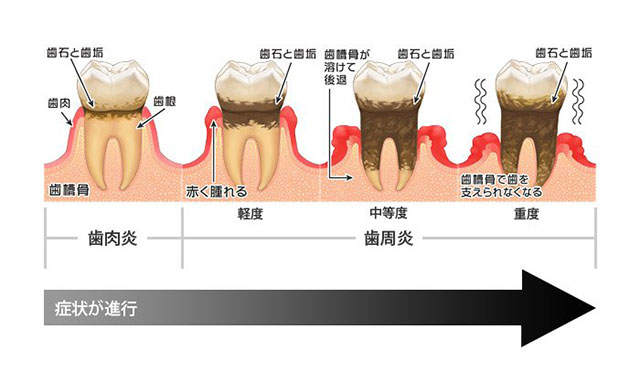
���Ö@
���Ö@�Ƃ��ẮA�ŏ��Ɋ��҂���Ɏ��ȉq���m���������w�����s���āA���҂����ɂȂ�A�����Ƃ�܂��i�X�P�[�����O�j�B
���̌�A���s�̒��̎����Ă��˂��Ɏ��܂��i���[�g�v���[�j���O�j�B
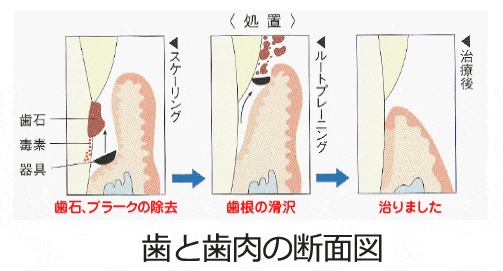
��������ƒ����炢�܂ł̎����a�Ȃ玡���Ă��܂����A����Ȃ��ꍇ�͎��s�̎�p�i�t���b�v��p�j���s���Ď����Ă����܂��B
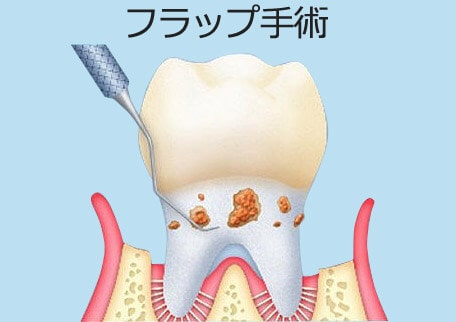
�ˌ�����4�l�����܂�

�� �傫�Ȓ���

�� �傫�Ȓ����ɋl�ߕ��������Ƃ���
���Ö@
�@ ��x�l�߂��l�ߕ���P�����āA���������S�Ɏ�菜���ꂽ�̂����`�F�b�N���܂��B�����A�������c���Ă�������S�Ɏ�菜������ŁA�Ăыl�ߕ������܂��B
�A ��x�l�߂��l�ߕ���P�����āA���������S�Ɏ�菜���ꂽ�̂����`�F�b�N���܂��B�����A�������c���Ă��Ȃ��̂ɒɂ�ł�ꍇ�́A�_�o��ی삷����h������ŁA�Ăыl�ߕ������܂��B
�B �@��A�̎��Â��s�����̂ɒɂ݂����Ȃ��ꍇ��A�ɂݎ��̂����Ȃ苭���ꍇ�́A�d���Ȃ����̐_�o�����܂��B�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����܂�܂��B�����A���̐_�o�͂Ȃ�ׂ����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͋ɗ͎c���悤�ɂ��Ă��܂��B
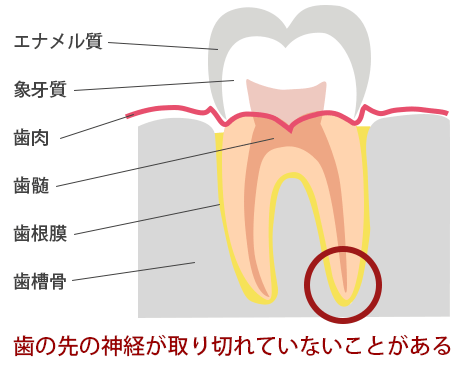
���Ö@
���̏ꍇ�́A��x���Ԃ������Ԃ�����P�����A���c���ꂽ�_�o�����S�Ɏ�菜�����Â��s���܂��B
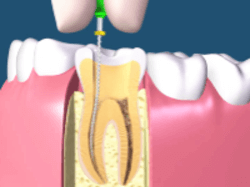
���̏Ǐ�́A�������₩�Ԃ����ɋN���邱�Ƃ������ł��B�������₩�Ԃ����͐_�o���������ɂ��鏈�u�ł����A�_�o�̖������́A�Ɖu�͂������̂ł��ۂɊ������₷���̂ł��B
�������N����ƁA���̍������̐���ۂɔ^�����܂�A����A�@�����肵�����ɒɂނ̂ł��B
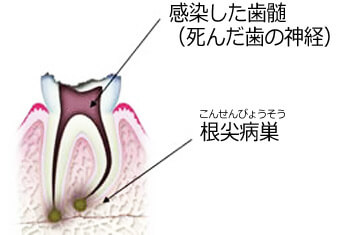

���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B
���R�́A
�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA
�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA
�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B
���Ö@
���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B
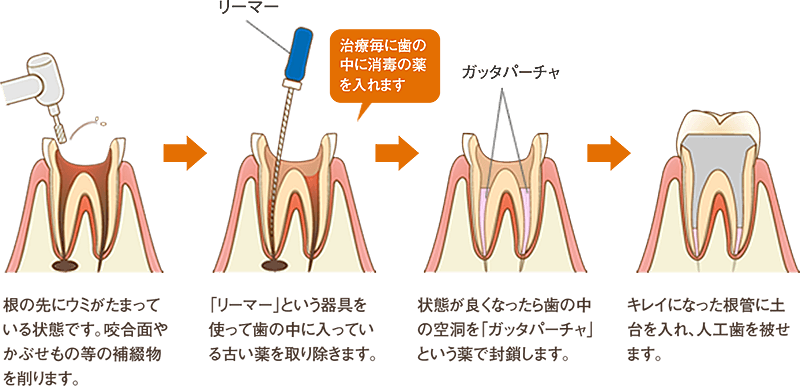
�́A���̐_�o����������ɔ^�����܂邱�Ƃ��悭����܂��B���̔^����鎡�Ái������_�o���Áj�̎��ɁA�^�����ꂸ�ɂނ��Ƃ�����܂��B
�^�݂�����Ȃ��ƁA�^�����̒��ɂ������Ă��܂��A���ɂ��N�������Ƃ�����܂��B
�^�����e�N�j�b�N�͎��Ȉ�@�ɂ���č�������A�c�O�Ȃ���A���ꂪ�s����Ȉ�@������܂��B

�� ���̏��ɔ^�����܂��Ă܂��B
�Ώ��@
�^���o���邱�Ƃ��厖�ł��B
���ʉ@���̎��Ȉ�@�ŁA�ɂ݂�������ēK�ȏ��u�����Ă��炢�܂��傤�B
�����A���̈�@���������̎��Â����ӂłȂ���A���ӂȈ�@�ɍs�����Ƃ��I�����Ƃ��Ă���܂��B
���Ö@
���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B
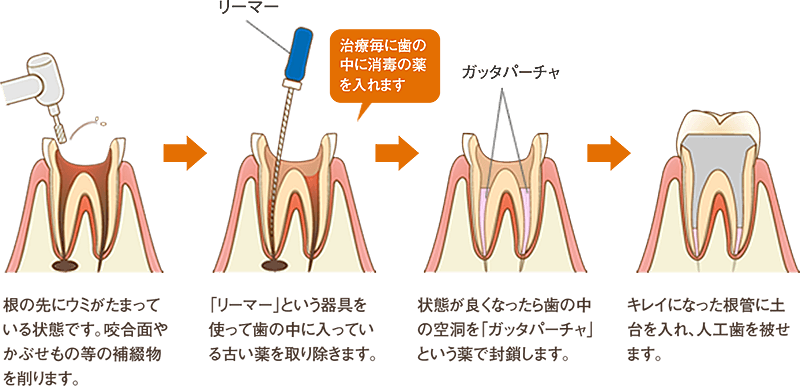
���ɂŔM���o�邱�Ƃ͂���܂��B
���������M���o��Ƃ����̂́A�g�̂ɓ����Ă������ۂ�E�B���X��������邽�߂ɔM���ł�킯�ł��B
�Ȃ̂ŁA���ɂɂ�鉊�Ǔ��Ŕ��M�������Ƃ͂������܂��B

�����āA���ɂŔM���o��ꍇ�Ƃ����̂��Ǐd���ꍇ�ł��̂ŁA�Ǐ�J�ɐf�f���Č������m�肵�A�����Ɏ��Â��邱�Ƃ��厖�ɂȂ�܂��B
�����A���ɂ������ŔM���o�锽�ʁA�M���o�����玕���ɂނ��Ƃ�����܂��̂ŁA�����̐f�f���d�v�ɂȂ�܂��B
���Ɏ��ɂŔM���o�錴������̓I�ɂ��������܂��B
�ˌ�����4�l�����܂�
����1�F�������傫���ꍇ
���ׂȂǂŔM�����鎞�ɁA�傫�Ȓ������������ꍇ�A�M�ɂ���Ď��̐_�o�̌������ǂ��Ȃ��Đ_�o�ɒʂ��Ă錌�ǂ̓������オ��܂��B
�������オ��Ǝ��̐_�o���������Ď����ɂނ��Ƃ�����܂��B�܂�A���ׂ̔M�������Œ����̎����ɂނƂ������Ƃ��N����܂��B

�� �傫�Ȓ���
���Ö@
���ɖ��������Ă���A���������S�Ɏ�菜���A�����ɋl�ߕ������܂��B �l�ߕ��͑傫���Q��ނ���܂��B
�@���^������Ă���Z�H�m���l�ߕ��i�C�����[�j������Ă��������ꍇ

�A������������炷���ɂ��̏�Ŏ������l�߂�ꍇ
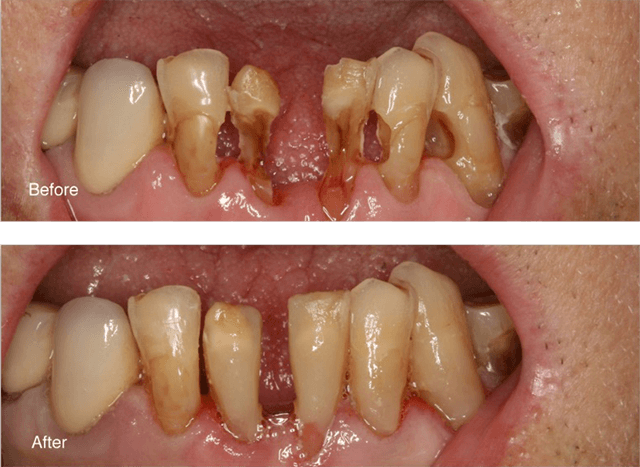
�l�ߕ��̎�ގ��̂͂�������܂��̂ŁA���Ȉ�@�ł��������������ˁB
�����Q�F ���̐_�o������ŕ������ꍇ
�������傫���Ȃ��Ď��̐_�o�܂ōs���Ă��܂��ƁA�_�o������ł��܂����Ƃ�����܂��B
�����āA���_�o�͕����Ă��܂��A�^��ł��܂��B
�����Ȃ�ƁA�������̐悪���Ă��ĉ��ǂ��N�����܂��B
���̉��ǂ������ꍇ�͔��M���邱�Ƃ�����܂��B
���̕������_�o�͍���a���Ƃ����^�̑܂�����Ă��܂��܂��B
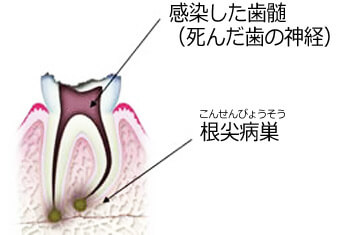

���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B
���R�́A
�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA
�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA
�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B
���Ö@
���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B
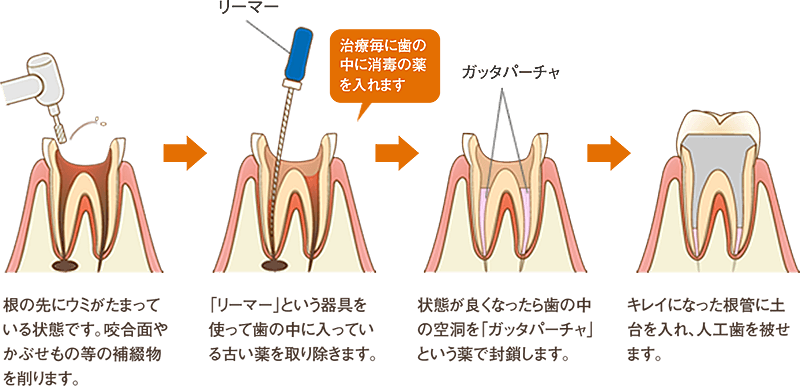
�����R�F �����a��e�m�炸�̉���
�����a�ɂȂ������́A�g�̖̂Ɖu�זE�Ǝ����a�̂��ۂ�����Ă��ł����A�����a���d�ǂɂȂ��Ă��܂��ƁA���̐킢���������𑝂��A�M���o�邱�Ƃ�����܂��B

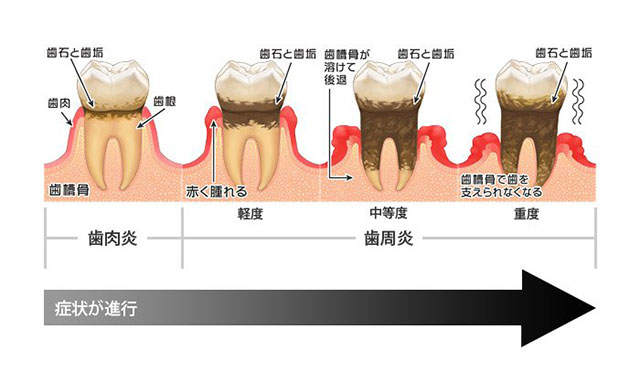
���Ö@
���Ö@�Ƃ��ẮA�ŏ��Ɋ��҂���Ɏ��ȉq���m���������w�����s���āA���҂����ɂȂ�A�����Ƃ�܂��i�X�P�[�����O�j�B
���̌�A���s�̒��̎����Ă��˂��Ɏ��܂��i���[�g�v���[�j���O�j�B
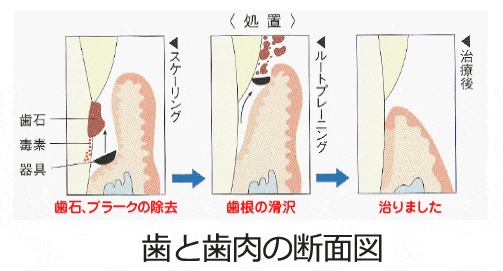
��������ƒ����炢�܂ł̎����a�Ȃ玡���Ă��܂����A����Ȃ��ꍇ�͎��s�̎�p�i�t���b�v��p�j���s���Ď����Ă����܂��B
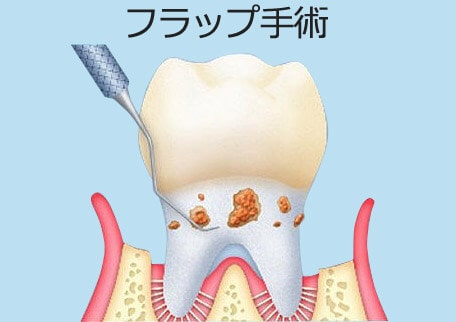
�܂��A�e�m�炸�̉��ǂ��������������悤�Ȏ����N����܂��B


���Ö@
���Ö@�Ƃ��ẮA�܂��͍R������������ł��炢�A���ۂ̐������炵�A���Ȃǂ̉��ǂ����܂�̂�҂��܂��B
���̒i�K�ŁA��U���ǂ����܂邱�Ƃ������ł��B
�����āA��U���܂������ǂ��Ĕ����Ȃ��ꍇ������܂��B
�Ĕ����Ȃ���Ύ��Â͂���ŏI���ɂȂ�܂��B

�����A�Ĕ����J��Ԃ��ꍇ��A�Ĕ��̕p�x�����Ȃ��Ă����ǂ̒��x�������ꍇ��A�e�m�炸����O�̎��������Ă��܂��Ď����тɂ��e�����o��ꍇ�Ȃǂɂ́A�e�m�炸�����ق����ǂ��ꍇ������܂��B
�����S�F ��{����
��̉����̂�����ɂ́A��{���i���傤�����ǂ��j�ƌ����āA���W���̒��Ɍ����J������Ԃ�����܂��B
�������Ђǂ����Ƃɂ���āA���̐_�o������ŕ����ĉ��ǂ��N�����Ă��܂��ƁA���̉��ǂ���{���܂Ŋg���邱�Ƃ�����܂��B
�����Ȃ�ƁA�M���o�邱�Ƃ������ł��B
���̑��ɁA�@���l�܂�����A���ɂ����鎞������܂��B
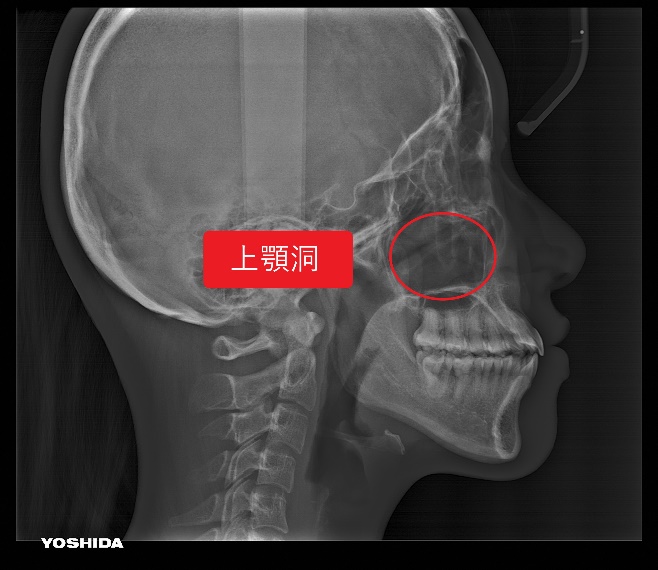
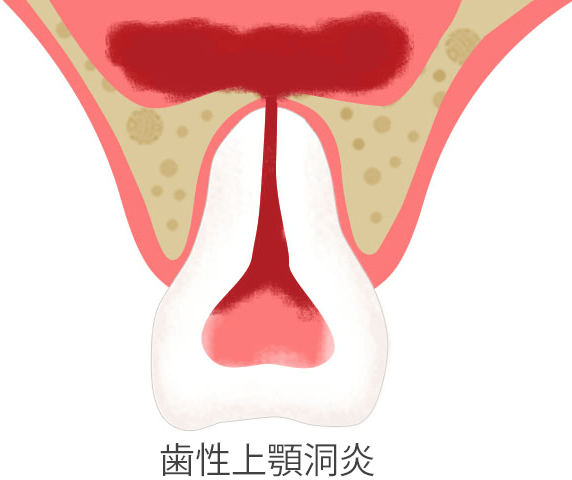
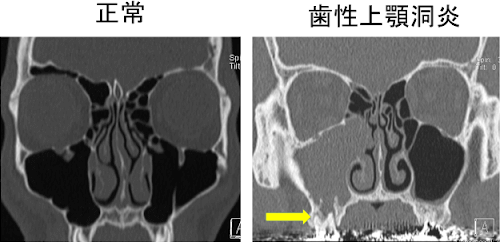
���Ö@
��{�����ɂ͎�ނ������āA���������ŋN������̂�������{�����ƌ����܂��B��{�����̒��ł���r�I�������ǂł��B���̏ꍇ�́A�u�����v�Ƃ������炢�ł����玕�Ɍ���������܂��B
�Ȃ̂ŁA���̎��Â�����킯�ł��B�����͎��̐_�o������ŕ����Ă��܂��A���̉��ǂ���{���܂Ŕg�y���Ă�킯�ł�����A���̎��Â����܂��B
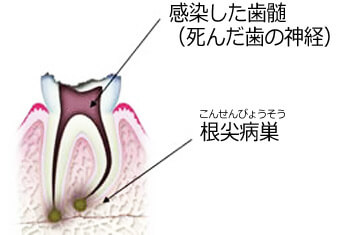

���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B
���R�́A
�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA
�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA
�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B
���Ö@
���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B
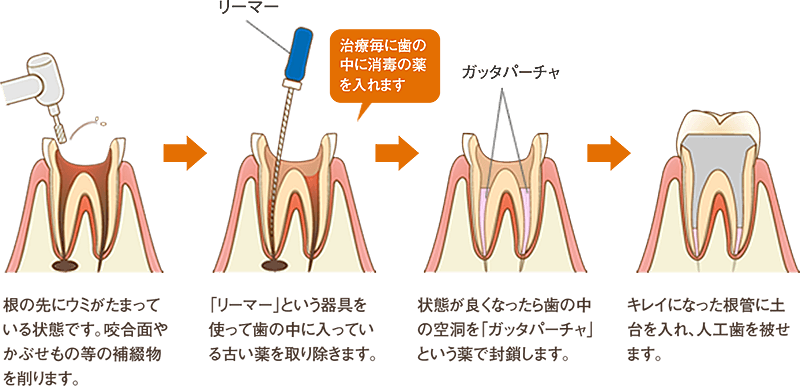
�����u���ɂ����ɒɂ��v�Ƃ��Ȃ�炢�ł���ˁI
�܂��A����Ȏ��̓��L�\�j���Ƃ��ɂݎ~�߂������Ȃ��ł��B
�����ƑΏ��@���킩��₷�����������܂��ˁB
�����̌��ɂ̌����͑傫��2����܂�
�����P�F
���̍������̐�ɔ^�����܂�A�^�����̒��ɂ������Ă��܂����ꍇ
�����Q�F
�������傫������ꍇ
����1�F���̍������̐�ɔ^�����܂�A�^�����̒��ɂ������Ă��܂����ꍇ
�����̌��ɂōł������p�^�[���ł��B
�_�o����������A�_�o�����R�Ɏ���ł��܂������͖Ɖu�͂��Ȃ����߁A���ۂ��������邱�Ƃ������A���ʔ^�����܂�̂ł����A���̔^�͎��R�ɔr�o����邱�Ƃ������̂ł����A�r�o���ꂸ�ɍ��̒��ɂ��������ꍇ�͑����������ɂ݂��o�܂��B
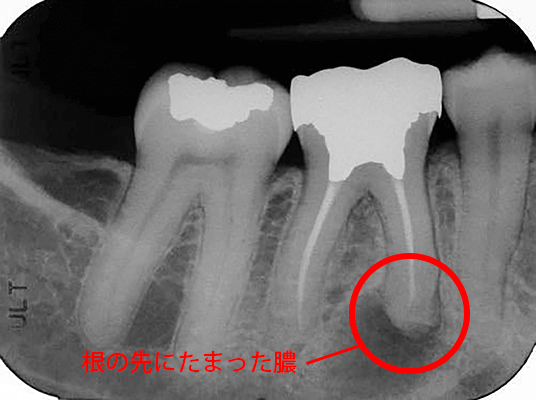
���Ö@
���̍������̐�ɗ��܂����^���o������A�������̓�����|�����ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B
���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B
���R�́A
�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA
�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA
�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

�����̕����ɔ^�����܂��Ă܂��B
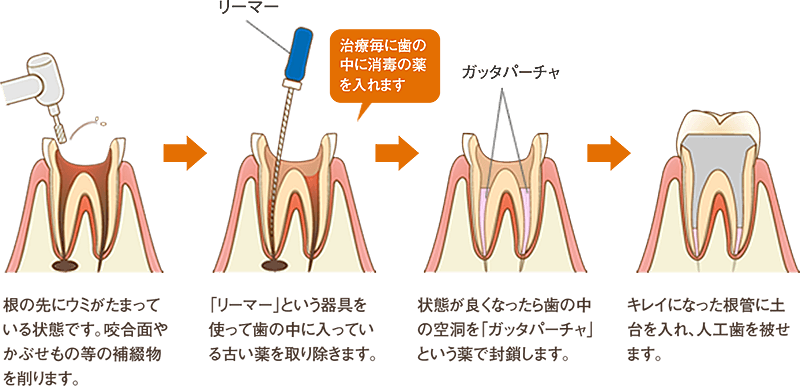
�i���Ӂj�����a�̎������l�̏ǏN���邱�Ƃ�����܂��B�܂��A���Ƀq�r���������芄��Ă�ꍇ�ɂ��N����܂��̂ŁA���Ȉ�@�Ō�����f�f���Ă�����ĉ������ˁB
����2�F�������傫������ꍇ
�������_�o�܂Ői��ł��܂��ƁA���������������l�Ȍ��ɂ��N����܂��B
�������܂Œ������i�s���Ă��܂��ƁA���̐_�o����炴��܂���B
�_�o������Ă��܂��A���̎�̒ɂ݂͒����Ɉ����܂��B
�_�o����邱�Ƃ��i�����j�ƌ����܂��B

���Ö@
�ʏ�A�����̒ɂ݂ɂ͒i�K������܂����A���������̐_�o�܂ōs���Ă��܂��ƁA���Ȃ�ɂ݂܂��B
���̏ꍇ�́A���̐_�o����菜�����Â����Ȃ��Ƃ����܂���B�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����Ɏ��܂�܂��B
�ˁi���Ӂj�������A���̐_�o�͂Ȃ�ׂ����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͂Ȃ�ׂ��_�o���c���悤�w�͂����Ă��܂��B
��̓I�Ȏ��Ö@
�@�܂��A�ɂ�ł鎕�ɖ��������܂��B
���@�ł͖����͒ɂ��Ȃ��ł��܂��B�ɂ��Ȃ����R�͂������B
�A���������������������A����������Ď��A���̌㎕�̐_�o��j�̂悤�Ȋ����g���Ď��܂��B
������������������Ă�̂Œɂ݂͑S������܂���B
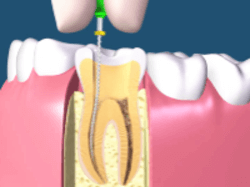
�B�_�o�����I�������A���̓����ɏ��ł̖�����āA�ӂ������ĂP��ڂ̎��Â͏I���ł��B
�C���̐_�o���������ɁA��U���ǂ��N���܂����A���ꂪ�P�`�Q�T�ԂŎ��܂�����_�o�̑���ɂȂ����l�߂܂��B

�������ʂ��Ă�̂��A�_�o�̑���ɂȂ��ł��B
���@�̖������ɂ��Ȃ����R
1�F�����̒��˂̐j���h�������ɂ݂��Ȃ���
���ƌ����Ă��A�j���h�����̒ɂ݂�h�����Ƃ��厖�ł��B
�����ɍׂ̐j���g���Ă���
�ːj�����ׂ��̂ŁA�����̒��Ɏh�������ɂ��킩��ɂ����B
���ɂ݂�������זE(�ɓ_)�̏��Ȃ��ӏ��ɍŏ��ɑł�
�˒ɓ_�����Ȃ��̂Œɂ݂ɂ����ł��B
���j���h���u�Ԃ́A�������̔S���ۂ̊v�̂悤�ɁA�s���ƒ����Đj����C�Ɏ������ɓ���悤�ɂ���B
�˂��̂悤�ɂ���Ɛj���h�������Ƃ��킩�炸�A���҂���ɂ́A�u�ŋ߂̖����͒��˂���Ȃ���ł����H�v�ƕ�����邱�Ƃ������ł��B

�Q�F������𒍓�����Ƃ����ɂ݂��Ȃ���

������͉t�̂Ȃ̂ʼn��x���Ⴂ�̂ł����A�������鎞�ɉ��x���Ⴂ�ƁA�̂��₽�������Ă��܂��Ɠ����ɒɂ������Ă��܂������ƂȂ�܂��B
���@�ł͂��炩�����������̉����炢�ɉ��߂Ē������܂��̂��A���җl�͋C�t����܂���̂ŁA�ɂ݂������܂���B
����ƁA�����ւ������̃X�s�[�h�����Ȃ������肵�Ă��܂��B�}���Œ�������ƁA���������Ă��܂��ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
���@�ł́A�P�H���P�b���炢�̂������Ƃ����X�s�[�h�ōs�����ŁA�����̑��ݎ��̂ɋC�t����܂���B
�P�C�Q�̏ꍇ�Ƃ��A�[�閰��Ȃ����炢�ɂ��킯�ł��̂ŁA������łł���Ώ��@�����������܂��B
������ŏo����Ώ��@
�i����������}���u�ł��̂ŁA�����ɂ͎��Ȉ�@�ɍs���Ă��������ˁj
���s�̂������́A�莝���̒ɂݎ~�߂�����
�[��ł��J���Ă�h���b�O�X�g�A������A�����Œɂݎ~�߂��邩���m��܂���B
�����A��t�����̎��ɂ��Ȃ��ꍇ�͔����Ȃ��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B
�܂��A�̖�ǂŔ�������A����҂���Ȃł���������ɖ����������ނƗǂ��ł��傤�B
�L���ȃ{���^�����A���L�\�j���͂������A�C�u�A�o�t�@�����Ȃǂ��L���ł��B
�܂��A���I�ۂ𒎎��̌��ɋl�߂���@���^�ۂ͂���܂����A�����͒��Ɍ��ʂ͂���܂��B
���ɂ��ӏ����₷
��₷�����߂邩�͖����Ƃ����Ǝv���܂����A�����͂����ł��B
���ǂ��i�s���̎��͗�₵�A���̎��͉��߂�A�Ƃ������Ƃł��B
����Ȃ����炢�����ɂ��킯�ł�����A�������₷�̂��ǂ��ł��B
��₵���́A�^�I���ɂ���ۗ�܂�A���ꂪ������ΕX���ŗ�₵���^�I���Ȃǂłق��������炠�Ăė�₵�܂��B
��₷�ƁA����������A�ɂ݂������ł����y������\��������܂��B
����ԋ~�}�Z���^�[��A���Ȉ�t��̖�ԋ~�}�O���𗘗p����
�����A�n��⎞�ԑтɂ���Đf�Â��ĂȂ���������܂��̂Ŋm�F���K�v�ł��B
�����ɂɌ����c�{������
�� �ڂ����͂��������̒ɂ݂Ɍ����c�{
���̒ɂ݂Ɍ����c�{�͂���������܂��B
�P.���J(��������)
�L���ȃc�{�Ŏ��̒ɂ݂����ł͂Ȃ��A���ɁA������A�ԕ��ǂȂǐF�X�Ȍ��ʂ�����ƌ����Ă��܂��B
��̍b���ŁA�e�w�Ɛl�����w�̌������邱�Ƃ납��Q�������炢�w��̕��ɂ���܂��B
��������⋭�߂ɉ����Ă����܂��B����ŁA���ꂼ��R�O�炢�����Ɨǂ��ł��B
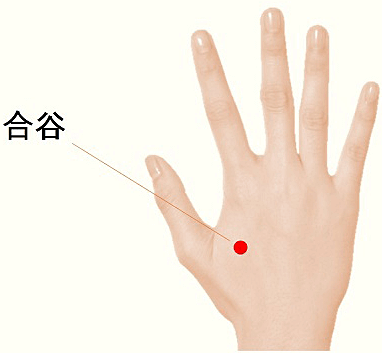
�Q.���ɓ_
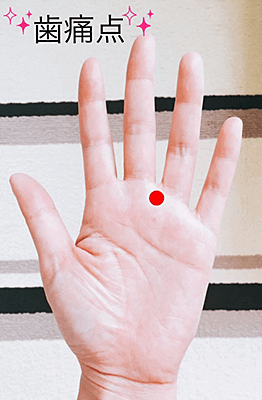
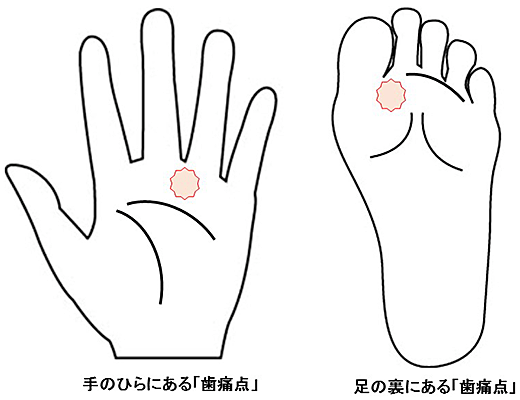
��̂Ђ瑤�Ƒ��̗��ɂ���܂��B��̂Ђ�ɂ́A���w�Ɩ�w�̕t�����̊Ԃɂ���܂��B ���̗��ɂ́A�e�w�Ɛl�����w�̕t�����̊Ԃ�1.5cm���炢���ɂ���܂��B
�������́A��⋭�߂ŁA�������߂ɉ����܂��B�����āA���E���݂ɉ����܂��傤�B�����⎕���^�R�Ɍ����ƌ����Ă��܂��B
�R.����(������)
���̌�����A�e�w�̕��łR�{���قǎ�O�ɂ���c�{�ł��B�w�̕��������ɂ��ĂāA�����Ă͗������J��Ԃ��܂��B

�S.�j��(���傤����)
���A�S�̃G���̊p����P�������炢��O�ɂ���c�{�ł��B�v���芚�ݒ��߂����ɁA�ӂ���މӏ��ł��B
�������w�̕��ʼn�������A������������J��Ԃ��܂��B

�T.���z�i���傤�悤�j
�l�����w�̒܂̕t�����̐e�w�̑��ɂ���܂��B
�K�x�ɉ������藣��������J��Ԃ��Ɨǂ��ł��B�܂��́A�l�����w�̒܂̎�̐e�w�Ɛl�����w�ł͂���ŝ��ނ��Ƃ����ʂ����҂ł��܂��B
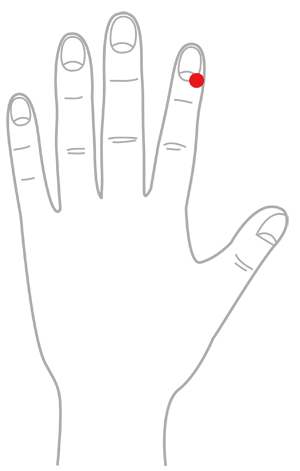
�U.����i�Ȃ��Ă��j

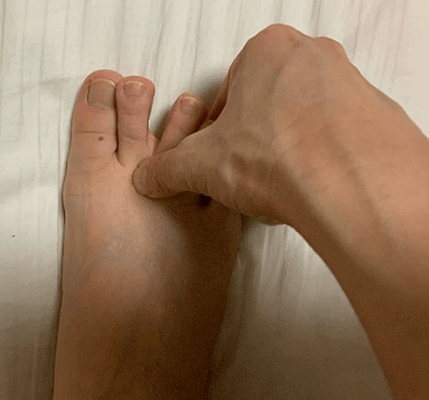
���̍b�̑��̐l�����w�ƒ��w�̕t�����̊Ԃɂ���܂��B
�������A��̐e�w�Ɛl�����w�ł܂�ʼn����Ă����ƌ��ʓI�ł��B
�V.�����i���傤���傤�j
�������̐�Ɖ������т�̊Ԃ̂��ڂ��ɂ���܂��B
���\���߂ɂR����x�w�̕��ʼn����܂��B
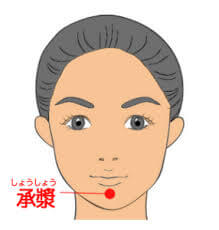
����
�����̃c�{�ً͋}���≞�}���u�ɍs�����̂ł��B
���ꂾ���Ŏ���킯�ł͂���܂���̂ŁA���m��w�ŁA��������ƌ������m�肵�Ă���A�K�����Ȉ�@�Ŏ��Â��Ă��������ˁB
��������́A�������Ɏ������荇�킹�邱�Ƃł��B
�H������́A�������łȂ��Ă��A���������Ɗ��ݒ��߂���A���ӎ��ɐH�������Ă邱�Ƃł��B
�������肪�����Ŏ����ɂނ��Ƃ�����܂��B���R�͂���������܂��B
����1�F ���̂܂��̎������̉���
�������肪�Ђǂ��ƁA���̂܂��������������ǂ��N��������A�_���[�W���N�����܂��B
�����āA���ނƒɂ݂��ł܂��B
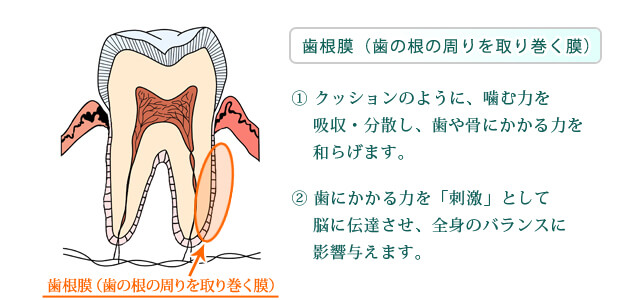
����2�F ���ɂЂт�����A�����
�������肪�Ђǂ��ƁA���ɂЂт���������A���ꂽ�肷�邱�ƂŒɂ݂܂��B
���ɁA�_�o���������ɋN����₷���ł��B�����āA���ނƒɂ��ł��B
����3�F �{�ߏǂɂ��ɂ�
�������肪�Ђǂ��ƁA�{�ߏǂɂȂ��āA�A�S���ɂނ��Ƃ�����܂��B
���Ö@
��������E�H��������������Ö@�ɂȂ�܂��B
1. ���ݍ��킹������
���̂��ݍ��킹���ǂ��Ȃ��āA�㉺�̎������������鏊���������ꍇ�A���������茸�����犚�ݍ��킹���ǂ��Ȃ�̂ŁA���茸�炻���Ƃ��āA�m�炸�m�炸�Ɏ�����������Ă��܂��܂��B
�˂Ȃ̂ŁA���Ö@�Ƃ��ẮA���ݍ��킹�̐f�f�����āA�����I�ɋ���������Ƃ�����ق�̏������Ȃǂ��Ď����܂��B
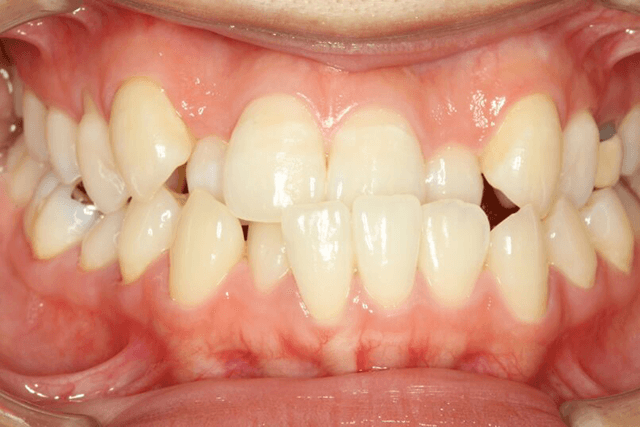
2. �}�E�X�s�[�X�Ŏ���
�i�ی��������܂��j
�}�E�X�s�[�X��t���邱�Ƃɂ���āA���ݍ��킹�̂ł��ڂ��̃A���o�����X���Ȃ����A�����S�̂̊��ݍ��킹���ϓ��ɂȂ�A�X���[�Y�Ɋ��ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B�����Ȃ�ƁA�P�{�P�{�̎��ւ̕��S������A�܂��A�S�̊߂ɂ����镉�S������܂��B
��Q�鎞�͕K���t���܂��B�������p�\�R���Ƃ��C�������d���̎����t����Ɨǂ��ł��B
���X�ɁA��������A�H�����肪���܂��Ă��܂��B

3. �X�g���X
�X�g���X������ƁA�͔̂������Ă��܂��Ď���������N�����₷���Ȃ�܂��B�i�����A�X�g���X���U�ׂ̈Ɏ�������͂�����x�K�v�ł�����܂��B�ł����A�Ђǂ���������͍���܂��j
�˃X�g���X�����߂Ȃ������ɕς��邱�Ƃ��K�v�ł��B

4. �����ɋN���鎕�������
�����Ɏ�����������Ă�ƋC�t������A�Ƃɂ������̗͂��ĉ������B
�㉺�̎������킳���ɗ����ĉ������B�H�ׂ���A���肷��Ƃ��ȊO�͋ɗ͎������܂Ȃ��悤�ɋC��t���ĉ������B
�����āA�A�S�̗͂������āA�����y�ɂ��ăX�g���b�`���ĉ������B
�ӎ��I�ɂ���𑱂��邱�Ƃ����ʂ�����܂��B
5. ��Q�Ă鎞�̐H�������
��Q��O�́A�[���Ȃ��Ƃ͍l�����ɁA�y�������Ƃ��l���ă����b�N�X���Ă��������B
���̗ǂ��������Ƃ邱�Ƃ��H������\�h�ɂȂ�܂��B
���̒ɂ݂̌�������������ɂ���̂ɁA�����������̎��Â������炵�Ă��������܂���B
�{���̌����������Ď����Ȃ��Ƃ����܂���B
�����g�ł̓X�g���X�̗\�h�ɂ��w�߂Ē�������ŁA���Ȉ�@�����Ў�f���Č����Ƒ�������炩�ɂ��āA���Â��ĉ������ˁB

�M�����̂�H�ׂ����ɒɂ��ꍇ�̌����ɂ��āA
�����P�F ���������Ȃ�i�s���Ď��̐_�o�����ǂ��N�������ꍇ�i�������j
���������������́A�₽�����̂ŏ������݂���x�ł����A���������Ȃ�i�s����Ɛ_�o���傫�ȉ��ǂ��N�����A�M�����̂ł��݂���ɂ肵�܂��B
�M�����̂Œɂ��ꍇ�͉��ǂ������̂ŁA���̏ꍇ�͎c�O�Ȃ���A�_�o�����Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ƃ������ł��B
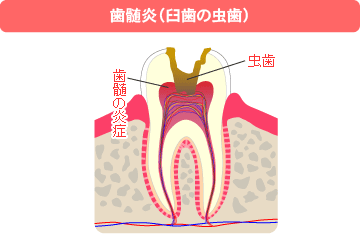
���Ö@
�ʏ�A�����̒ɂ݂ɂ͒i�K������܂����A���������̐_�o�܂ōs���Ă��܂��ƁA���Ȃ�ɂ݂܂��B
���̏ꍇ�́A���̐_�o����菜�����Â����Ȃ��Ƃ����܂���B�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����Ɏ��܂�܂��B
�ˁi���Ӂj�������A���̐_�o�͂Ȃ�ׂ����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͂Ȃ�ׂ��_�o���c���悤�w�͂����Ă��܂��B
��̓I�Ȏ��Ö@
�@�܂��A�ɂ�ł鎕�ɖ��������܂��B
���@�ł͖����͒ɂ��Ȃ��ł��܂��B�ɂ��Ȃ����R�͂������B
�A���������������������A����������Ď��A���̌㎕�̐_�o��j�̂悤�Ȋ����g���Ď��܂��B
������������������Ă�̂Œɂ݂͑S������܂���B
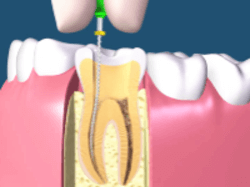
�B�_�o�����I�������A���̓����ɏ��ł̖�����āA�ӂ������ĂP��ڂ̎��Â͏I���ł��B
�C���̐_�o���������ɁA��U���ǂ��N���܂����A���ꂪ�P�`�Q�T�ԂŎ��܂�����_�o�̑���ɂȂ����l�߂܂��B

�������ʂ��Ă�̂��A�_�o�̑���ɂȂ��ł��B
���@�̖������ɂ��Ȃ����R
1�F�����̒��˂̐j���h�������ɂ݂��Ȃ���
���ƌ����Ă��A�j���h�����̒ɂ݂�h�����Ƃ��厖�ł��B
�����ɍׂ̐j���g���Ă���
�ːj�����ׂ��̂ŁA�����̒��Ɏh�������ɂ��킩��ɂ����B
���ɂ݂�������זE(�ɓ_)�̏��Ȃ��ӏ��ɍŏ��ɑł�
�˒ɓ_�����Ȃ��̂Œɂ݂ɂ����ł��B
���j���h���u�Ԃ́A�������̔S���ۂ̊v�̂悤�ɁA�s���ƒ����Đj����C�Ɏ������ɓ���悤�ɂ���B
�˂��̂悤�ɂ���Ɛj���h�������Ƃ��킩�炸�A���҂���ɂ́A�u�ŋ߂̖����͒��˂���Ȃ���ł����H�v�ƕ�����邱�Ƃ������ł��B

�Q�F������𒍓�����Ƃ����ɂ݂��Ȃ���

������͉t�̂Ȃ̂ʼn��x���Ⴂ�̂ł����A�������鎞�ɉ��x���Ⴂ�ƁA�̂��₽�������Ă��܂��Ɠ����ɒɂ������Ă��܂������ƂȂ�܂��B
���@�ł͂��炩�����������̉����炢�ɉ��߂Ē������܂��̂��A���җl�͋C�t����܂���̂ŁA�ɂ݂������܂���B
����ƁA�����ւ������̃X�s�[�h�����Ȃ������肵�Ă��܂��B�}���Œ�������ƁA���������Ă��܂��ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
���@�ł́A�P�H���P�b���炢�̂������Ƃ����X�s�[�h�ōs�����ŁA�����̑��ݎ��̂ɋC�t����܂���B
�����Q�F �_�o����������̍������̐�ɔ^�����܂����ꍇ�i����a���j
���̏Ǐ�́A�������₩�Ԃ����ɋN���邱�Ƃ������ł��B�������₩�Ԃ����͐_�o���������ɂ��鏈�u�ł����A�_�o�̖������́A�Ɖu�͂������̂ł��ۂɊ������₷���̂ł��B
�������N����ƁA���̍������̐���ۂɔ^�����܂�A����A�@�����肵�����ɒɂނ̂ł��B
���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B
���R�́A
�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA
�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA
�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B
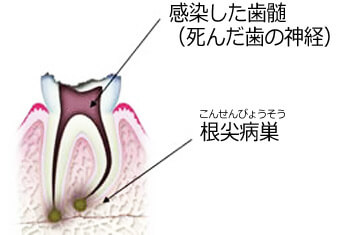

���Ö@
���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B
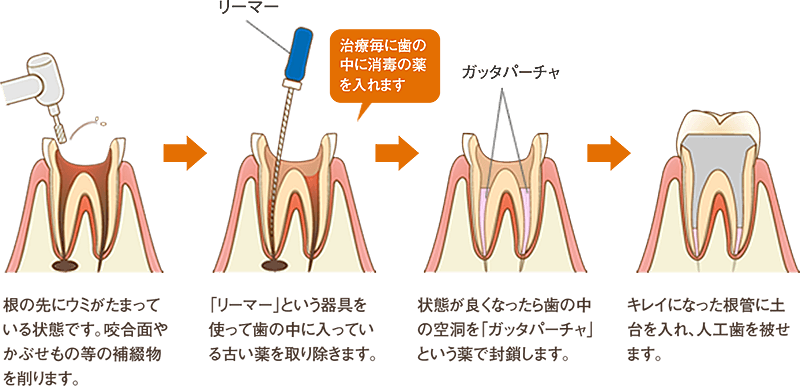
�����R�F �����̋l�ߕ��₩�Ԃ��������Ă���ꍇ
�⎕�Ȃǂ����Ă�ꍇ�́A�����͔M��ʂ��₷���̂ŁA�M�����̂̎h�����`���₷���ł��B
�_�o�������Ă��鎕�̋����̋l�ߕ��̏ꍇ�́A�������M�����x��ʂ��Ă��܂��A�_�o�܂ŔM���͂��₷���Ȃ�܂��B
�����A���Ò���ŔM�����̂��ɂ��ꍇ�͂P�T�Ԃ��炢�Ŏ��邱�Ƃ������ł��B

���Ö@
�@�����g�Q�����B�e���A�l�ߕ����������̓����ɒ���������Β����̎��Â����܂��B
�������傫���Ȃ���A�������������A�Ăыl�ߕ������܂�
�A�����A�������傫���Đ_�o�܂œ͂��Ă�ꍇ�́A�_�o������鎡�Â����Ȃ��Ƃ����܂���B�i�����A�Ȃ�ׂ��_�o�͎��Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͂Ȃ�ׂ��_�o���c���w�͂����Ă��܂��j
�M�����̂Œɂ��ꍇ�́A�ً}���������̂ő�������҂ɍs���������ǂ��I
�M�����̂��ɂ��ꍇ�́A���R�͂���������܂����A��������d�ǂ̎��������ł��B
�d�ǂ���u����ƁA����Ɉ������Č��ɂ��N������A�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�\���������̂ŁA�����ɂł�����҂ɍs���������ǂ��ł��B
�Â����̂�H�ׂ����Ɏ����ɂ��A���݂������邱�Ƃ͗ǂ�����܂��B
���p����Ö��Ɂi����݂��j�ƌ����܂��B
���̏Ǐ�́A����������؋��ɂȂ�܂��B�������L�̏Ǐ�ł��B
�`���R�A�A�C�X�A�O�~�A�K���Ȃǂ�H�ׂ����ɋN����₷���ł��B
�Â����̂Ŏ����ɂ��Ȃ闝�R
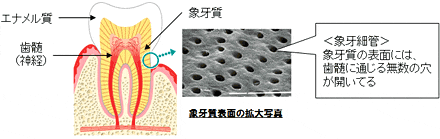
�����A������₱�����̂Ŗ����ɓǂ܂�Ȃ��Ă����v�ł��B
���̓����ɂ͏ۉ县�Ƃ�������������܂����A�����Ŏ��̕\�ʂ̃G�i���������n�����ۉ县���I�o���邱�Ƃ������ł��B
���̏ۉ县�ɂ́A�_�o�ɂȂ���ׂ���������������J���Ă��āA������ۉ�ǁi��������������j�ƌ����܂��B���̒��ɂ́A�t�̂������Ă��܂��B
�Â����̂�H�ׂ�ƁA���ꂪ�������̂悤�ɂȂ�܂����A���������ۉ�ǂɐG��Ă��܂��ƁA�Z�����̍����������̂ق��ɁA�ۉ�Ǔ��̉t�̂��z���グ���Ă��܂��܂��B
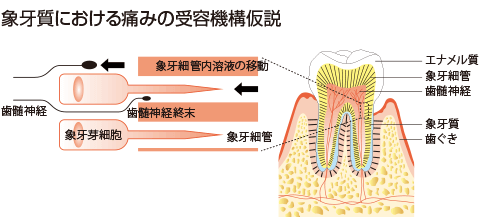
���̎��ɒɂ݂��o��̂ł��B
���Ö@
���̏ꍇ�́A�����̎��ÂɂȂ�܂��B����������ċl�ߕ�������̂����ʂł��B
�������傫�߂���Ɛ_�o�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ�܂����A�Ȃ�ׂ��_�o�͎��Ȃ������ǂ��̂ŁA���ǂ��̈�@�ł͂Ȃ�ׂ��Ȃ�_�o�͎��Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B
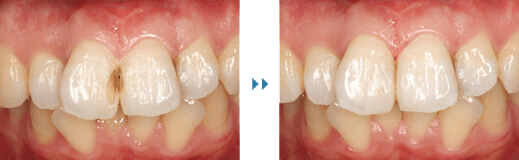
���O���̒����������ŋl�߂��ꍇ

�������̒������C�����[�Ƃ����l�ߕ��ŋl�߂��ꍇ
�����ɂ����������N�������Ƃ͂悭����܂��I
�܂��A��̂��т��A�A�S�⎨�܂Œɂ����Ƃ�����܂��I
���Ԃɂ��������܂��ˁB
���ɂœ��ɂ��N�����P�[�X
�����̂��镔�ʂ�����Ċ������Ƃ������߁A���ݍ��킹�����������Ȃ�܂��B���ݍ��킹�����������Ȃ�ƁA�A��̒ɂ݂⌨���肪�N���܂����A����Ɉ��������ē��ɂ��N����܂��B
���̂悤�ɁA��⌨�A�w���̋ؓ����ْ����邽�߂ɋN���铪�ɂ��ْ��^�����ƌ����܂��B���ɂ������œ��ɂ��N���錴���̃g�b�v�ł��B
�����A���ɁA������A��̒ɂ݂⒣�肪�����ɂ���ꍇ�ْ͋��^���ɂ��^���܂��B
�����a�ɂ���āA���ݍ��킹�̃o�����X�����ꂽ�Ƃ��ɂ����l�̂��Ƃ��N���蓾�܂��B
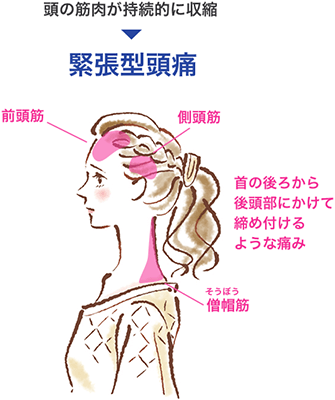
���Ö@
�]�_�o�O�Ȃɍs���Ɠ����Ɏ��Ȉ�@�Œ����⎕���a�̎��Â����Ă��������B
���@�ł́A�������̖��ɂ̒������Â����Ă��܂��B
�܂��A������ł̓}�b�T�[�W��X�g���b�`��A�̉����������肵�Č��s��ǂ����Ă��������B
�ْ��^���ɂ͉��߂邱�Ƃ��L���ł��B
�������ԕ��u�����ꍇ��A�����ɂ�鉊�ǂ��������āA�����ۂ��_�o�̐�̌��ǂ܂œ��荞��ł��܂��A�����ɂ��]�܂œ͂��A�]�̒��̐Ö��Ɍ���������Ă��܂����Ƃ�����܂��B
�������ł���Ɣ]���̌�������邭�Ȃ�A���ɂ��������܂��B�i�]�[�ǂ�]�o���̌����ɂ��Ȃ�܂��j
![�]��������](img/ha_itai/img_ha_itai_41.png)
���Ö@
�܂��́A�]�_�o�O�Ȃɍs�����Ƃ��厖�ł��B
�����āA���}���u�����Ă��������œK�Ȏ��Ȏ��Â������Ă��������B
�܂��A��ɒ�����f�Ŏ��̌��N����邱�Ƃ��厖�ł��B
�_�o����������́A�Ɖu�������Ȃ��̂Ŋ������N�������Ƃ��悭����܂��B
���̓����⍪�����̕������������ĉ��ǂ��g�����āA���ɂ��N�������Ƃ�����܂��B
���ǂ������ꍇ�́A���������ɂ��N���邱�Ƃ�����܂��B
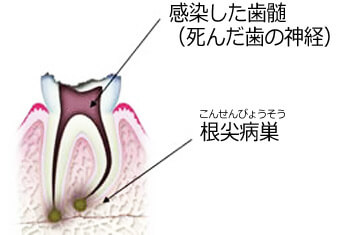

���Ö@
���������������̓����𐴑|���ăo�C�ۂ�ǂ��o���Ă��܂��A�����鍪�����̎��Â����܂��B
���@�́A�������̎��Âɗ͂𒍂��ł��܂��B
�ɂ݂̂����ŁA�����������Ċ��ނ悤�ɂȂ�A���ݍ��킹�������Ȃ�����A���������H�����肪�����Ŋ{�ߏ��ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
�{�ߏǂ̏Ǐ�Ƃ��ē������o�Ă��܂��B

���Ö@
�{�ߏǂ̌������m���ɐf�f���ĂȂ����Ɠ����ɁA�}�E�X�s�[�X�����ăA�S�̊߂ɂ����镉�S���Ȃ����Ă����܂��B

��{���ƌ����āA�@�̉��̓��W���̒��ɊJ���Ă������܂��B
�������傫���āA���̐_�o�ɉ��ǂ��N�����A���̉��ǂ��������̐悩���{���ɔg�y���ď�{�������N�������Ƃ�����܂��B�����Ȃ�ƁA��{�����ɂȂ�܂��B
���ɁA��{���ɋ߂������̎��Â��s�����ꍇ�������ł��B
��{�����̏Ǐ�Ƃ��āA���ɁA���d���Ȃǂ�����܂��I
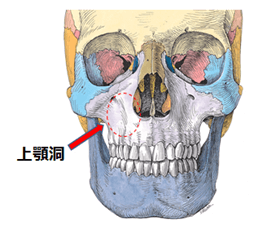
���Ö@
���Ȉ�@�ō������̎��Â����āA�������̐�[�ɂ���o�C�ۂ�ǂ��o���Ă����܂��B
�ǂ����Ă�����Ȃ��ꍇ�́A���̌����̎������邱�Ƃ�����܂��B
���@�ȓI�Ȏ��Â��K�v�ȏꍇ�͎��@�Ȃ��邢�́A���o�O�ȂŎ��Â��܂��B
��p���K�v�ɂȂ�ꍇ������܂��B
�Q�������ƌ��������ɂ݂��N���铪�ɂ�����܂����A���̃^�C�v�̓��ɂ��ځA�@�A���̐_�o�ɒɂ݂������N�������Ƃ�����܂��B
���ɂ��N�������ꍇ�́A�����g�ł͌������킩��ɂ����Ȃ�܂��B

���Ö@
���̒ɂ݂Ɠ��ɂ������Ɍ��ꂽ�ꍇ�͐F��ȃP�[�X���l�����܂��B�d�ĂȃP�[�X������܂��̂ŁA�]�O�ȁA���Ȉ�@�ŁA�K�ȏ��u�𑁂߂ɎĂ��������B
�����������āA�����������Ċ��ޕȂ����Ă��܂�����A�����������Ă��Ԃ�������ꂽ��ŁA���Ԃ����̍����Ɋ���Ȃ��ăA�S�ɕ��S���������{�ߏ��ɂȂ邱�Ƃ���r�I�悭����܂��B
�����������P�{�̎��̂��߂ɁA�{�߂���]�ɉe�����y�ڂ��A��̂��т��A�S�A���̒ɂ݂������N�����܂��B
�܂��A�����a�ɂ���Ď�����������A���ݍ��킹�������Ȃ������ɂ����l�̂��Ƃ��N����܂��B

���Ö@
�����������̒��ɂ��邱�Ƃ��悭����܂��̂ŁA���`�O�Ȃ⎨�@�Ȃ����łȂ��A���Ȉ�@�ł��K�Ȑf�f���āA���Â����܂��傤�B
���̒ɂ݂ɂ̓p�^�[��������܂��B�邾���ɂ��Ƃ��A���N�����������ɂ��Ƃ��A�H�ゾ���ɂ��Ƃ��F�X����܂��I
����Ȏ��͂ǂ������炢���̂��Y�݂܂���ˁB

�����ł͂��̌����ƑΏ��@�E���Ö@�����������܂��B
��Ɏ����ɂ��ꍇ
�ˌ�����3�l�����܂�
�����P�F ���̌������オ�邩��
��́A�g�̂����ɂ���̂ŁA���Ɍ����s���₷���Ȃ�A���̌������オ��܂��B
���̐_�o�ɉ��ǂ��������ꍇ�A�������オ���Č����������Ă��܂��ƁA�������オ���Đ_�o���������A�ɂ݂��o�܂��B
�����Q�F �������_�o���D�ʂɂȂ邩��
���Ԃْ͋���ۂ����_�o���D�ʂɂȂ�A���ǂ����k���Ă��܂����A��̓����b�N�X���邽�߂ɁA�������_�o���D�ʂɂȂ�܂��B
��������ƁA���̐_�o�ɍs�������������Ă��܂��A�_�o���������Ēɂ݂₷���̂ł��B
�����R�F ���ǂ��g�����Č����̗ʂ������邩��
�����C�ɓ���ƁA���R���ǂ��g�����Č����������܂��B
�܂������b�N�X����̂ŕ������_�o���D�ʂɂȂ��āA���ǂ��g�����A�_�o�ɗ���錌�̗ʂ������Đ_�o���������A�ɂ݂��o�₷���Ȃ�̂ł��B
�ł͎��ɁA��ɒɂދ�̓I�ȕa�C�����������܂��ˁB
�� �������i����������j
�������_�o�܂Ői��ł��܂��āA�_�o�ɉ��ǂ�������a�C�ł��B
��Ɍ����������Ȃ��Ă�������ɂ݂������܂��B�Y�L�Y�L�Ɣ����Ɂi�͂��ǂ����j���N����܂��B
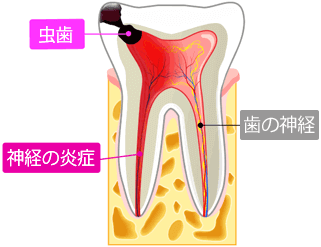
�������̑Ώ��@�E���Ö@
�������_�o�܂œ͂��Ă��܂��āA�_�o���������ǂ��N�����Ă܂��̂ŁA���̏ꍇ�͐_�o����炴��܂���B�_�o�������Βɂ݂͈����܂��B
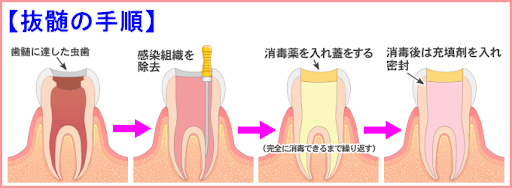
��ɒɂ�Ŗ���Ȃ����́A�������₷���ƂƁA�s�̂̒ɂݎ~�߂����ނ��Ƃł��B
�� ���됫�������i���������イ����j
���̍������̐�̕������ۂɊ������ĉ��ǂ��N�����A���ꂪ�A�������̎��ӂ̍��܂Ŕg�y���Ĕ^�����܂�����Ԃł��B
���̕a�C�̏ꍇ�A�^�����R�ɏo�Ă��܂����Ƃ�����A���̎��͒ɂ݂��o�Ȃ��̂ł����A�^���������Ă��܂����ꍇ�́A���Ȃ�̌��ɂɂȂ�܂��B
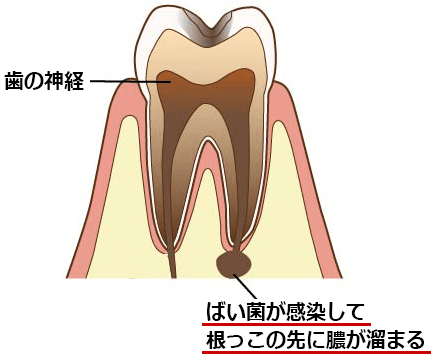
���됫�������̑Ώ��@�E���Ö@
���̍������̓������������Ă邽�߁A�������̒����L���C�ɂ��鎡�Ái���ǎ��Áj���s���܂��B
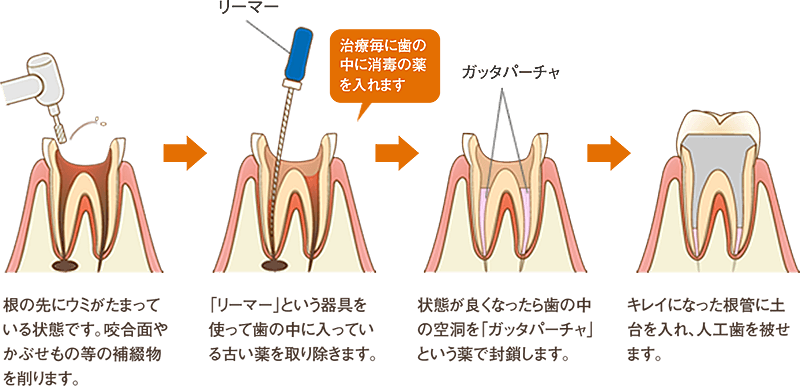
��ɒɂ�Ŗ���Ȃ����́A�������₷���ƂƁA�s�̂̒ɂݎ~�߂����ނ��Ƃł��B
�� ��Ԃ̎�������
��ԂɎ�����������邱�Ƃ͂��Ȃ葽���ł��B���̏ꍇ�A������������邱�Ƃɂ���āA���⎕�����⎕���x���Ă鍜�ɒɂ݂≊�ǂ��N�����Ă��܂��a�C�ł��B
�����ɂ͙������O���i�������������������傤�j�ƌ����܂��B
�������O���̑Ώ��@�E���Ö@
�}�E�X�s�[�X��t���邱�Ƃɂ���āA���ݍ��킹�̂ł��ڂ��̃A���o�����X���Ȃ����A�����S�̂̊��ݍ��킹���ϓ��ɂȂ�A�X���[�Y�Ɋ��ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B�����Ȃ�ƁA�P�{�P�{�̎��ւ̕��S������A�܂��A�S�̊߂ɂ����镉�S������܂��B
��Q�鎞�͕K���t���܂��B�������p�\�R���Ƃ��C�������d���̎����t����Ɨǂ��ł��B
���X�ɁA��������A�H�����肪���܂��Ă��܂��B

���N�����玕���ɂ��ꍇ
�ˍl�����錴����1�ł�
�����F �Q�Ă�Ԃ̎��������H������
���N�������ɓ��Ɏ����ɂ��Ƃ������������܂��B
����́A��ԐQ�Ă�ԂɎ��������H����������Ă���̏ꍇ�������ł��B
��������́A�傫�ȉ�������̂ł��Ƒ�����w�E����邱�Ƃ�����܂����A���X�����ł͋C�Â��ɂ����̂ŁA�������������肵�Ă�Ƃ͎v���ĂȂ����������ł��B
�H������͒P�ɏ㉺�̎����������ݒ��߂邾���Ȃ̂ŁA���͂��Ȃ��ł��B
���ʂɊ��ގ��́A���ɑ̏d���炢�̗͂�������܂����A��������A�H������́A����ɂ�����傫�ȗ͂�������A���⎕������A�S�ɑ傫�ȕ��S���y�ڂ��܂��B
���Ƀq�r�������Ă��܂�����A����Ă��܂����Ƃ�����܂��B
���̂����ŁA�N�������ɒɂ݂��o��̂ł��B
���͂������A�A�S�̒ɂ݂��o�邱�Ƃ�����܂��B
��������̑Ώ��@�E���Ö@
�}�E�X�s�[�X��t���邱�Ƃɂ���āA���ݍ��킹�̂ł��ڂ��̃A���o�����X���Ȃ����A�����S�̂̊��ݍ��킹���ϓ��ɂȂ�A�X���[�Y�Ɋ��ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B�����Ȃ�ƁA�P�{�P�{�̎��ւ̕��S������A�܂��A�S�̊߂ɂ����镉�S������܂��B
��Q�鎞�͕K���t���܂��B�������p�\�R���Ƃ��C�������d���̎����t����Ɨǂ��ł��B
���X�ɁA��������A�H�����肪���܂��Ă��܂��B

�H�㎕���ɂ��ꍇ
�ˍl�����錴����2�ł�
�����P�F �Â����̂�H�ׂ����ɒ������ɂ�
������������x�傫���ꍇ�A�H��ɒɂނ��Ƃ�����܂��B
���ɁA�����͊Â����̂Œɂށi�Ö��Ɂj�Ƃ�������������܂��B
�Ȃ��A�Â����̂Ŏ����ɂ������������܂��B
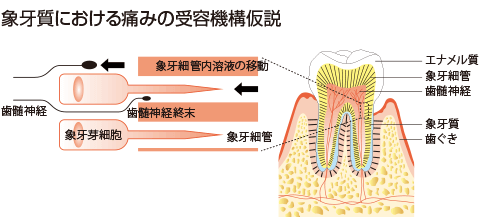
�����A������₱�����̂Ŗ����ɓǂ܂�Ȃ��Ă����v�ł��B
���̓����ɂ͏ۉ县�Ƃ�������������܂����A�����Ŏ��̕\�ʂ̃G�i���������n�����ۉ县���I�o�������Ƃ������ł��B
���̏ۉ县�ɂ́A�_�o�ɂȂ���ׂ���������������J���Ă��āA������ۉ�ǁi��������������j�ƌ����܂��B���̒��ɂ́A�t�̂������Ă��܂��B
�Â����̂�H�ׂ�ƁA���ꂪ�������̂悤�ɂȂ�܂����A���������ۉ�ǂɐG��Ă��܂��ƁA�Z�����̍����������̂ق��ɁA�ۉ�Ǔ��̉t�̂��z���グ���Ă��܂��܂��B
���̎��ɒɂ݂��o��̂ł��B
�����肩�玕���ɂ�A�����ɂ�ł��猨���肪�����肷�邱�Ƃ͗����Ƃ����蓾�܂��B�����ł́A���̌����ƑΏ��@�E���Ö@�����������܂��B
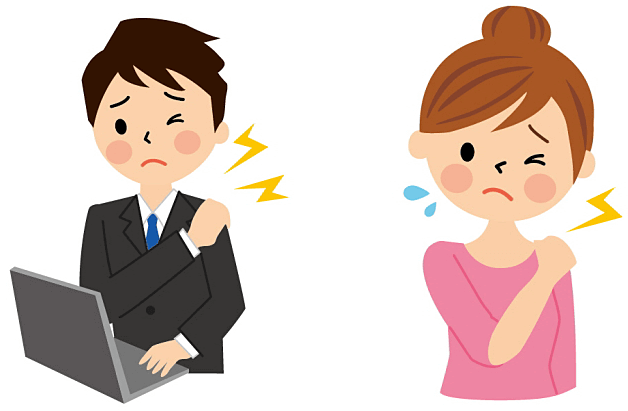
�����P�F �����肩�玕���ɂޏꍇ
���̏ꍇ�͂Q��ނ���܂��B�����肩�璼�ړI�Ɏ����ɂޏꍇ�ƊԐړI�ɒɂޏꍇ�ł��B
���ړI�ȏꍇ�F
�֘A�ɂƌ�����Ǐ���܂��B����́A���ۂ̒ɂ݂��N���Ă�ӏ��ƈႤ�ӏ����ɂތ��ۂł��B�Ⴆ�A���ۂ̒ɂ݂��S���Ȃ̂ɁA����r�ɒɂ݂�������Ƃ��������̂ł��B
�֘A�ɂ̌����́A�]�̊��Ⴂ�ɂ����̂ł��B�l�Ԃ̑̂ɂ͖����̐_�o������܂����A���̐_�o�����ɂȂ��Ă鏊������A�����Œɂ݂��N����Ǝ��ۂ̒ɂ݂��킩��Ȃ��Ȃ芨�Ⴂ����̂ł��B
������ɂ́A���ړI�Ɏ����ɂ��Ɗ��Ⴂ������֘A�ɂ̎d�g�݂����邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B
�ԐړI�ȏꍇ�F
������ɂ��A���R�p��������Ă��܂��B���ꂽ�p���œ����x���Ȃ��Ă͂����܂���̂ŁA��⌨�ɉߏ�ȃX�g���X��������܂��B
���̂����ŁA�㉺�̎����{���Ƃ͈Ⴄ�ʒu�Ŋ���ł��܂��Ƃ������Ƃ��N����܂��B
��������ƁA�{�����ɂ�����͂����ȏ�ɑ傫���͂�����̎��ɂ������Ă��܂�����A���鎕��������������������A�������������肷�邱�ƂŎ����ɂ�ł��܂��̂ł��B
�����Q�F �����ɂ�ł��猨���肪�N����ꍇ
���������⎕���a�Œɂ��ꍇ�́A�ɂ݂̂��鎕�������Ċ������Ƃ��܂��B
���̏ꍇ�A�����Ȋ��ݕ��ɂȂ�����A�ُ�Ȋ��ݕ��ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
�������Ċ��ݍ��킹�������Ȃ�ƁA�܂��A�S�̊߂ɕ��S��������܂��B
�A�S�̊߂ɕ��S��������ƁA�A�S�̋ؓ��E�_�o�ƌ��̋ؓ��E�_�o�͂Ȃ����Ă��܂��̂ŁA���R����������Ă���킯�ł��B
�܂��A���̒ɂ݂ł͂Ȃ��A���̊��ݍ��킹���̂������ꍇ�ɂ�������͋N����܂��B
����́A�傫���Q����܂��B
�P�ڂ́A���A�S�����E�ɓ����������ɁA�㉺�̉���������������ꍇ�ł��B�i�������ƌ����܂��j
�{���A�A�S�����E�ɓ��������ꍇ�͎��莕��������A�����͓�����Ȃ��̂ł��B�����̉�������͒��ړI�ɃA�S�̊߂ɕ��S��^���Ă��܂��܂��B
�Q�ڂ́A�㉺�̎������ݍ��킹�����ɁA�ꕔ�̎����������̎����������������Ă��܂��ꍇ�ł��B�����ڐG�Ƃ����܂����A���̎����A�A�S�̊߂ɕ��S���������Ă��܂��܂��B

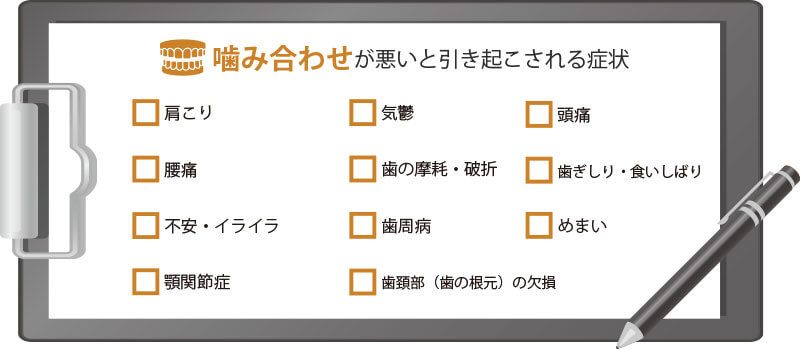
���Ö@�E�Ώ��@
���������ɂ߂āA�������������Ƃ��厖�ł��B
�����肩�玕�ɂ����Ă�̂ł���A������̌������l���Č�����������܂��傤�B
�܂��A���������̏ꍇ�͌����̎��������Ă������Ƃ��厖�ɂȂ�܂��B
���Ȉ�@�Ō�����f�f���Ă��炱�Ƃ����ɑ厖�ɂȂ�܂��B
���̊��ݍ��킹�������Ō����肪�N�����Ă�ꍇ�́A�����Ƀ}�E�X�s�[�X�����Ď������Ƃ��悭�s���܂��B
�}�E�X�s�[�X��t���邱�Ƃɂ���āA���ݍ��킹�̂ł��ڂ��̃A���o�����X���Ȃ����A�����S�̂̊��ݍ��킹���ϓ��ɂȂ�A�X���[�Y�Ɋ��ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B
�����Ȃ�ƁA�P�{�P�{�̎��ւ̕��S������A�܂��A�S�̊߂ɂ����镉�S������܂��B
��Q�鎞�͕K���t���܂��B�������p�\�R���Ƃ��C�������d���̎����t����Ɨǂ��ł��B
���X�ɁA��������A�H�����肪���܂��Ă��܂��B

�����g�łł��邱�ƂƂ��ẮA�A�S���������J����������肵�ăA�S�̋ؓ��̃X�g���b�`���s������A���̎���̋ؓ����ق����ׂɁA���܂��̃X�g���b�`�����Ă݂Ă��������B
�܂��A�X�}�z�ɂ��X�g���[�g�l�b�N���������Ȃǂ��Ă݂�Ɨǂ��ł��B
�����ɂ������͂�������܂��B��������Ȃ��̂Ɏ����ɂ��ꍇ�A�Ȃ�ł��낤�ƕs�v�c�ł���ˁI
����͒����ȊO�������̎��̒ɂ݂ɂ��ďڂ������������܂��ˁB
�����ȊO�̒ɂ݂͑傫���Q����܂��I
1�F �����ȊO�����������A�����̂��̂Ɍ���������ꍇ
2�F ���ȊO�������ŁA�����ɂޏꍇ
�ł��B
�قƂ�ǂ̕���1.�̗��R�ɂ��Ă͂܂�Ǝv���܂��̂ŁA�܂���1���炲�������܂��B
1�F�����ȊO�����������A�����̂��̂Ɍ���������ꍇ
�����P�F ���̍������ɔ^�����܂�a�C
���̏Ǐ�́A�������₩�Ԃ����ɋN���邱�Ƃ������ł��B�������₩�Ԃ����͐_�o���������ɂ��鏈�u�ł����A�_�o�̖������́A���ۂɊ������₷���̂ł��B
�Ȃ��_�o�̖��������������₷�������������܂��ˁB
�܂������Ȗ��O�������i�������j�ƌ����܂��B
�����āA�����̒��ɂ͖{���ɐ_�o���ʂ��Ă邵�A���ǂ��ʂ��Ă܂��B
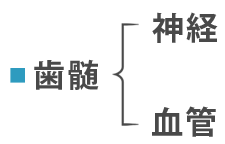
����ł��Ă��܂��B
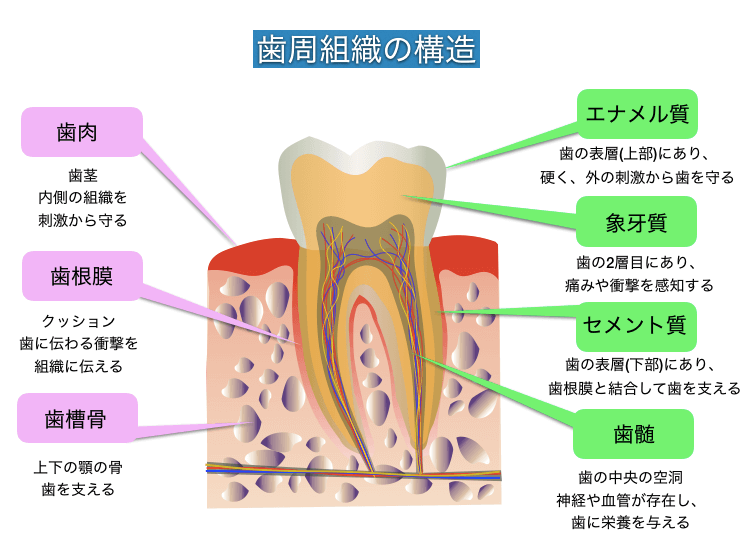
�ł��̂ŁA��������������Ƃ����̂́A���̒�����A�_�o�����łȂ����ǂ��Ȃ��Ȃ��Ă��ł��B
���ǂ̒��ɂ͔������Ȃǂ̖Ɖu�זE������A���ۂ�������Ă��܂��B
�Ƃ��낪�A�������Ă��܂��ƁA���̒�����Ɖu�זE�����Ȃ��Ȃ�A���̒��ɂ��ۂ������ė��Ă�������邱�Ƃ��ł����ɁA�������ĉ��ǂ��N�����Ă��܂���ł��B
��������Ď��̓����ɋN���������ǂ͍������̐���ۂ��獜�̒��ɐi��ōs���܂��B
�����āA���̍������̐���ۂɔ^�����܂��Ă��āA����A�@�����肵�����ɒɂ��̂ł��B
���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B
���R�́A
�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA
�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA
�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B
���Ö@
���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B
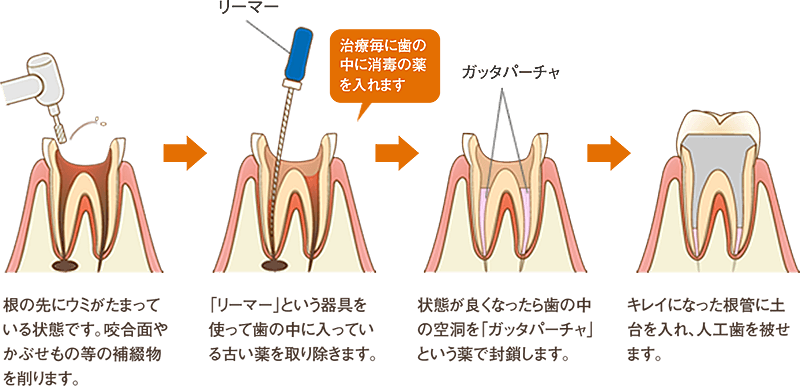
�����Q�F ���Ǝ��̊ԂɐH�ׂ������Q�`�R���l�܂����܂܂Ŏ��������N�����Ă���
���Ǝ��̊ԂɐH�ׂ��������܂邱�Ƃ͔��ɂ悭����܂��B
���̎��ɁA�H�ׂ������K�b�`�����Ǝ��̊ԂɁA�͂��܂��Ă��܂��ĂĎ��u���V���Ă����c���Ă��܂����Ƃ�����܂��B��������ƁA���\�ɂ݂܂��B
�ɂݎ��͎̂��s���ɂ�ł�̂ł����A�����ɂ��ƍ��o���Ă��܂����Ƃ��قƂ�ǂł��B
���Ö@�́A�͂��܂����H�ׂ�������菜���Ă��Β����Ɏ���܂��B
�����āA�ǂ��ɕ����͂��܂��Ă����̂��A�����Ď��u���V�̎d���𗝉�����Ĕ������ɂ����̂ŁA��r�I�ȒP�Ɏ���a�C�ƌ����܂��B
�ʏ�̓t���X�ŐH�ׂ�������菜���܂��B
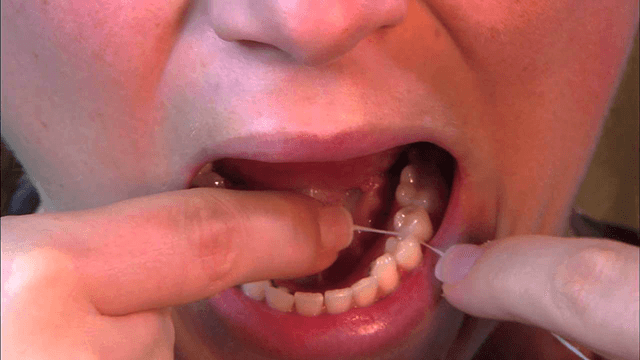
�����R�F �����a�Ŏ��������Ă�
�����O���O���ɂȂ��Ċ��ގ��ɒɂ݂��o����A���s�̎���o�����āA���R�ɉ������ĂȂ����ɂ��ɂނ��Ƃ��悭����܂��B
�����a�̎��Â����邱�Ƃ��厖�ł��B

�����S�F ���̊��ݍ��킹�������āA�������Œɂ�
���̎��Â��I����āA�l�ߕ��₩�Ԃ������������A����������Ȃ��Ă��̂܂܂ɂ��Ă����ꍇ�ɁA���̎��ɑ傫�ȕ��S���������Ēɂ݂��o�邱�Ƃ�����܂��B
�����ԕ��u����ƁA���̐_�o������ʼn��ǂ��傫���Ȃ�A���ɂ��N�������Ƃ�����܂��B
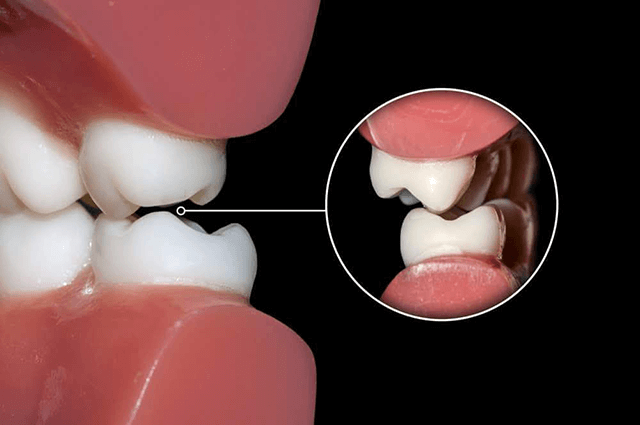
�����T�F �������茸���Ă�i�m�o�ߕq�̏ꍇ�j
���u���V�̗͂��������āA���̍������̂Ƃ��낪���茸�邱�Ƃ��悭����܂��B
�܂��A�H������⎕�����肪�Ђǂ������������茸��܂��B
�������茸�邱�Ƃɂ���āA�₽�����̂Ȃǂ̎h�������̐_�o�ɂƂǂ��₷���Ȃ��Ă��܂��A���݂�ȏ�ɒɂ��Ɗ����邱�Ƃ�����܂��B
���Ö@�Ƃ��ẮA���茸�����Ƃ�����A�����p�̎����ŋl�߂Ă�����ƒ����Ɏ��邱�Ƃ��唼�ł��B
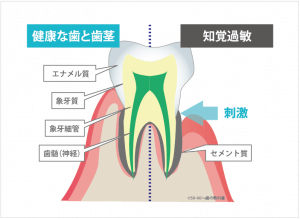
�����U�F ��������
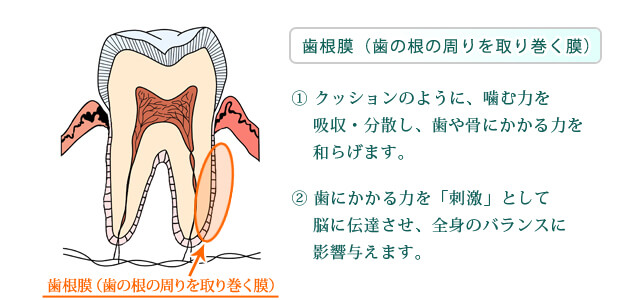
���������H������A�X�g���X�A�L�w�Ȃǂ̎p���̈�������A�������ɉ��ǂ��N���邱�Ƃ�����܂��B
���ݍ��킹�̈����������̎��ɋ����͂�������A���̎������ǂ��N�����Ă��܂��A�ɂ݂��o��̂ł��B
�킩��₷������������ƁA�����Ŗo�����悤�ȃC���[�W�ł��B
���Ö@�Ƃ��ẮA���R�����̏����ƁA�}�E�X�s�[�X�p���Ď����Ă����܂��B
�����V�F �e�m�炸
���e�m�炸�́A�P�W����R�O���炢�̊ԂŐ����Ă��܂����A�^������������Ƃ͌��炸�A�߂ɐ����邱�Ƃ����ɑ����ł��B
���̂��߁A������ߒ��Ŏ����a�̃o�C�ۂɊ������Ď����������ǂ��N�����Ēɂ�A������͂���O�̎��ɂ�����A��O�̎���������Ēɂ��Ƃ��������N���₷���ł��B
���̏ꍇ�́A�ꍇ�ɂ���Ă͐e�m�炸���Ȃ��Ă͂����Ȃ����Ƃ�����܂��B
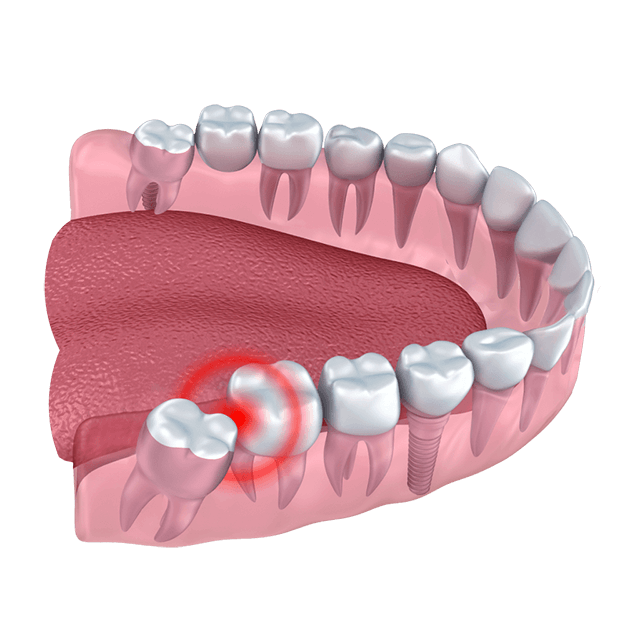
�����W�F �����������
�_�o�̂Ȃ����͋��x�����Ȃ藎���邽�߂ɁA�C�t���Ȃ������Ɋ��ꂽ��A�q�r�������Ă邱�Ƃ��悭����A�����ɂȂǂɒɂ݂��ł܂��B
�����̂̐_�o�͂Ȃ��̂ŁA���ꂽ�u�Ԃ̒ɂ݂������Ȃ��ׂɁA���ꂽ���ɋC�t���Ȃ����������ł��B
���ẤA���Ȉ�t�������A�����g�Q���ACT�ł�������f�f���A����̒��x���y����Όo�ߊώ@�����鎞������܂����A���x��������A�������Ȃ��Ƃ����Ȃ���������܂��B
�Q�F���ȊO�������ŁA�����ɂޏꍇ
��������Ȃ��̂Ɏ����ɂ��Ƃ��������ł͂Ȃ��āA�����̂���������Ȃ��̂ɁA�����ɂ��Ƃ������Ƃ�����܂��B
���̒ɂ݂��u�������Ɂi�Ђ����������j�v�ƌ����܂��I
�����ɂ��Ƃ������ƂŎ��Ȉ�@�ɗ���ꂽ���̂R���ƌ����Ă��܂��B�܂��A���Ǝ��ȊO�̗����Ɍ�����������͂X���ƌ����Ă��܂��B
���Ȉ�@�ɂ���ẮA�f�f������Ă��܂��A������������Ȃ��̂ɁA�����������A�_�o���������A�ň����������邱�Ƃ�����܂��B
�������茴�������ɂ߂�\�͂̂��鎕�Ȉ�@��I�Ԃ��Ƃ���ł��B
�����P�F �֘A��
�ɂ݂�������ƁA���̒ɂ݂͔]�ɓ`�����܂��B
�����āA�_�o�Ɛ_�o���ߐڂ��Ă�ꍇ�ł��ƁA���������ł͂Ȃ��̂ɁA���Ⴂ���N�����Ă��܂��A�����ɂ��悤�Ɋ�����̂ł��B�]�Ɛ_�o���֘A����ɂ��Ƃ������܂��B

�����Q�F �ؓ��̒ɂ�
���ނ��߂̋ؓ������ǂ��N�����Ēɂ݂��o��ƁA�����ɂ��Ȃ��Ĕ����ė~�����Ƃ������Ŏ��Ȉ�@�ɗ�����������܂��B
���������g�Q���⎋�f�A�G�f���ł�����Ă��˂��ɐf�@���Ă����Ɉُ킪�����Ȃ��̂ɁA���҂����̒ɂ݂��^���ꍇ�́A���̋ؓ��̒ɂ݂��l�����܂��B
���p��ŁA�u�E�ؖ������Ɂv�ƌ����܂��B
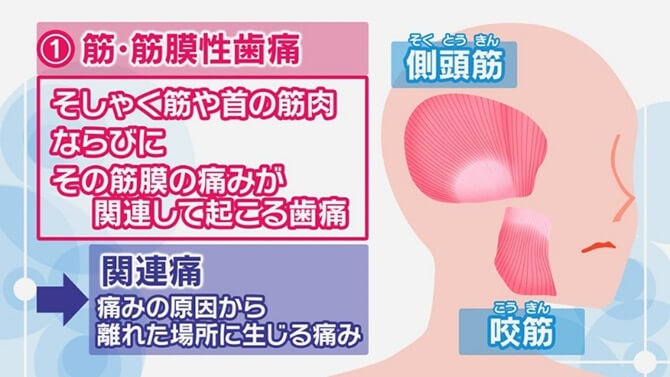
���ÂƂ��ẮA���������߂���A�}�b�T�[�W��������A�X�g���X�����炵����A�p���������Ȃǂ̐����K���̉��P��ڎw�����ƂɂȂ�܂��B
�����R�F �_�o���̂��̂���Q����Ă�ꍇ
1�̊֘A�ɂł́A���ȊO�̏ꏊ���ɂ��̂Ɏ����ɂ������܂������A�ɂ݂�`����_�o���̂��̂���Q�������ʁA�����ɂނ悤�Ɋ�����Ƃ����a�C�ł��B
�u�_�o��Q���u�Ɂv�ƌ����܂��B
���̓��A�ł������̂��u�O���_�o�Ɂv�ł��B�O���_�o�́A��A�S�≺�A�S�̐_�o�Ƀ_�C���N�g�ɂȂ����Ă��܂��̂ŁA���������ǂɈ��������ȂǏ�Q����Ǝ��Ɍ������ɂ݂��N�����܂��B
�ɂ��Ċ��Ȃ��A�Ђ����肪�ł��Ȃ��Ȃǂ̏Ǐo�܂��B
���Ö@�Ƃ��ẮA�Ö@��_�o�u���b�N�Ȃǂ̕��@������܂����A���o�O�Ȃ�]�_�o�O�ȓ��֏Љ�邱�Ƃ������ł��B
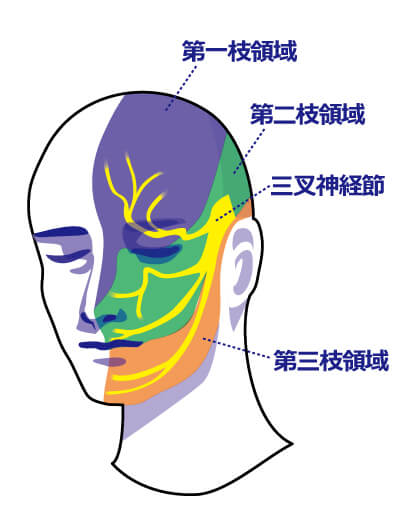
�����S�F ����
���ɂ̒��ł��Q�����ɂƌĂ�铪�ɂ�����܂��B
�Q�����ɂ͂P���ɉ��x���P���Ԃ��炢�N���܂��B���̓��ɂ͓��Ɏ��ɂƊԈႦ���₷���A�ԈႦ����m���͂P�P��������܂��B�ԈႦ����ƁA������Ă��܂�����A���̐_�o������Ă��܂����肵�܂��B
�Ȃ̂ŁA�T�d�Ȑf�f���K�v�ɂȂ�܂��B
���Ö@�́A�]�_�o�O�ȂɏЉ�邱�ƂɂȂ�܂��B

�����T�F ��{���ɉ��ǂ�����ꍇ
��{���́A���W���̒��̕@�̉��ɂ���ł��B���������ׂȂǂʼn��ǂ��N�����ƁA�������ɂނ��Ƃ�����܂��B������A��{�������ɂƌ����܂��B
���̏ꍇ�A�ʏ�͍��E�̕Е��̉������ɂ݂܂��B
���Ö@�́A��������������f�f���Č��ɂ߂āA��{�����̎��Â����邱�ƂɂȂ�܂��B
���Ȉ�@�����Ŏ���Ȃ��ꍇ�́A���@�Ȃɂ���`���Ă��炤���ƂɂȂ�܂��B
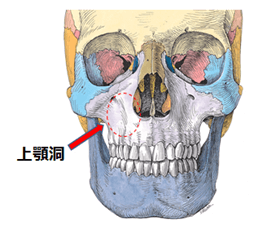
�����U�F �S���ɕa�C������ꍇ
�S�؍[�ǂ�A���S�ǁA�S�������Ȃǂ�����ꍇ�A���ɒɂ݂��y�ڂ����Ƃ�����܂��B
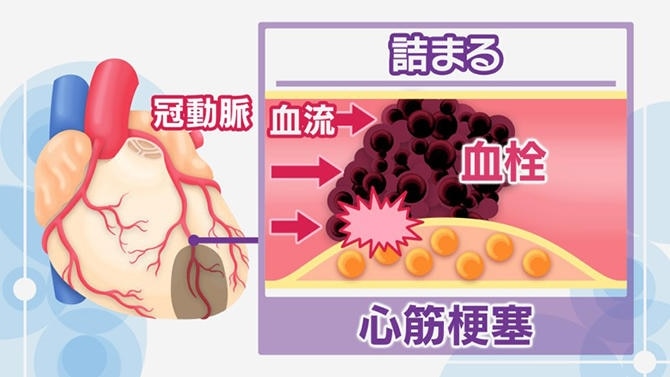
�����V�F �_�o���ǐ�����
���ɁA���ɕГ��ɂ̎��ɋN���鎕���ɂ��Ɗ����錻�ۂł��B
�������Ƃ����A���̐_�o�̉��ǂƒɂ݂����Ă邽�߁A���ʂ�����ł��B
�����W�F ���_�I�Ȃ��Ƃ�Љ�S���I�Ȃ��Ƃ������̏ꍇ
�s����X�g���X����������A���ɂȂ�����A���������ǂȂǂ̐��_�I�Ȏ��������Ŏ��ɒɂ݂��o�邱�Ƃ�����܂��B
���̗l�ɁA�����ɂ������͂�������܂��B
�K�Ȑf�f�����Ȉ�@�ŎāA�m���Ɏ������Ƃ��A���̎����̉����ɂȂ���܂��B
���߂Ɏ��Ȉ�@�Őf�Ă�����Ă��������ˁB
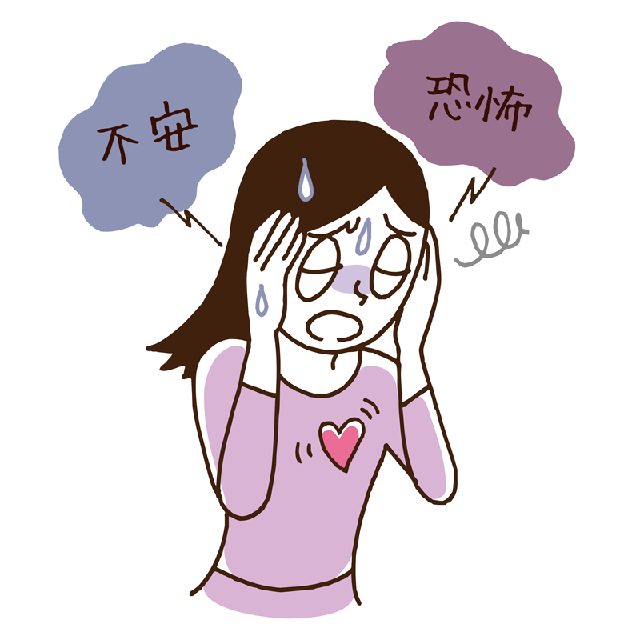
���̎��ÂŎ��ȉ@�ɒʂ��ĂāA���Ò��̎����ɂނ̂͂킩����ǁA���Ò��ȊO�̎����ɂނ̂͂ӂ����ł����A���Ȉ�@�ɕs�M�����������肵�܂���ˁB
�������܂ł����������҂�����o���������Ƃ�����܂��B
�����P�F ���Ò��ȊO�̎��̒ɂ݂����R�ɓ������ɋN����
�P���ɁA���Ò��ȊO�̎��̒ɂ݂����R�ɓ������ɋN���邱�Ƃ�����܂��B
���̏ꍇ�́A�{���ɋ��R�Ȃ̂ŁA�ǂ����悤������܂���B
�����ɂޗ��R�́A���̃T�C�g��1.�`15.�ɂ���܂��̂ŁA�܂��ǂꂩ�����Ă͂܂�͂��ł��B
�����Q�F ��蒚�J�Ɏ�����������悤�ɂȂ�A���ɑ���C�������q���ɂȂ���
���Ȏ��Â���悤�ɂȂ��āA����������蒚�J�ɂ��邱�Ƃɂ���āA���ɑ���C�������q���ɂȂ��Ă��݂���x�̏������ɂ݂�傫�������Ă��܂����Ƃ�����܂��B
�����R�F �������Ă����������A�h�����͂��₷���Ȃ���
�܂��A���݂����J�ɂ���ƁA���X�������������Ă����������A�h���������̎��̐_�o�ɓ͂��₷���Ȃ�A�ɂ݂������邱�Ƃ�����܂��B

�����S�F ���̂ӂ���l�ߕ����������������Ȃ�A���Α��̎��Ŋ��ނ��Ƃ������Ȃ���
���Â��Ă鎕�ɉ��̂ӂ���l�ߕ����������ɁA���̍��������������Ă��݂ɂ����A���Α��̎��Ŋ��ނ��Ƃ������Ȃ邱�Ƃɂ��A�ɂ݂��o�邱�Ƃ�����܂��B
�܂��A�������s��ŃA�S�̊߂ɕ��S��������A�A�S�����łȂ��A��⌨���ɂ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��B
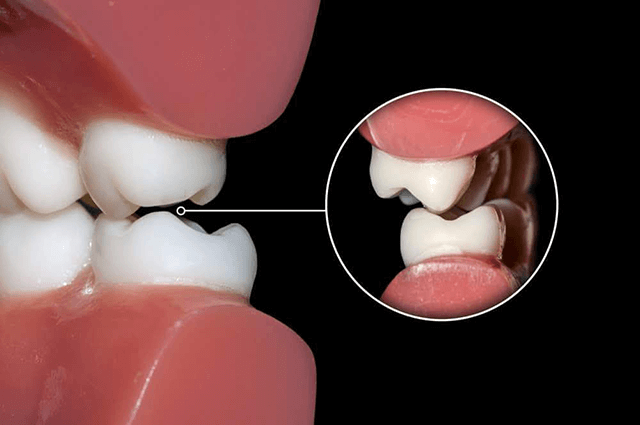
�����T�F ���f���Ɏ��Ȉ�t�����f�������
�Ō�ɁA����͗ǂ��b�ł͂���܂��A���f�̎��ɁA���Ȉ�t�����f������Ă��܂��A�����̎��ȊO�̎��Â��n�߂Ă��܂��A���܂��܂��̎��ɖ{���ɒɂ����̒ɂ݂����܂��Ă������A�Ăђɂ݂��o�Ă��܂����Ƃ������Ƃ��l�����Ȃ��͂Ȃ��ł��B

�钆�Ɏ����ɂ�A�d�����Ɏ����ɂ肵�āA�����Ɏ���҂ɍs���Ȃ���������܂���ˁB
����Ȏ��ɁA
�@�茳�ɂ�����ɂɌ����̂��Ƃ��A����ł����v�Ȃ̂��Ƃ��A
�A��ǂ�R���r�j�ł����Ɩ�������Ƃ��A
�B�ɂݎ~�߂������nj����Ȃ��Ƃ��A
�C������ނ���������҂ɍs���Ȃ��ėǂ��̂��Ƃ��A�F��Ȃ��Y�݂�����Ǝv���܂��B

����Ȃ��Y�݂��������邽�߂ɂ��������܂��ˁB
1. �茳�ɂ�����ɂɌ����̂��A����ł����v�Ȃ̂�
���Ȃ�`�O�Ȃł�������ɂݎ~�߂��茳�ɂ��邱�Ƃ��Ă悭����܂���ˁB
���̓��A���ɂɌ���������Љ�܂��ˁB��������̂ŁA�܂��͗L���Ȗ�S�����������܂��B
���ɂ̖�l�V��
�i���Ȉ�t�̎�������ɂ��܂����B�j
�l�V���P�F�{���^����

�ł��L���Ȓɂݎ~���ł��B
���ɂ͂������A�_�o�ɂ⍘�ɁA��p��̒ɂ݂Ȃ��S�ʓI�ɒɂ݂Ɍ�����ł��B
������ɂ���ꍇ�́A�����ɂ��C��t���Ă�����āA��x��1��25mg��2���T�O��������ʼn������B
�ɂ݂������ꍇ��2��50��������ʼn������B
�����Ĉ��ނƂ���6���Ԃ͊J���Ă��������B
�s ���ӎ��� �t
�����̂�����A�C���t���G���U�̕��Ȃǂ͕���p������̂ōT���ĉ������B
�܂��A�q������͑̏d������ň��ޗʂ��ς��̂łނ�݂ɂ͈��܂Ȃ��ł��������B
�D�w���������w����́A�P�[�X�o�C�P�[�X�Ȃ̂Ŏ��Ȉ�t�̔��f�����ł��������B
�l�V���Q�F���L�\�j��

���L�\�j�������Ȃ�L���Ȓɂݎ~�߂ł��B
�{���^�������l�A���ɁA��p��̒ɂ݁A�_�o�ɁA���ɂȂǂɌ����܂��B�{���^�����ƈႤ�̂́A���̑傫���ł��B
1�������a9mm�Ō������R�������炢�����đ傫���ł��B���܂����Ȃ����͂����݂ɂ����Ǝv���܂��B
������ɂ���ꍇ�́A�����ɂ��C��t���Ă�����āA��x��60��������ʼn������B�ɂ݂����Ȃ苭���ꍇ��2��120��������ʼn������B�����Ĉ��ނƂ���6���Ԃ͊J���Ă��������B
�s ���ӎ��� �t
�A�X�s�����b���̂�����A�d�ĂȊ̑��A�t���A�S���ɏ�Q��������Ȃǂ͕���p������̂ōT���ĉ������B
�܂��A�q������͑̏d������ň��ޗʂ��ς��̂łނ�݂ɂ͈��܂Ȃ��ł��������B
�D�w���������w����́A�P�[�X�o�C�P�[�X�Ȃ̂Ŏ��Ȉ�t�̔��f�����ł��������B
�l�V���R�F�o�t�@����

�o�t�@���������Ȃ�L���Ȓɂݎ~�߂ł��B�s�̂���Ă����A��ނ���������̂ŁA��ǂŔ������ɖ�t����Ɉ��ݕ����悭�����Ă��甃���Ă��������B
������ɂ���ꍇ�́A�����ɂ��C��t���Ă�����āA��͂�A���i�ɂ���Ĉ�x�Ɉ��ޗʂ��Ⴄ�̂ŁA�悭�m�F���Ă������ʼn������B
�s ���ӎ��� �t
���̒��ɍ܂ƈꏏ�Ɉ��܂Ȃ��ł��������B
�܂��A�d�ĂȊ̑��A�t���A�S���ɏ�Q��������Ȃǂ͕���p������̂ōT���ĉ������B
�܂��A15�Ζ����̎q������͈��܂Ȃ��ł��������B
�o�Y����̔D�w����́A���܂Ȃ��ł��������B
�����w����̓P�[�X�o�C�P�[�X�Ȃ̂Ŏ��Ȉ�t�̔��f�����ł��������B
�l�V���S�F�J���i�[��

�J���i�[�����L���Ȓɂݎ~�߂ł����A�{���^�����A���L�\�j���ƈႤ�Ƃ���́A���S���������A����p�����Ȃ��������p����r�I���S�Ȃ��Ƃłł��B�����A�ɂݎ~�߂Ƃ��Ă̌��ʂ͂��₩�ł��B
������ɂ���ꍇ�́A�����ɂ��C��t���Ă�����āA��x��1������ʼn������B�ɂ݂������ꍇ��5������ʼn������B�����Ĉ��ނƂ���4~6���Ԃ͊J���Ă��������B
�s ���ӎ��� �t
������A�����M�[�̂�����́A���Ȉ�t�ɑ��k���Ă��������B�܂��A�d�ĂȊ̑��A�t���A�S���ɏ�Q��������Ȃǂ͕���p������̂ōT���ĉ������B�s�̂̕��ז�ƕ��p���Ȃ��ʼn������B
�q����������߂܂����A���p�ʂ͑̏d�ɂ���ĕς��̂Ŏ��Ȉ�t�ɑ��k���ĉ������B
�����̑��Ŏ��ɂɌ�����
�� �W�N���t�F�i�N �� �{���^�����̃W�F�l���b�N���i�ł�
�� �����O���A�C�r�[ �� ���ɂɂ������܂��B�C�u�v���t�F���ł��B�s�̂���Ă܂�
�� ���L�\�v���t�F�� �� ���L�\�j���Ɠ����ł�
�� �|���^�[�� �� ���ɂɂ������܂��B
�� �C�u�v���t�F�� �� �����Ђ̒A�������ɂ́A���ɂɌ����Ƃ͏����Ă܂��A���ɂɂ������܂��B��p�@���̓��L�\�j���Ɠ����ł��B
�� �Z�f�X�n�C �� ���ɂɌ����܂��B�s�̂���Ă܂��B
�� �����J���A�Z���R�b�N�X�A�y�I�� �� ���ɂɌ����܂��B��p�@���̓{���^�����A���L�\�j���Ɠ����ŁA��X�e���C�h�n�������ɍ܂ł��B
�� ���L�\�}���� �� ���L�\�j���̃W�F�l���b�N���i�ł�
�� �m�[�V�� �� �J���i�[���Ɠ����A�Z�g�A�~�m�t�F���ŁA���ɂɃ}�C���h�Ɍ����܂�
�� �t���x�� �� ���ɂ̖�Ƃ��Ĉ�ʓI�ɕ��y���Ă��܂�
�� �C�ua �� �C�u�v���t�F���Ƃ������ɍ܂ł��B�s�̂���Ă܂��B�C�u�N�C�b�N�Ƃ���ނ���������܂�
�� �g���l�L�T���_ �� ���e�畆�ȂŔ�����V�~���Âɂ��g���Ă܂��B���Ȃł͏o���̗\�h�ɂ͎g���܂����A�ɂݎ~�߂Ƃ��Ă̌��ʂ͒Ⴂ�ł�
�� �o�C�G���A�X�s���� �� ��s�����n�̒ɂݎ~�߂ł��B���ɂɌ����܂��B�s�̂���Ă܂�
�Q. ��ǂ�R���r�j�ł����Ɩ������
�s�̂Ŕ����Ă鎕�ɂ̖�͂���������܂��B
�L���Ȃ̂́A�o�t�@�����A�Z�f�X�n�C�A�C�u�A�o�C�A�X�s�����Ȃǂł��B
���d�����Z����������ȂǂŁA����҂ɍs���Ȃ����́A���}�ň��ނ̂͗ǂ����Ǝv���܂��B
�����A�ɂ݂����܂���������Ȉ�@�̎�f���K�v�Ȏ��������ł��B

�R. �ɂݎ~�߂������nj����Ȃ�
�ɂݎ~�߂�����ł������Ȃ����Ƃ͓��R����܂��B�ǂ�ȏꍇ�����������܂��B
���������傫���Đ_�o�܂œ͂��Ă���A�_�o���������ǂ��N�����Ă���ꍇ
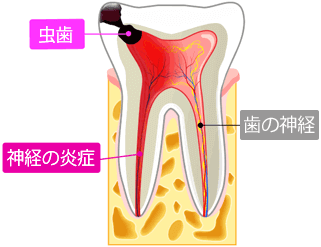
�����̐_�o������ŕ����Ă��܂��A�������ǂ��N�����Ă�ꍇ
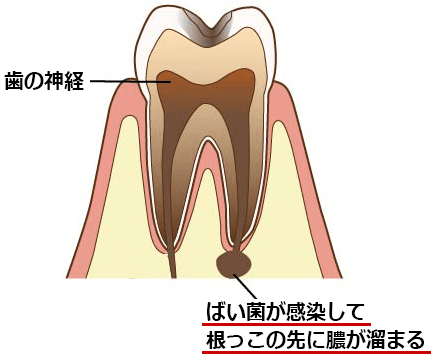
�����s�ɂ��ۂ��������A���s�ɋ������ǂ������Ă��܂��A���s���猌��^���o��ꍇ �Ȃǂł��B

������̉��ǂ��ɂݎ~�߂������Ȃ��������ǂł��̂ŁA���Ȉ�@�œK�Ȏ��Â������葼�ɂȂ��ł��B
�S. ������ނ����Ŏ���҂ɍs���Ȃ��Ă����̂��H
�{���͎���҂ɍs���Ȃ��Ă��ǂ��ꍇ
�������Œɂ݂����܂�Ȃ��ꍇ�́A����҂ɍs������܂��A�ɂ݂����܂����ꍇ�́A����҂ɍs���Ȃ��ėǂ��̂������܂���ˁB
����ɂ��Ă��������܂��ˁB
�� �y���������̏ꍇ
�������Ƃ́A�����ʂ莕�s�ɉ��ǂ��N���邱�ƂȂ̂ł����A���̒��x���y���ꍇ�́A�ɂݎ~�߂�A������ɒu���Ă������R�������Ŏ����Ă��܂��A��{�I�ɂ͑��v�ł��B
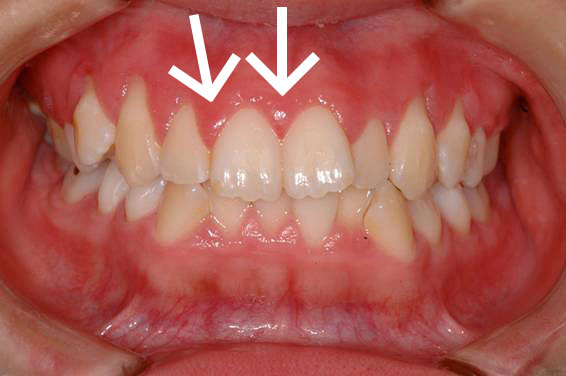
�� �m�o�ߕq���痈���ߐ��̒ɂ�
�m�o�ߕq�Ƃ͎������݂邱�ƂȂ̂ł����A���̎��Ɏ��ɒɂ݂������邱�Ƃ�����܂��B
����Ȏ��ɁA�ɂݎ~�߂������x�Œɂ݂����邭�炢�̉��ǂł���A�Ĕ��̉\�����Ⴂ�̂ŁA���Ȉ�@�ɍs���Ȃ��Ă��A��U�l�q������Ƃ������ő��v�ł��B
�������A�J��Ԃ����͎��Ȉ�@�ɍs���Đf�f����K�v������܂��B
�� ���������ɏ����ɂ�
���̏ꍇ�A�l�����邱�Ƃ͑傫���Q����܂��B
1�́A�y���������ł��B
�y���������͈�ߐ��̂��Ƃ������̂ŁA��U�ɂ݂����܂�Α��v�ł��B
2�ڂ́A���̐_�o�������Ƃɂ�艊�ǂ��N�������̂�����ǂ��A���̒��x���y���Ĉ��̏ꍇ�͉��ǂ��i�s���Ȃ����������̂ŁA��͂��U���ǂ����܂�Α��v�ł��B
�������A�Ĕ������ꍇ�͎��R�Ɏ���Ȃ����Ƃ������̂Ŏ��Ȉ�@�ɍs���Ă��������ˁB
����҂ɍs���ׂ����s���Ȃ��ėǂ��̂��A�����̂��Ƃ����ɂ߂�͔̂��ɍ���ł��B
�����A�����g�̔��f���Ԉ���Ă����ꍇ�A�Ǐi�s���Ă��܂��āA���̐_�o�����Ȃ��ƍs���Ȃ��Ȃ�����A�ň��͔����ɂȂ���������܂��̂ŁA�ł�����莕�Ȉ�@�֍s���Ă݂Ă�����ĉ������ˁB
�K������҂ɍs���Ȃ��Ƃ����Ȃ��ꍇ
�ɂݎ~�߂ł�������ɂ݂������Ă��A�ق��Ă��������ƈ����Ȃ�ꍇ������܂��B
�� �����炢�̒����̏ꍇ�A�ɂݎ~�߂Œɂ݂͂�����x���܂�܂����A�����������炢�̑傫���ɂȂ��Ă��܂������́A�i�s�͂Ƃ܂�Ȃ��̂ŁA�K�����Ȉ�@�Ŏ����K�v������܂��B
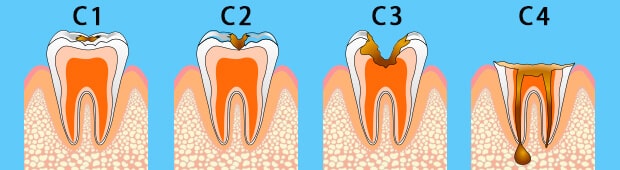
����}�łb�Q�Ə����Ă�̂������炢�̒����ł��B����������ċl�߂邾���Ŏ���܂��B
�����̐_�o�������Ĕ^���o�Ă�ꍇ�A�ɂݎ~�߂₲����ɃX�g�b�N���Ă�R�����������ނƈ�U�A�ɂ݂���͎��܂邱�Ƃ��܂�����܂��B
�����A���̎�̉��ǂ͈�U���܂��Ă��Ĕ�����\����������ɁA�Ĕ����J��Ԃ��Ȃ��牊�ǂ��i��ł����A���̍������̎���̍���n�����A�ň��͔����ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����̂ŁA�K�����Ȉ�@�ɍs���Ă��������B
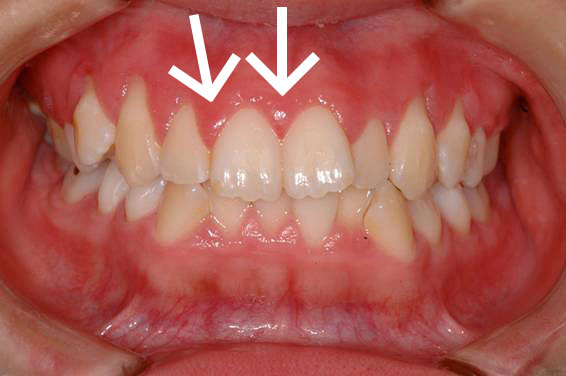
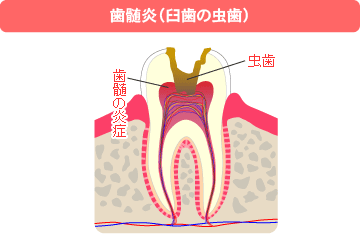
�������M�����Œɂ������ꍇ�́A���̐_�o���傫�ȉ��ǂ��N�����Ă邱�Ƃ������ł��B
�₽�����̂Œɂ��ꍇ�͈�ߐ��Ŏ��邱�Ƃ������̂ł����A�M�����Œɂ��ꍇ�͐_�o���������Ƃ����������ǂ��N�����Ă���A���ǂ��ǂ�ǂ�i��ł����܂��̂ŁA���Â̕K�v������܂��B
���̑��̐F�X�Ȓɂ݂�����܂����A�����Ƃ��ẮA���ȓI�ȕa�C�ƈႢ�A���̕a�C�͎��R�Ɋ��S�Ɏ��邱�Ƃ͏��Ȃ����߁A���Ȉ�@�ł̎�f�������߂������܂��B

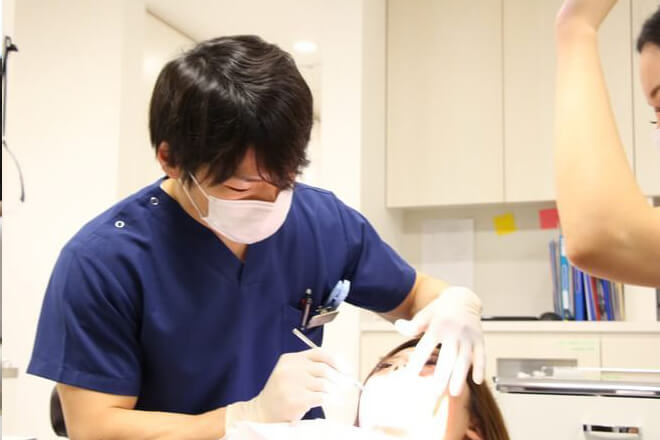
���̐_�o�����̂ɒɂ����Ƃ�����܂���ˁB�Ȃ�Ő_�o�����̂ɒɂ��̂��s�v�c�ł���ˁI
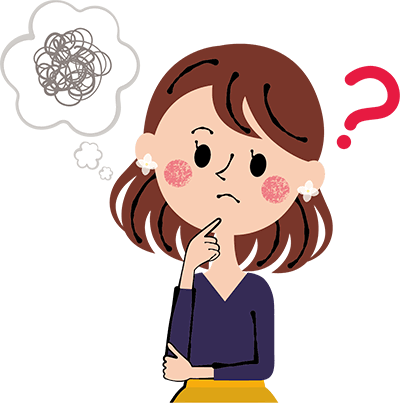
���̐_�o���Ă��܂��A���R�ł��������̂̒ɂ݂͐�ɂȂ��Ȃ�܂��B
�Ƃ��낪�A
�_�o��������
�Ȃ�Ă��Ƃ͂悭����܂��B
����Ȃ̂ɒɂނ̂͗��R������܂��B
���̗��R�����������܂��ˁB
�܂������Ȗ��O�������i�������j�ƌ����܂��B
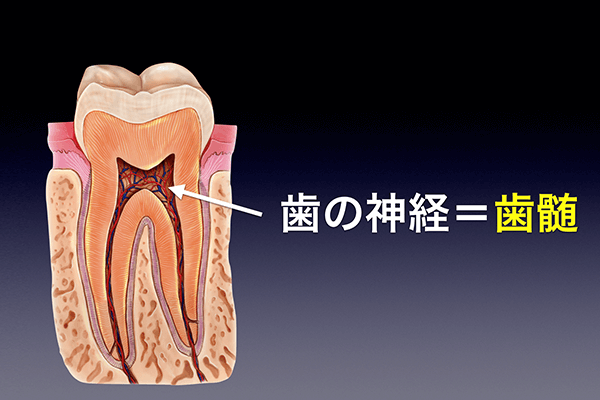
�����āA�����̒��ɂ͖{���ɐ_�o���ʂ��Ă邵�A���ǂ��ʂ��Ă܂��B
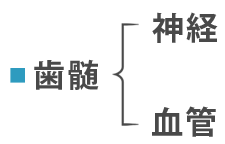
�Ƃ��������ł��B
�ł��̂ŁA�_�o�i�����j�������Ƃ����̂́A���̒�����A�_�o�����łȂ����ǂ��Ȃ��Ȃ��Ă��ł��B ���ǂ̒��ɂ͔������Ȃǂ̖Ɖu�זE������A���ۂ�������Ă��܂��B
�ł��̂ŁA�_�o�i�����j���Ă��܂��ƁA���̒�����Ɖu�זE�����Ȃ��Ȃ�A���̒��ɂ��ۂ������ė��Ă�������邱�Ƃ��ł����ɁA�������ĉ��ǂ��N�����Ă��܂���ł��B
��������Ď��̓����ɋN���������ǂ͍������̐���ۂ��獜�̒��ɐi��ōs���܂��B
���ǂ́A�������̐���ۂ��玕�����ւƐi��ōs���A����Ɏ������܂Ŋg�����Ă��܂��܂��B
���ɁA�������̐���ۂɔ^�����܂�i����a���j���Ƃ������ł��B���̔^�݂ɂ���āA�ɂ݂��o�Ă��܂���ł��I
�����ŁA���}�������������B�������̐���ۂɔ^�����܂��Ă��܂��I
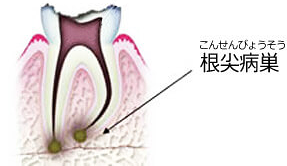
���_�o���������������āA�������̐���ۂɔ^�����܂����l�q

���_�o���������������āA�������̐���ۂɔ^�����܂����l�q
�^�����܂��āA���̒��ɂ������Ă��܂��ƌ��ɂ��N�������Ƃ�����܂��B
���̉��ǂ͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������I
���R�́A
�@���ǂ��i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA
�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA
�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����
�Ȃǂł��B
���Ö@
���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o�����Ƃ��挈�ł��B�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA�����ɂ�����ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�������̊ǂ̒��ɖ���߂Ă���A�Ăт��Ԃ��������܂��B
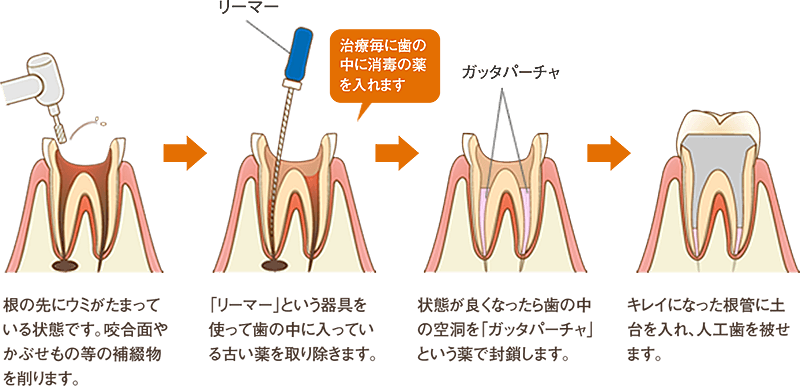
�������̎��Ấu���ǎ��Áv�ƌ����܂����A���̎��Â͊ȒP�ł͂Ȃ��A���̎��Ȉ�@�łȂ��ƒ��X�L���C�Ɏ���܂���B�K���A���ǎ��Â����ӂȎ��Ȉ�@�Ŏ��Â����Ă��������B
���L�ɁA���ǎ��Â����ӂȎ��Ȉ�@�������Ă��܂��B
�����O���O�����Ēɂ��ꍇ�́A�傫���T�̌���������܂�
�����P �����a�̏ꍇ�i���u����Ɣ����̊댯��������j
�����Q ���̍�����������Ă�ꍇ
�����R ���̍������̐�ɔ^�����܂��Ă�ꍇ
�����S �킹����y��̐ڒ��܂����ꍇ
�����T ��������̏ꍇ
�ł��B���ꂼ�����Ö@���S�R�Ⴂ�܂��̂ŁA���J�ɂ��������܂��ˁB
����1 �����a�̏ꍇ
�i���u����Ɣ����̊댯��������j
�����O���O������ꍇ�̌����ň�ԑ����̂������a�ł��B
�����a�Ƃ́A������₷�������ƁA�����x���Ă����̍����n���Ă��܂��a�C�ł��B
�x���Ă鍜���n���܂��̂ŁA���R���̓O���O�����Ă��܂��B

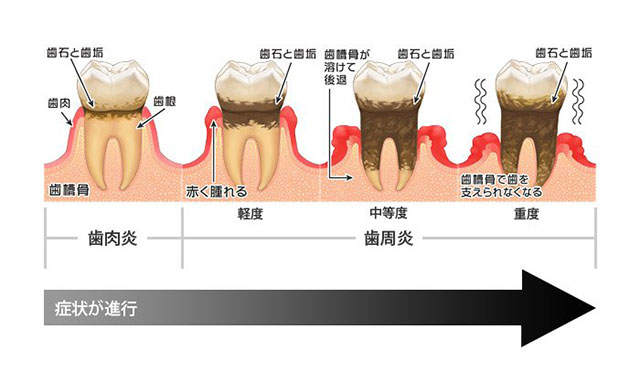
���Ö@
�����a�̎��ÂɂȂ�܂��B
�����a�͓��{�l�����������ő�̌����ł��B
���߂Ȃ玡��܂��B�K�����߂Ɏ����ĉ������B�i�s����Ǝ���ɂ����Ȃ�܂��B
����2 ���̍�����������Ă�ꍇ
���̍�����������Ă�Ƃ����܂�C���[�W�ł��Ȃ���������܂��A���͌��\����܂��B�Ⴂ���ł��悭�N����܂��B �����̂́A�_�o�̖������̂��Ԃ����ɋN���邱�Ƃ��唼�ł��B
�����́A�_�o�̖������͎��Ɍ����ʂ��ĂȂ����߁A������ʂ��Ď��ɉh�{�����Ȃ��̂ŁA���̋��x�������Ă�����ł��B �i�_�o���������́u�����v�ƌ����āA�_�o�ƌ��ǂ��ʂ��Ă��܂��B�j
���x�������Ă鎕�Ŗ����ł����̂�H�ׂ�킯�ł�����A�q�r�������Ă��܂��Ċ�����ł��B
�����āA����Ă��܂��ƁA�����̂��O���O�����Ă��܂��B
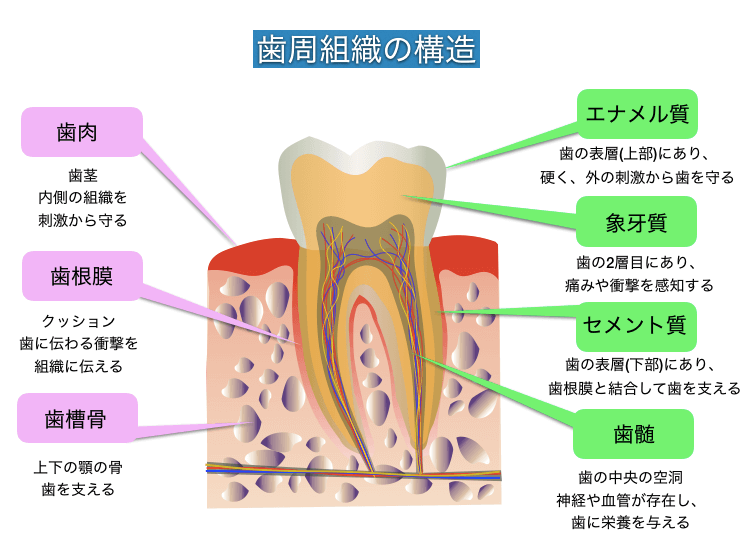
�� ��̓I�ȃq�r�̗�
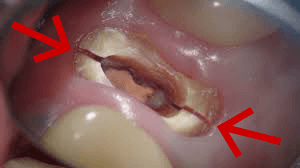
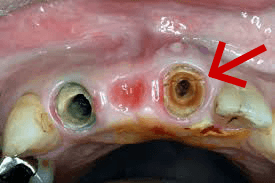
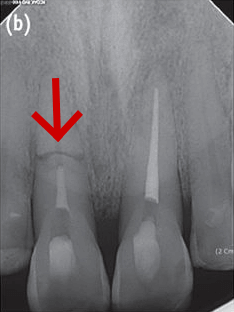

���Ö@
���̍����������ꂽ�ꍇ�́A���ꂽ�ʒu�ɂ���Ď��Ö@���ς��܂��B
�@�q�r���������̏�̕��ɏ������������Ă�ꍇ�̓q�r��ڒ��܂̂悤�ȕ⋭�܂Ŗ��߁A�������̒��ɏ�v�ȓy������Ă��炩�Ԃ��������������x����܂��B
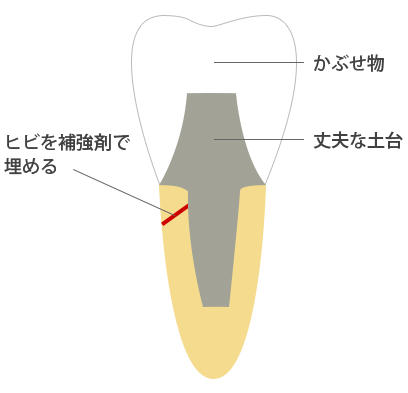
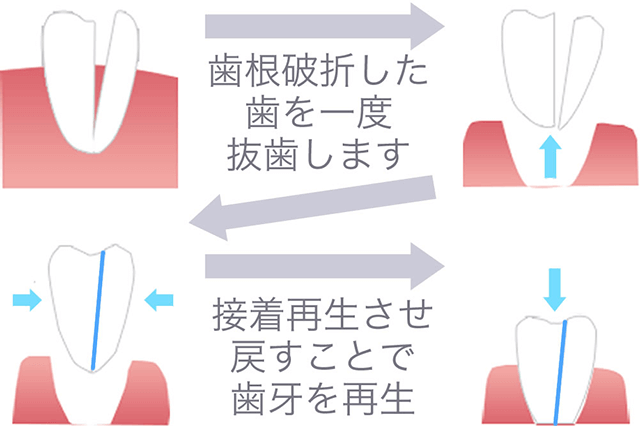
�A�q�r���������̐[���ʒu�ɓ������ꍇ�́A��x�����ăq�r��⋭�܂Ŗ��߂āA�܂����ɖ߂����Ái�ĐA�p�j�����܂��B�����A�ĐA���Ă��������Z���Ȃ邱�Ƃ������ł��B�i�ĐA�ł��Ȃ���������܂��j
�����A�q�r���[���ꍇ�̑����͎c�O�Ȃ��甲���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������ł��B
�q�r���g�勾�i�}�C�N���X�R�[�v�j���g���Ď��Â���Ǝ���m����������܂��̂ŁA�ǂ����Ă����������Ȃ����ɂ͂������߂̎��Âł��B

����3 ���̍������̐�ɔ^�����܂��Ă�ꍇ
���̍������̐�ɔ^�����܂����ꍇ�́A�������̐�̍���n�����Ă��܂��A������������Ƃ�����܂��B
�ǂ�Ȏ��ɍ������̐�ɔ^�����܂邩�ƌ����ƁA���̓��������ۂɊ����������ł��B
���̊����́A�������₩�Ԃ����ɋN���邱�Ƃ������ł��B
�������₩�Ԃ����͐_�o���������ɂ��鏈�u�ł����A�_�o�̖������́A���ۂɊ������₷���̂ł��B
�Ȃ��_�o�̖��������������₷�������������܂��ˁB
�܂������Ȗ��O�������i�������j�ƌ����܂��B
�����āA�����̒��ɂ͖{���ɐ_�o���ʂ��Ă邵�A���ǂ��ʂ��Ă܂��B
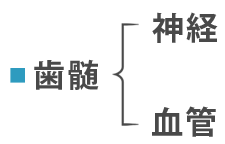
����ł��Ă��܂��B
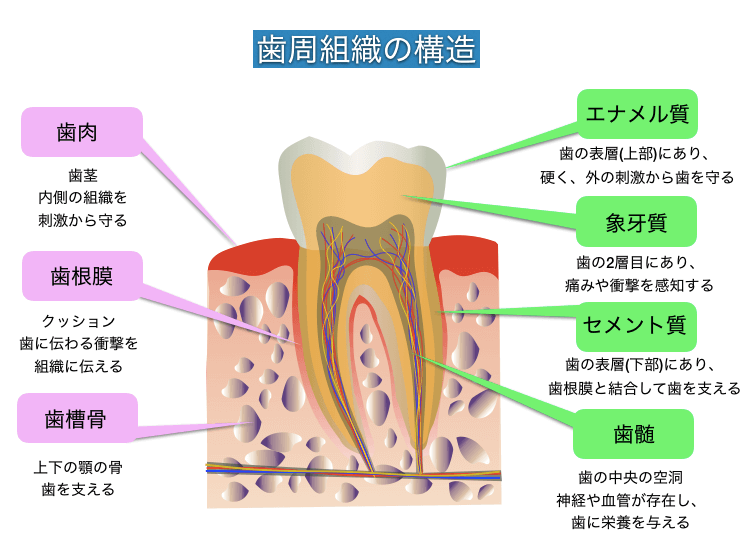
�ł��̂ŁA��������������Ƃ����̂́A���̒�����A�_�o�����łȂ����ǂ��Ȃ��Ȃ��Ă��ł��B
���ǂ̒��ɂ͔������Ȃǂ̖Ɖu�זE������A���ۂ�������Ă��܂��B
�Ƃ��낪�A�������Ă��܂��ƁA���̒�����Ɖu�זE�����Ȃ��Ȃ�A���̒��ɂ��ۂ������ė��Ă�������邱�Ƃ��ł����ɁA�������ĉ��ǂ��N�����Ă��܂���ł��B
��������Ď��̓����ɋN���������ǂ͍������̐���ۂ��獜�̒��ɐi��ōs���܂��B
�����āA���̍������̐���ۂɔ^�����܂��Ă��āA�����O���O��������A����A�@�����肵�����ɒɂ�A����̂ł��B
���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B
���R�́A
�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA
�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA
�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B
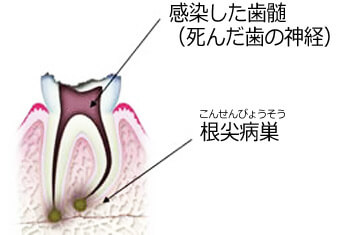

���Ö@
���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B
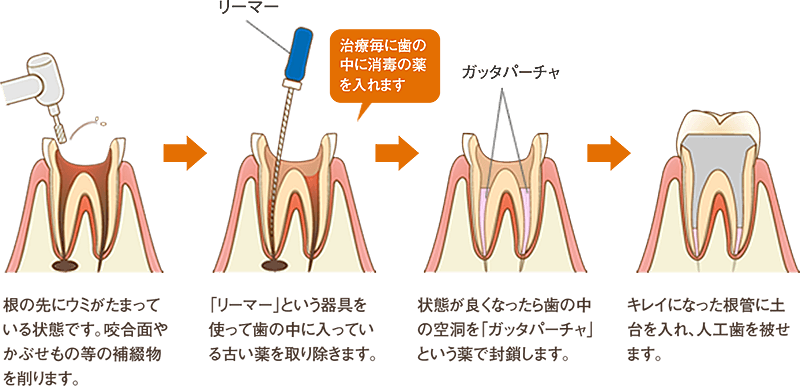
����4 ���Ԃ�����y��̐ڒ��܂����ꍇ
���Ԃ�����y��́A���ɐڒ��܂ň����t���Ă��ł����A���̐ڒ��܂��n������A�j�ꂽ�肵�āA�ڒ����キ�Ȃ邱�Ƃ�����܂��B
�����Ȃ�ƁA�P���ɂ��Ԃ������O��悤�Ƃ��āA�O���O�����Ă����ł��B
�܂��A�y��̐ڒ������ނƁA�y�䂲�Ɠ����Ă��܂��B

�� ���Ԃ��������ɐڒ��܂ň����t���܂��B���̐ڒ��܂��n����Ƃ��Ԃ�����������Ă��܂�

�� �܂��A���̒��ɓ����y����ڒ��܂ň����t���܂��B���̐ڒ��܂��n�����ꍇ�́A�y�䂪�����Ă��܂��B
���Ö@
�@��U�A�O�ꂩ�����ăO���O�����Ă邩�Ԃ�����y���������O���܂��B���̌�A���Ԃ�����y��A�����̂Ɉُ킪������A����ň�ԋ����ڒ��܂Őڒ��������܂��B
�A���Ԃ�����y�䎩�̂ɁA��j�����������ꍇ�́A�V������蒼���܂��B
�B�����̂ɒ������������璎��������Ď���Ă���A���Ԃ�������蒼���܂��B
���̏ꍇ�́A���߂̎��Â��K�v�ɂȂ�܂��B�ق��Ă����ƁA�����̂�����Ă��܂��A�����ɂȂ邱�Ƃ����邩��ł��B
����5 ��������̏ꍇ
�������肪������́A���ɋ����͂��������Ă��܂��܂��B
���ɁA����̎��ɗ͂������邱�Ƃ������ł��B
�����āA���̎��̎���̍��Ƀ_���[�W��^���Ă��܂��āA�����O���O�����Ă��邱�Ƃ�����܂��B
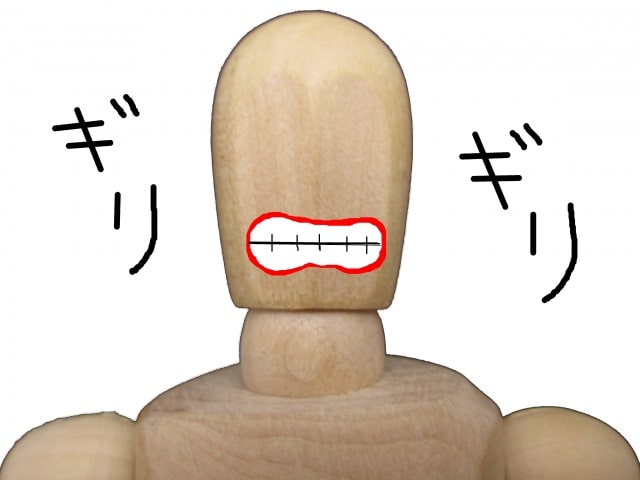

���Ö@
��������E�H��������������Ö@�ɂȂ�܂��B
1. ���ݍ��킹������
���̂��ݍ��킹���ǂ��Ȃ��āA�㉺�̎������������鏊���������ꍇ�A���������茸�����犚�ݍ��킹���ǂ��Ȃ�̂ŁA���茸�炻���Ƃ��āA�m�炸�m�炸�Ɏ�����������Ă��܂��܂��B
�˂Ȃ̂ŁA���Ö@�Ƃ��ẮA���ݍ��킹�̐f�f�����āA�����I�ɋ���������Ƃ�����ق�̏������Ȃǂ��Ď����܂��B
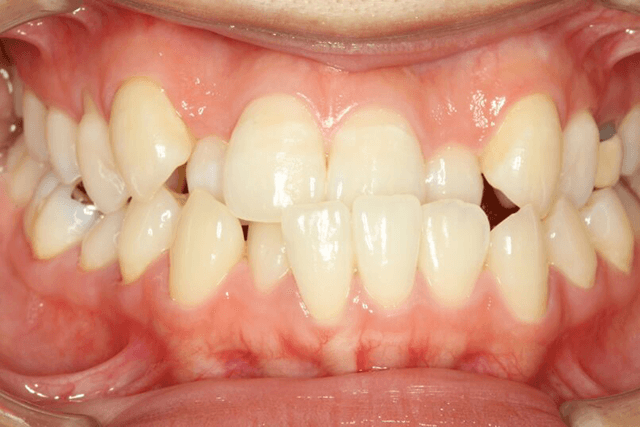
2. �}�E�X�s�[�X�Ŏ���
�i�ی��������܂��j
�}�E�X�s�[�X��t���邱�Ƃɂ���āA���ݍ��킹�̂ł��ڂ��̃A���o�����X���Ȃ����A�����S�̂̊��ݍ��킹���ϓ��ɂȂ�A�X���[�Y�Ɋ��ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B�����Ȃ�ƁA�P�{�P�{�̎��ւ̕��S������A�܂��A�S�̊߂ɂ����镉�S������܂��B
��Q�鎞�͕K���t���܂��B�������p�\�R���Ƃ��C�������d���̎����t����Ɨǂ��ł��B
���X�ɁA��������A�H�����肪���܂��Ă��܂��B

3. �X�g���X
�X�g���X������ƁA�͔̂������Ă��܂��Ď���������N�����₷���Ȃ�܂��B�i�����A�X�g���X���U�ׂ̈Ɏ�������͂�����x�K�v�ł�����܂��B�ł����A�Ђǂ���������͍���܂��j
�˃X�g���X�����߂Ȃ������ɕς��邱�Ƃ��K�v�ł��B

4. �����ɋN���鎕�������
�����Ɏ�����������Ă�ƋC�t������A�Ƃɂ������̗͂��ĉ������B
�㉺�̎������킳���ɗ����ĉ������B�H�ׂ���A���肷��Ƃ��ȊO�͋ɗ͎������܂Ȃ��悤�ɋC��t���ĉ������B
�����āA�A�S�̗͂������āA�����y�ɂ��ăX�g���b�`���ĉ������B
�ӎ��I�ɂ���𑱂��邱�Ƃ����ʂ�����܂��B
5. ��Q�Ă鎞�̐H�������
��Q��O�́A�[���Ȃ��Ƃ͍l�����ɁA�y�������Ƃ��l���ă����b�N�X���Ă��������B
���̗ǂ��������Ƃ邱�Ƃ��H������\�h�ɂȂ�܂��B
���̒ɂ݂̌�������������ɂ���̂ɁA�����������̎��Â������炵�Ă��������܂���B
�{���̌����������Ď����Ȃ��Ƃ����܂���B
�����g�ł̓X�g���X�̗\�h�ɂ��w�߂Ē�������ŁA���Ȉ�@�����Ў�f���Č����Ƒ�������炩�ɂ��āA���Â��ĉ������ˁB

�˂��̏ꍇ�́A�_�o�̉��ǂ��l�����܂��B
�_�o�̉��ǂ͐����ɂ��u�������v�ƌ����܂��B
���������N�����̂͂Q����������܂��B
�����P�F ���������̐_�o�܂Ői��ł���ꍇ
�����̑傫���ɂ͒i�K������܂����A�b�R�ƌ����Ē��������̐_�o�܂ōs���Ă��܂��ƁA���Ȃ�ɂ݂܂��B
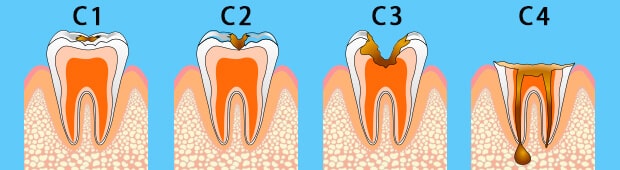
���������̐_�o�܂ōs���ƁA�_�o�������̂��ۂɂ���ċ������ǂ��N�����܂��B
�����āA���Ȃ苭���ɂ݁i�Y�L�Y�L�A�ǂ�����ǂ�����etc�j���o�Ă������܂��B
�ɂݎ~�߂������ɂ����Ȃ�܂��B
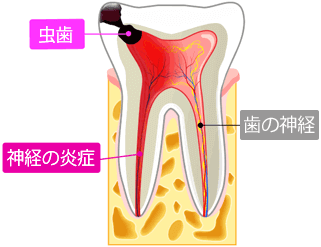
���Ö@
�ʏ�A�����̒ɂ݂ɂ͒i�K������܂����A���������̐_�o�܂ōs���Ă��܂��ƁA���Ȃ�ɂ݂܂��B
���̏ꍇ�́A���̐_�o����菜�����Â����Ȃ��Ƃ����܂���B�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����Ɏ��܂�܂��B
�ˁi���Ӂj�������A���̐_�o�͂Ȃ�ׂ����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͂Ȃ�ׂ��_�o���c���悤�w�͂����Ă��܂��B
��̓I�Ȏ��Ö@
�@�܂��A�ɂ�ł鎕�ɖ��������܂��B
���@�ł͖����͒ɂ��Ȃ��ł��܂��B�ɂ��Ȃ����R�͂������B
�A���������������������A����������Ď��A���̌㎕�̐_�o��j�̂悤�Ȋ����g���Ď��܂��B
������������������Ă�̂Œɂ݂͑S������܂���B
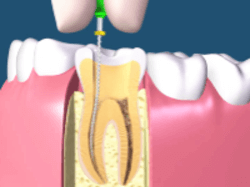
�B�_�o�����I�������A���̓����ɏ��ł̖�����āA�ӂ������ĂP��ڂ̎��Â͏I���ł��B
�C���̐_�o���������ɁA��U���ǂ��N���܂����A���ꂪ�P�`�Q�T�ԂŎ��܂�����_�o�̑���ɂȂ����l�߂܂��B

�������ʂ��Ă�̂��A�_�o�̑���ɂȂ��ł��B
���@�̖������ɂ��Ȃ����R
1�F�����̒��˂̐j���h�������ɂ݂��Ȃ���
���ƌ����Ă��A�j���h�����̒ɂ݂�h�����Ƃ��厖�ł��B
�����ɍׂ̐j���g���Ă���
�ːj�����ׂ��̂ŁA�����̒��Ɏh�������ɂ��킩��ɂ����B
���ɂ݂�������זE(�ɓ_)�̏��Ȃ��ӏ��ɍŏ��ɑł�
�˒ɓ_�����Ȃ��̂Œɂ݂ɂ����ł��B
���j���h���u�Ԃ́A�������̔S���ۂ̊v�̂悤�ɁA�s���ƒ����Đj����C�Ɏ������ɓ���悤�ɂ���B
�˂��̂悤�ɂ���Ɛj���h�������Ƃ��킩�炸�A���҂���ɂ́A�u�ŋ߂̖����͒��˂���Ȃ���ł����H�v�ƕ�����邱�Ƃ������ł��B

�Q�F������𒍓�����Ƃ����ɂ݂��Ȃ���

������͉t�̂Ȃ̂ʼn��x���Ⴂ�̂ł����A�������鎞�ɉ��x���Ⴂ�ƁA�̂��₽�������Ă��܂��Ɠ����ɒɂ������Ă��܂������ƂȂ�܂��B
���@�ł͂��炩�����������̉����炢�ɉ��߂Ē������܂��̂��A���җl�͋C�t����܂���̂ŁA�ɂ݂������܂���B
����ƁA�����ւ������̃X�s�[�h�����Ȃ������肵�Ă��܂��B�}���Œ�������ƁA���������Ă��܂��ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
���@�ł́A�P�H���P�b���炢�̂������Ƃ����X�s�[�h�ōs�����ŁA�����̑��ݎ��̂ɋC�t����܂���B
�����Q�F �����Ƀq�r������A����������ۂ��_�o�Ɋ��������ꍇ
�ł����������A�����Ԃ������A�����������Ђǂ�������A�����������ȂǂŁA���Ƀq�r�����邱�Ƃ�����܂��B
�q�r�������Ă��܂��ƁA����������ۂ��_�o�܂ōs���Ă��܂��A���ǂ��N�������Ƃ�����܂��B

�� ���Ƀq�r�������Ă�l�q
���Ö@
1�F�_�o�̉��ǂ��ア�ꍇ
���̏ꍇ�́A���̃q�r���C���ėl�q���݂܂��B��C�Ő_�o�̒ɂ݂�����A����Ŏ��Â͏I���ł��B
�����A�ɂ݂����Ȃ��ꍇ�́A���̐_�o����菜�����Â����Ȃ��Ƃ����܂���B�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����Ɏ��܂�܂��B
�ˁi���Ӂj�������A���̐_�o�͂Ȃ�ׂ����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͂Ȃ�ׂ��_�o���c���悤�w�͂����Ă��܂��B
2�F�_�o�̉��ǂ������ꍇ
���̏ꍇ�́A�c�O�Ȃ������̐_�o����菜�����Â����Ȃ��Ƃ����܂���B
�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����Ɏ��܂�܂��B
3�F���ɓ������q�r���傫���ꍇ
�q�r�������炢�̏ꍇ�́A���̐_�o����������ƂŁA���Ԃ���������̂ł����A�q�r�����̍������̕��܂ōs���Ă��܂��Ă�ꍇ�́A�����Ȃ��Ƃ����Ȃ���������܂��B


�������A�Ȃ�ׂ����͔����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͂Ȃ�ׂ������Ȃ��悤�w�͂����Ă��܂��B
�������Œ��Ӂ�
���Â���K�v���Ȃ��q�r������܂��B
���}�̂悤�ɁA�O���ɂ��ĂɃq�r�������Ă�ꍇ�ł��B
�O���͕\�ʓI�ɂ��̂悤�Ȕ����ȃq�r������₷���̂ł����A���Â̕K�v�͂���܂���B
���̃q�r�ɏڂ������Ȉ�@�Œ��J�ɂ݂Ă�����ĉ������ˁB

�� �O���̂��Ẵq�r
���̍�����t�������ɂ����Ƃ�����܂���ˁI


�������̐�ɂł����݂̂����Ȃ̂��ł��邱�Ƃ�����܂��B
���̏Ǐ�́A���̐_�o������Ă鎕��_�o������ł��܂������ɋN����܂��B
�i�⎕�ȂǁA���Ԃ����̎��ɂ悭�N����܂��j
���̗��R�����������܂��ˁB
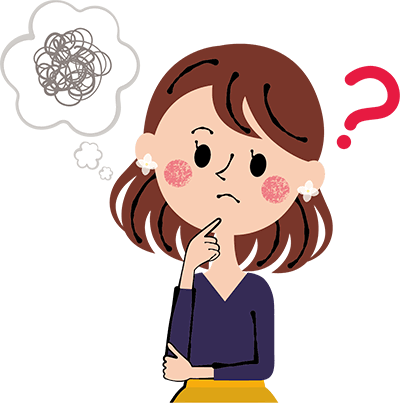
�܂������Ȗ��O�������i�������j�ƌ����܂��B
�����āA�����̒��ɂ͖{���ɐ_�o���ʂ��Ă邵�A���ǂ��ʂ��Ă܂��B
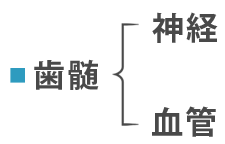
����ł��Ă��܂��B
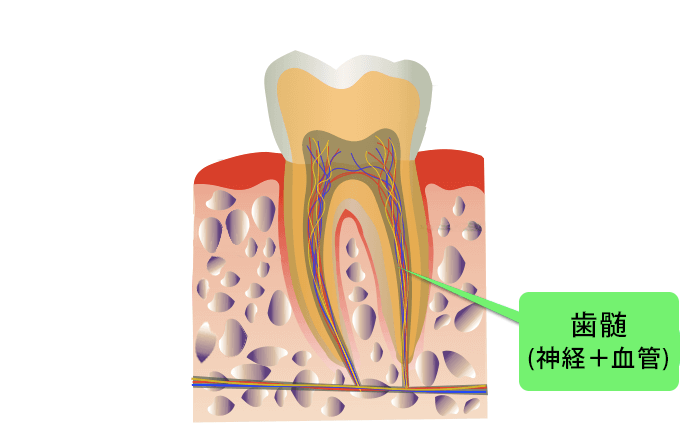
�ł��̂ŁA�_�o����������Ƃ����̂́A���̒�����A�_�o�����łȂ����ǂ��Ȃ��Ȃ��Ă��ł��B ���ǂ̒��ɂ͔������Ȃǂ̖Ɖu�זE������A���ۂ�������Ă��܂��B
�Ƃ��낪�A�������Ă��܂��ƁA���̒�����Ɖu�זE�����Ȃ��Ȃ�A���̒��ɂ��ۂ������ė��Ă�������邱�Ƃ��ł����ɁA�������ĉ��ǂ��N�����Ă��܂���ł��B
��������Ď��̓����ɋN���������ǂ͍������̐���ۂ��獜�̒��ɐi��ōs���܂��B
�����ŁA������x���}���������������B
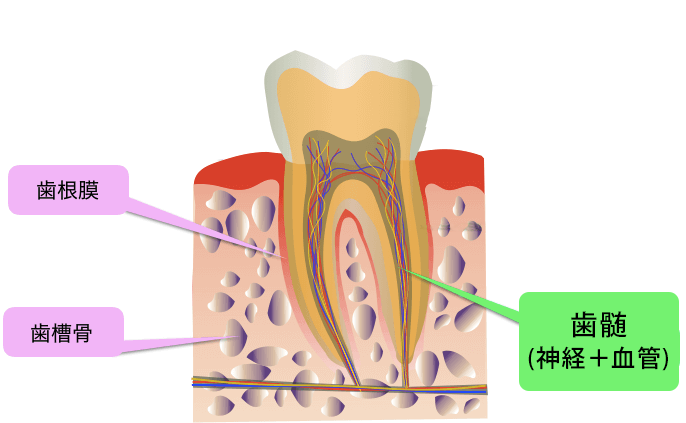
�_�o�̎���ɂ́A�������Ƃ����g�D���������Ƃ�����������܂��B
���ǂ́A�������̐���ۂ��玕�����ւƐi��ōs���A����Ɏ������܂Ŋg�����Ă��܂��܂��B �����Ȃ邱�Ƃɂ���āA�_�o���������ɂނ�ł��B
�������⎕���������ǂ��N�����Ă��܂��A���R���̎��͒ɂ��Ȃ�܂��B���̐_�o�������ł��A�����ł��B
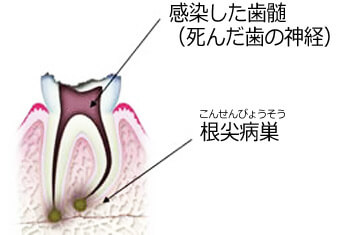
���_�o���������������āA�������̐���ۂɔ^�����܂����l�q

���_�o���������������āA�������̐���ۂɔ^�����܂����l�q
���̉��ǂ̐������̂́u���됫�������v�ƌ����܂��B
���̉��ǂ͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B
���R�́A
�@���ǂ��i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA
�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA
�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B
���Ö@
���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B
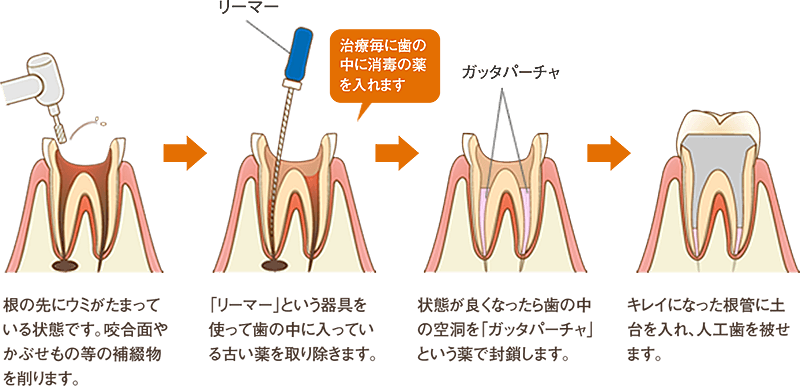
���@�o�Ƃ́A�@�̎��͂̓��W���ɊJ���Ă����Ԃ̂��ƂŁA�S��ނ���܂��B
�̂S�ł��B
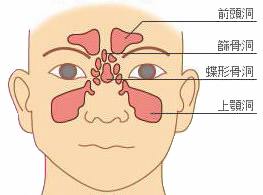
�� ���@�o�̂S�̎��
���̂S�̓��A���̒ɂ݂ɊW������̂��A��{���ł��B
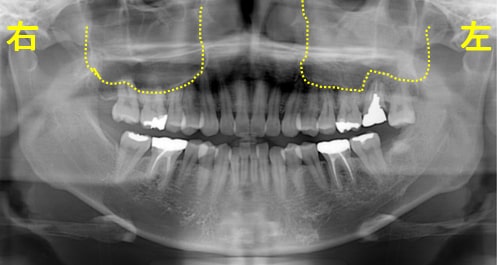
�� ��{���̃����g�Q���ʐ^
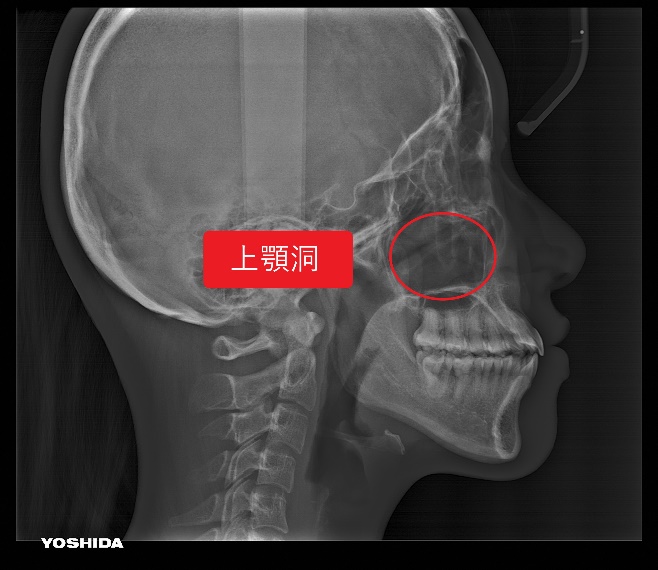
�� ���F�����ň͂܂ꂽ��������{��
���̏�{���ɉ��ǂ��N����ƁA���ɒɂ݂������Ċ����Ă��܂��̂ł��B
�Ȃ��Ȃ�A�����͏�{���ɔ��ɋ������߂��A���ɑ���P���͍������̐悪��{���ɓ˂��o�Ă��܂��B
�Ȃ̂ŁA��{���ɉ��ǂ��N����ƁA�����̍������̎h�����`���A�����ɂނ̂ł��B
��{���̉��ǂ͕��ׂ��Ђ�����A�ԕ��ǂȂǂŋN����܂����A�����̉��ǂ������ŏ�{���ɉ��ǂ��N�������Ƃ��悭����܂��i�����A�����a�A���������^�ނȂǁj�B
�y������{�����z�ƌ����܂��B��{���̉��ǂ̂P�O�`�R�O���������������ƌ����Ă��܂��B
��̓I�ȏǏ�
�P�F�������Ȃ��Ă������ɂ�
��{�������A���̍����q�̐��_�o���������Ď����������Ȃ��Ă��ɂ��i�����Ɂj���N����܂��B�����ɂ݂��o�܂��B
�Q�F�����Ɏ����ɂ�
��{�������A���̎���̎������Ɋg�����Ă��܂��A�����ɒɂ݂��o�܂��B �������Ƃ́A���̍����q�̎���ɂ����āA�������ƍ����Ȃ��N�b�V�����̂悤�ȑg�D�ł��B
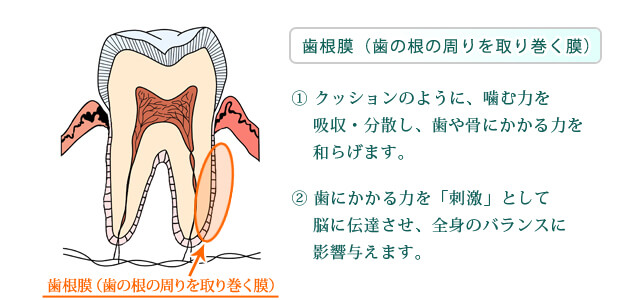
�R�F��������������������
��{�����̉��ǂ����̍��������������āA�����������悤�Ɋ����܂��B
��{�����i���@�o���j�ɂ�鎕�ɂ̓���
�P�F�O���ɂ͒ɂ݂��o���A�����ɏo��B
���R�́A�����͍������̐悪��{���ɔ��ɋ߂��̂ʼn��ǂ��g�y���₷������ł��B
�Q�F�����i�Q�`�R�{�j�̎��ɒɂ݂��o��
�����̒ɂ݂��ƁA���̎��P�{�����ɒɂ݂��o�܂����A��{�����̒ɂ݂̏ꍇ�́A��{���̋߂��ɍ����������鉜�����{�ɓn���Ēɂ݂��o��Ƃ�������������܂��B
�R�F���E�ǂ��炩�ɒɂ݂��o��
��{���͍��E�ɂ��邽�߁A�ǂ�������ǂ��N�����\���͓��R����܂����A�����ɋN���邱�Ƃ͏��Ȃ����߁A���̒ɂ݂����E�̂ǂ��炩�ɏo�邱�Ƃ������ł��B
��{�����i���@�o���j�������Ŏ����ɂ��̂��A���������Œɂ��̂���ʂ�����@
�P�F���ׂ��������Ď����ɂ��ꍇ�͏�{�����i���@�o���j�̉\��������
�� ���ׂƓ����ɒ������̒ɂ݂��o�邱�Ƃ����R����̂Œ��ӂ��K�v�B
�Q�F�₽�����̂�M�����̂����݂�ꍇ�͎��Ɍ���������\��������
�� ��{�����i���@�o���j�͎��̍����q���������Ēɂ݂��o��̂ŁA���݂��肷�邱�Ƃ͒ʏ�͂Ȃ��ł��B
�R�F�ɂ��������ł���ꍇ�́A���������̉\��������
�� ��{�����i���@�o���j�������̏ꍇ�́A�����{�ɓn���Ēɂނ��Ƃ������ł����A�������̒ɂ݂��ƁA�ɂ������r�I���肵�₷���ł��B
�����A���ۂɂ͂��̔��f�͓���A���Ȉ�@�Ń����g�Q���Ȃǂ̌��������āA�m���ɐf�f���Ă�����ĉ������ˁB
���ȗp�����g�Q���ł��A��{���̉��ǂ͂����킩��܂��B
�܂��A���Ȉ�@�Őf�f���āA���Ɉُ킪�����ƕ��������ꍇ�͎��@�Ȃ����Љ�邱�Ƃ�����܂��B
���Ö@
���������ŏ�{�����i���@�o���j�ɂȂ����ꍇ
���̏ꍇ���Q����������܂�
1. ���������̐_�o�܂Ői��ł��܂��A�_�o�������Ĕ^��ʼn��ǂ��N�����A��{���ɔg�y���Ă��܂��ꍇ
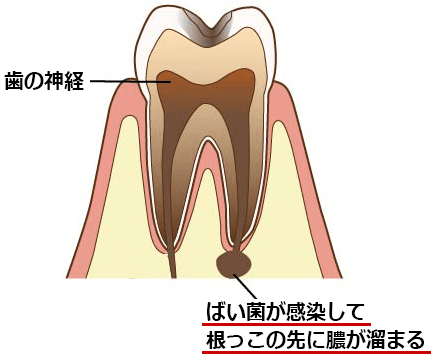
���̏ꍇ�̎��Ö@
���̍������̐�ɗ��܂����^���o������A�������̓�����|�����ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A���Ԃ��������܂��B
���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B
���R�́A
�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA
�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA
�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

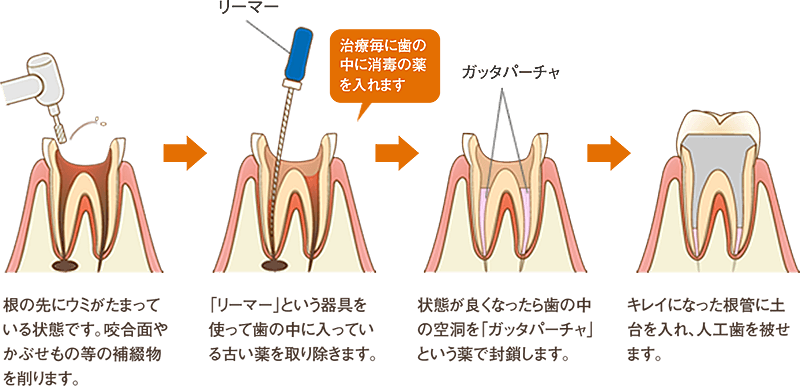
�Q. �����a�̂��ۂ��A���Ǝ������̊Ԃ̎����|�P�b�g�Ƃ����Ƃ�����A��{���ɍs���Ă��܂�����A�����a���i�s���Ď��̎���̍���n�����Ă����A�������̐�̍����n�����āA�������牊�ǂ���{���ɍs���Ă��܂��ꍇ
���̏ꍇ�̎��Ö@
�����a�ɂȂ�ƁA��{�����̖�肾���ł͂Ȃ��A���ۂɂ���Ď����������Ă�����A�o��������A�^���o����A���̎���̍���n�����Ď����O���O���ɂȂ��Ă��܂��܂��̂ŁA���}�����a�̎��Â�����K�v������܂��B

��{�����i���@�o���j�������Ŏ����ɂ��ꍇ
���ȂŎ����ڂ����f�f�������ʁA��{�����i���@�o���j�������Ŏ����ɂ��Ƃ킩�����ꍇ�́A���@�ȂŎ����K�v������܂��B
�����}�ɒɂ��Ȃ�����A�钆�ɒɂ��Ȃ����獢��܂���ˁI
����Ȏ��ɁA�����܂ނƒɂ݂��܂��ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
���̒ɂ݂͐F��Ȍ���������܂����A�����܂�Œɂ݂��܂��ɂȂ闝�R�ƁA�ǂ�ȏǏ�̎������킩��₷�����������܂��ˁB
�����܂�Œɂ݂��܂��ɂȂ闝�R
���ɒɂ݂����������ɁA�����ɐ����܂ނƁA���̐_�o�⎕�����ɒʂ��Ă錌�̗ʂ�����܂��B
���̒��ɂ͒ɂ݂����������鐬���i���ɕ����j������܂��̂ŁA���ꂪ���邱�Ƃɂ���Ēɂ݂��܂��ɂȂ�܂��B
�� ���ӓ_
�@ �X�ȂǗ₽��������̂Ŏ����}���ɗ�₷�ƁA�₽���̎h���ɂ���āA�������Đ_�o�ɒɂ݂������Ă��܂��܂��B
�A ��₷�̂ł���A�₽���^�I���Ŕ畆�̏ォ���₷���A��p�V�[�g�ŏ��X�ɗ�₷�悤�ɂ��Ă��������I
�B �t�ɁA�g�߂Ă��܂��ƁA���̗ʂ������A�ɂ݂����������鐬���i���ɕ����j�������Ă��܂��܂��̂ŁA�]�v�ɒɂ�ł��܂��܂��B
�Ǐ�P�F ����
�����������͓��R�ɂ݂܂������炢�ȏ�̒����ł́A�H�����ɒɂޒ��x����Y�L�Y�L�������ꍇ�܂ł���܂��B
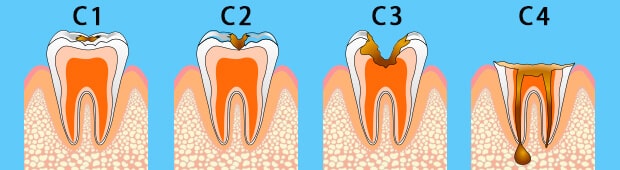
���������̐_�o�܂ōs���ƁA�_�o�������̂��ۂɂ���ċ������ǂ��N�����܂��B
�����āA���Ȃ苭���ɂ݁i�Y�L�Y�L�A�ǂ�����ǂ�����etc�j���o�Ă������܂��B
�����������ɁA�����ɐ����܂ނƒɂ݂������܂��ɂȂ�܂��B�����A���}���u�ł��̂ŁA���߂Ɏ��Ȉ�@�Őf�Ă�����Ă��������B
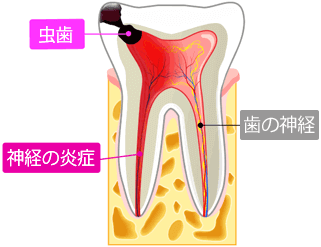
���Ö@
�����������炢�̏ꍇ
����������ĂƂ��Ă���A�������l�߂���A�^�������Ă���l�ߕ������܂��B
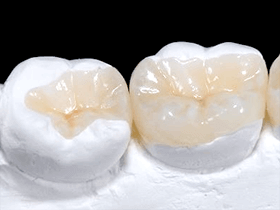
�������傫���ꍇ�i�_�o�܂œ͂��Ă�ꍇ�j
���̏ꍇ�́A���̐_�o����菜�����Â����Ȃ��Ƃ����܂���B�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����Ɏ��܂�܂��B
�ˁi���Ӂj�������A���̐_�o�͂Ȃ�ׂ����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͂Ȃ�ׂ��_�o���c���悤�w�͂����Ă��܂��B
��̓I�Ȏ��Ö@
�@�܂��A�ɂ�ł鎕�ɖ��������܂��B
���@�ł͖����͒ɂ��Ȃ��ł��܂��B�ɂ��Ȃ����R�͂������B
�A���������������������A����������Ď��A���̌㎕�̐_�o��j�̂悤�Ȋ����g���Ď��܂��B
������������������Ă�̂Œɂ݂͑S������܂���B
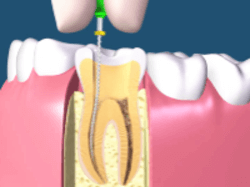
�B�_�o�����I�������A���̓����ɏ��ł̖�����āA�ӂ������ĂP��ڂ̎��Â͏I���ł��B
�C���̐_�o���������ɁA��U���ǂ��N���܂����A���ꂪ�P�`�Q�T�ԂŎ��܂�����_�o�̑���ɂȂ����l�߂܂��B

�������ʂ��Ă�̂��A�_�o�̑���ɂȂ��ł��B
���@�̖������ɂ��Ȃ����R
1�F�����̒��˂̐j���h�������ɂ݂��Ȃ���
���ƌ����Ă��A�j���h�����̒ɂ݂�h�����Ƃ��厖�ł��B
�����ɍׂ̐j���g���Ă���
�ːj�����ׂ��̂ŁA�����̒��Ɏh�������ɂ��킩��ɂ����B
���ɂ݂�������זE(�ɓ_)�̏��Ȃ��ӏ��ɍŏ��ɑł�
�˒ɓ_�����Ȃ��̂Œɂ݂ɂ����ł��B
���j���h���u�Ԃ́A�������̔S���ۂ̊v�̂悤�ɁA�s���ƒ����Đj����C�Ɏ������ɓ���悤�ɂ���B
�˂��̂悤�ɂ���Ɛj���h�������Ƃ��킩�炸�A���҂���ɂ́A�u�ŋ߂̖����͒��˂���Ȃ���ł����H�v�ƕ�����邱�Ƃ������ł��B

�Q�F������𒍓�����Ƃ����ɂ݂��Ȃ���

������͉t�̂Ȃ̂ʼn��x���Ⴂ�̂ł����A�������鎞�ɉ��x���Ⴂ�ƁA�̂��₽�������Ă��܂��Ɠ����ɒɂ������Ă��܂������ƂȂ�܂��B
���@�ł͂��炩�����������̉����炢�ɉ��߂Ē������܂��̂��A���җl�͋C�t����܂���̂ŁA�ɂ݂������܂���B
����ƁA�����ւ������̃X�s�[�h�����Ȃ������肵�Ă��܂��B�}���Œ�������ƁA���������Ă��܂��ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
���@�ł́A�P�H���P�b���炢�̂������Ƃ����X�s�[�h�ōs�����ŁA�����̑��ݎ��̂ɋC�t����܂���B
�Ǐ�Q�F �_�o������Ŕ^��ł�ꍇ
�����ۂ��_�o�܂œ͂��Ă��܂��āA�_�o�����ʂ��Ƃ��p�ɂɂ���܂��B�����āA���_�o�������Ĕ^��ł��܂��A�����ɂ݂��o���܂��B
�܂��A���łɐ_�o���������̍��������^��Œɂނ��Ƃ��p�ɂɂ���܂��B
����Ȏ����A�����ɐ����܂ނƒɂ݂������܂��ɂȂ�܂��B�����A���}���u�ł��̂ŁA�c�O�Ȃ��獪�{�I�Ɏ��邱�Ƃ͂���܂���̂ŁA���߂Ɏ��Ȉ�@�Őf�Ă�����Ă��������B
���Ö@
�܂��A�_�o�����������^��ł��闝�R���炲�������܂��B
�܂��_�o�̐����Ȗ��O�������i�������j�ƌ����܂��B
�����āA�����̒��ɂ͖{���ɐ_�o���ʂ��Ă邵�A���ǂ��ʂ��Ă܂��B
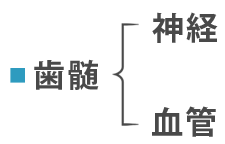
����ł��Ă��܂��B
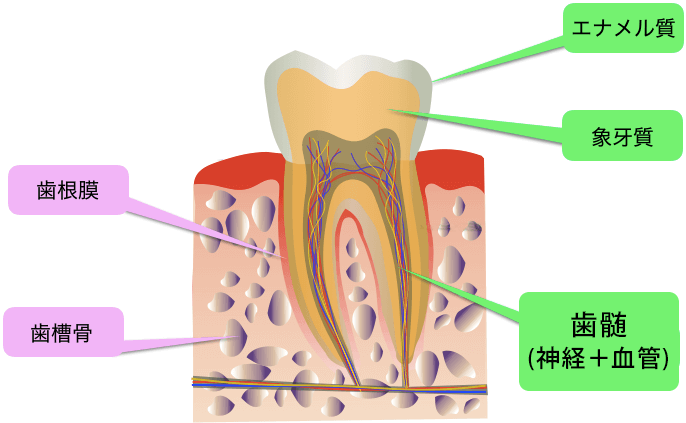
�ł��̂ŁA��������������Ƃ����̂́A���̒�����A�_�o�����łȂ����ǂ��Ȃ��Ȃ��Ă��ł��B
���ǂ̒��ɂ͔������Ȃǂ̖Ɖu�זE������A���ۂ�������Ă��܂��B
�Ƃ��낪�A�������Ă��܂��ƁA���̒�����Ɖu�זE�����Ȃ��Ȃ�A���̒��ɂ��ۂ������ė��Ă�������邱�Ƃ��ł����ɁA�������ĉ��ǂ��N�����Ă��܂���ł��B
��������Ď��̓����ɋN���������ǂ͍������̐���ۂ��獜�̒��ɐi��ōs���܂��B
�����āA���̍������̐���ۂɔ^�����܂��Ă��āA����A�@�����肵�����ɒɂ��̂ł��B
���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B
���R�́A
�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA
�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA
�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B
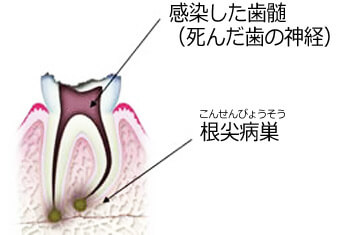

���Ö@
���̍������̐�ɗ��܂����^���o������A�������̓�����|�����ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B
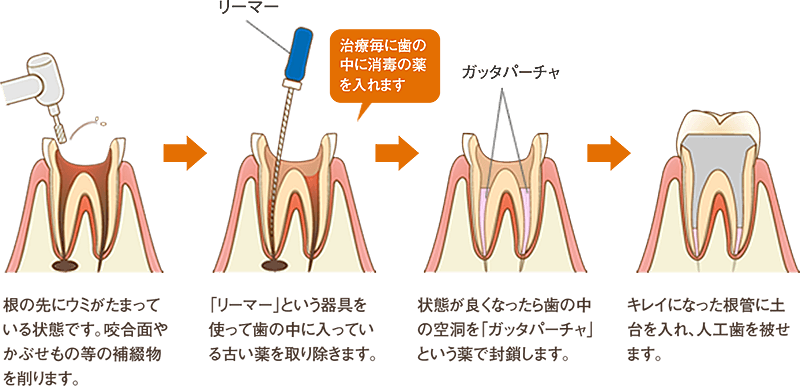
�Ǐ�R�F �����a�Ŏ��Ă�ꍇ
�����a�Ŏ����������Ēɂނ��Ƃ�����܂��B
����Ȏ����A�����ɐ����܂ނƒɂ݂������܂��ɂȂ�܂��B�����A���}���u�ł��̂ŁA���߂Ɏ��Ȉ�@�Őf�Ă�����Ă��������B

�� �����a�̏Ǐ�
���s�����Ȃ�������܂��A�Ԃ��Ȃ�A���u���V���y�����Ă������ł��o���������A���s�������Ɣ^���o�邱�Ƃ�����܂��B���L�����܂��B
�܂��A�����a�̂��ۂ������x���Ă鍜���n�������߁A�����O���O�����Ă��܂��B
�ɂ݂͏o�鎞���o�Ȃ���������܂��B�������̏Ǐ�����啪���������ł��B
�����a���L�̌��L�����鎞������܂��B
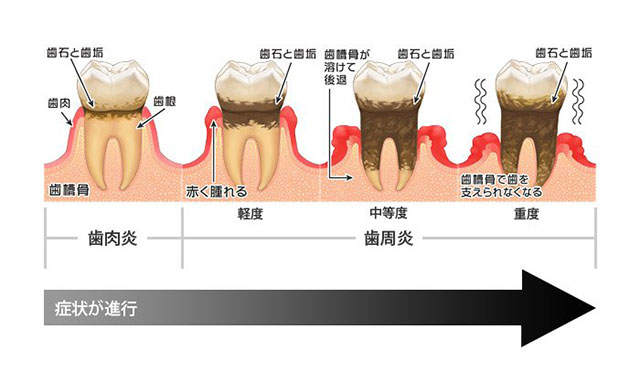
�� �����a�̌���
���������i�s���āA���Ǝ��s�̊ԁi�����|�P�b�g�j�ɂ�����ۂɂ���āA���s�ɋ������ǂ��N��������A����n�������肵�܂��B
���Ö@
���@�ł̎����a�̎��Õ��@
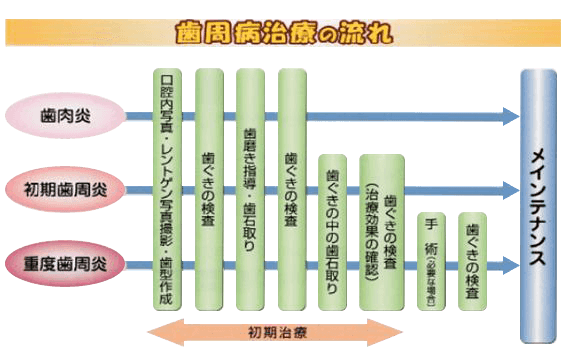
��܂��Ȏ��Â̗���
�����a���Âł܂��s���̂��A�������̌����i�����g�D�����j�ł��B
�����āA�������̎w���⎕�̏������s���܂��B���̌�A�Č������s���A�ǂ����Ă����P���݂��Ȃ��ꍇ�͎����O�Ȏ�p���s�����Ƃ�����܂��B
�ڂ������Â̓��e
�P. ���o���ʐ^�̎B�e�E�����g�Q���ʐ^�B�e�E���^�쐬
�ŏ��ɁA����̏�Ԃ̋L�^�Ƃ��āA�����̒��̎B�e���s���܂��B�����āA���̏�Ԃ�f�邽�߂ɁA�����g�Q���B�e�A�����Ă��ݍ��킹���m�F���邽�߂Ɏ��^�����܂��B

�Q. �������̌����i�P��ځj
���Ǝ������̊Ԃ̂����ԁi�����|�P�b�g�j�̑����A����������̏o���̒��x�A���̃O���O���̋�Ȃǂ��������܂��B
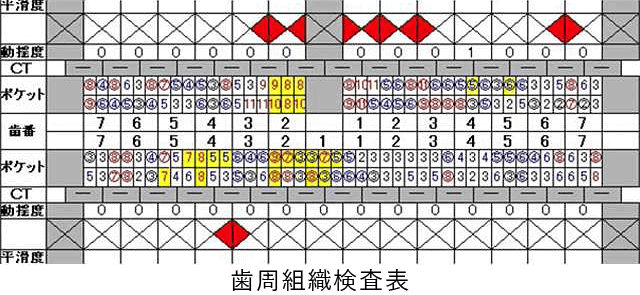
�R. �������w���E���Ύ��
�����f�[�^�[�͂��āA
�u�����a�̌���̂������v�Ɓu�����a���������߂̎������̕��@�̎w���v
���s���܂��B����͍��܂Ŏ����Ă����̂Ɏ����a�ɂȂ��Ă��܂����̂ł�����A���܂ł̎������ƈႤ���������K�v������ł��B
���ꂩ�玕�Ύ������܂��B�܂��́A���̕\�ʂ̎����L���C�Ɏ��A���A���C�̂Ȃ����ꂢ�Ȍ��o�������グ�āA���������������ȏ�Ԃ����܂��B
���̂��ƂŁA�������x�̎����a�͎���܂��B

�S. �������̌����i�Q��ځj
���̕\�ʂ̎����Ȃ��Ȃ�A���݂����������ɂȂ�����Ԃł�����x�A�����a�̏Ǐ�͊ɘa����܂����A�����x�ȏ�̎����a�͂��ꂾ���ł͎���܂���B
�����ŁA�Ăю������̌��������܂��B
�T. �������̒��̎��Ύ��
�Q��ڂ̌����̌��ʁA���P���݂Ƃ߂��Ȃ��ӏ��ɂ��܂��ẮA�X�ɒ��J�Ȏ������̒��̎��̍��̕\�ʂɂ��т�����������(SRP)�K�v������܂��B
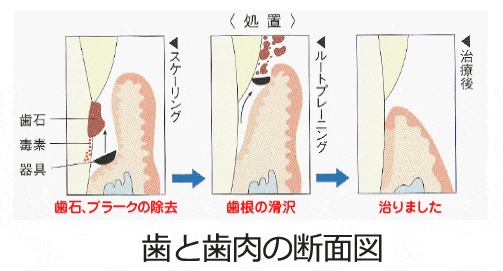
�U. �������̌����i���Ì��ʂ̊m�F�j
�������̒��̎�������āi�r�q�o�j���ƁA�����a�͑傫�����P���Ă��܂��B���̏��u�Œ����x�̎����a�͎��邱�Ƃ����ɑ����ł��B�����Ă���A�������烁���e�i���X�ɂȂ�܂��B
�V. ��p�i�K�v�ȏꍇ�̂݁j
�������̒��̎��Ύ��i�r�q�o�j�ł��A�����a������Ȃ��ꍇ�́A�������̎�p�����܂��B�i�t���b�v��p�ƌ����܂��j
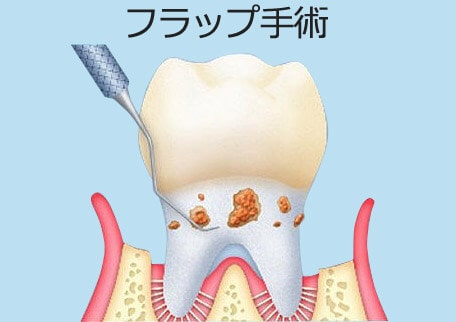
���̃t���b�v��p�́A��������؊J���Ă��玕�����A���̍������ɕt���������������A�����������ɖ߂��ĖD�����킹�܂��B
�ŋ߂ł́A�t���b�v��p�ƍ��킹�Ď����g�D�Đ����Â��s���P�[�X������܂��B
�l�H�̓���Ȗ��uGTR���v�����ȃ^���p�N�����g���āA�����x���鍜�Ȃǂ̑g�D���Đ����鎡�Âł��B
�����A�������̏�Ԃɂ���ẮA�s���Ȃ��ꍇ������̂ŁA��]����ꍇ�͒S����ɂ����k���������B
�W. �����e�i���X
���݂����ł͎��Ȃ���������ȉq���m���O��N���[�j���O���Ă����܂��B
�܂��Ǝ��Ȃł͎����a�̃����e�i���X���ÂƂ��āAPMTC�ƁA�G�A�t���[���g�p�����p�E�_�[�ɂ��o�C�I�t�B�����̏������s���Ă��܂��B
�� �����e�i���X(������f)�ɂ��������ɂ��Ȃ��āA�����p�܂Ŏ��Ēɂނ��Ƃ�����܂��B
�����p�܂ʼn��ǂ��y�Ԃ̂͏Ǐ��Ȃ肫���ꍇ�ł����A����������������܂��B
���̍ő�̌������u���������v�ƌ����܂��B

���̎���ɂ́A�������ƌ����āA���ƍ��̊Ԃ̃N�b�V�����̂悤�Ȗ�������A������������ƌĂ�ł܂��B
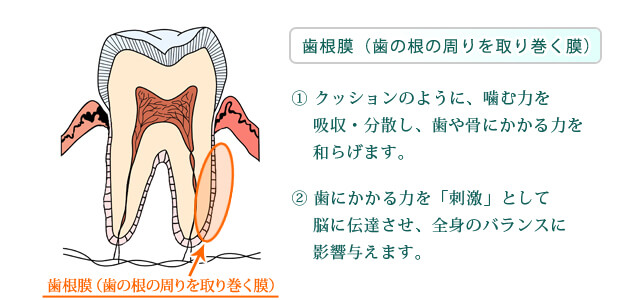
���̎������ɉ��ǂ��N�������̂����������ł��I
�����������N�����ĂЂǂ��ꍇ�́A�����p�܂Œɂނ̂ł��I
�@�����ۂ��A���̐_�o�Ɋ������A�_�o���玕�̍������̐��ʂ��āA�������܂Ŋ������邱�Ƃɂ���ċN����܂��B�i���������������j�唼�����̏ꍇ�ł��B
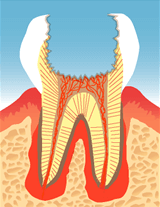
�A���������ł�����A�����Ď����Ԃ���ȂǁA���ɋ����O�͂�������Ă��N����܂��B
�i�������������j���̏ꍇ�́A�����p�܂Œɂނ��Ƃ͏��Ȃ��ł��B

�����̏����Ƃ��A���x���y���ꍇ�́A���������������Ƃ��A����@�����肷��ƒɂ����x�ł��B
�������i�ނƁA�A�S�̉��̃����p�܂ʼn��ǂ��y��ł��܂��A��ꂽ��ɂ����܂��B
����������Ԃ���u���Ă����ƁA�M���o���蓪�ɂ�������A���̍����q�̐�ɂ�������^�����܂��Ă��܂��A�傫�ȕa�������܂��B
�����āA���̕a���������ŁA�S�g�ɕa�C���L�߂Ă��܂��܂��B�S���A�t���A�ߓ��ɂ����ǂ��N�������Ƃ�����܂��B

���������̎��Ö@
�����ۂ����̐_�o�Ɋ������Ă邱�Ƃ������̂ŁA�܂��͂��̎��Â��s���܂��B
�����������̐_�o���������āA�����L���C�ɐ�Ă��ۂ�O��I�ɏ������܂��B
���̍����q�̐�ɔ^�����܂��Ă邱�Ƃ����ɑ����̂ŁA�^����������o���܂��B
���̌�A���̐_�o���ӂ�������l�߂Ă���A���Ԃ��������܂��B
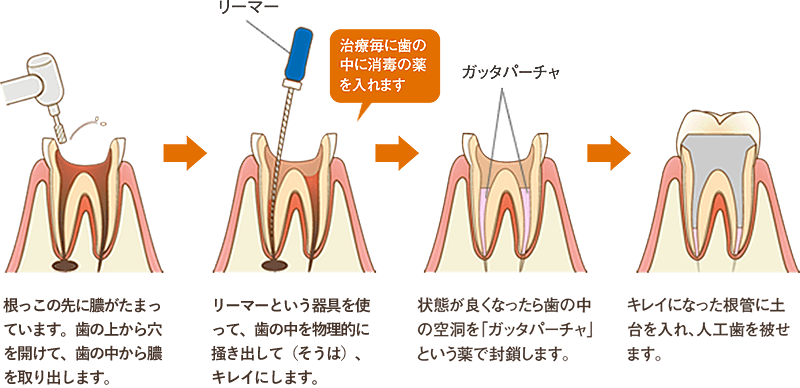
���������́A�ق��Ă������ꍇ�A���̎���̍���n��������A�S�g�ɂ��ۂ��L�����肵�܂��B
�Ƃ��낪�A�ꎞ�I�ɉ��ǂ����܂��Ēɂ݂����邱�Ƃ�����܂����A���R�Ɏ��邱�Ƃ͎c�O�Ȃ��炠��܂���̂ŁA���Ȉ�@�Ŋm���Ɏ��Â���Ă��������ˁB

�X�N���̕��Ŏ����ɂނ��Ƃ͂悭����܂��B�����ɂ͒ɂ݂₷���Ȃ�ƌ����Ă������ł��B
��ɂ͏����z�������i�G�X�g���Q���j�̒ቺ�ɂ��z�������o�����X�̗���ɂ����̂ł��B
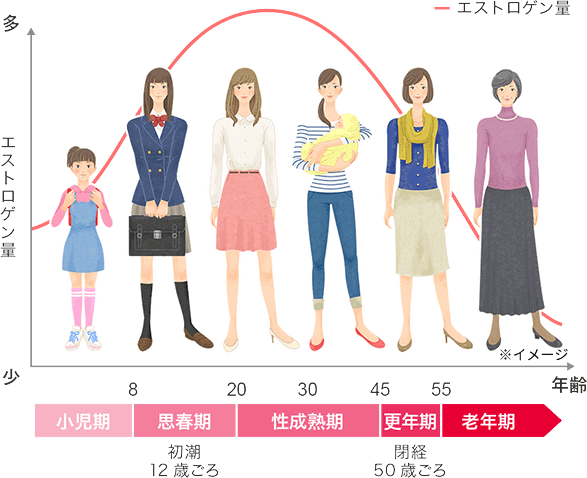
�����z�������i�G�X�g���Q���j�́A�u�����炵���v�̑匳�̃z�������ł��B
�����炵���g�̂̃��C�����������A���[�B��������A���̗ʂ��ӂ₵����A�g�̂ɂ��邨���������炵���肵�Ă��܂��B
����ȃz������������킯�ł�����A�����̒��ɂ��F��ȏǏN����̂ł��B

��ԑ����Ǐ�́A�G�X�g���Q���̌����ɂ�鍜���x�̒ቺ�i�������傤���j�������݁A����j�Ă��܂��A�����a�i�X�N�������a�j�ɂȂ邱�Ƃł��B
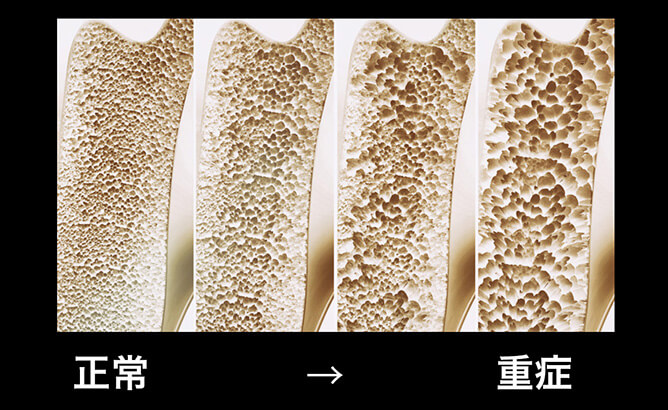
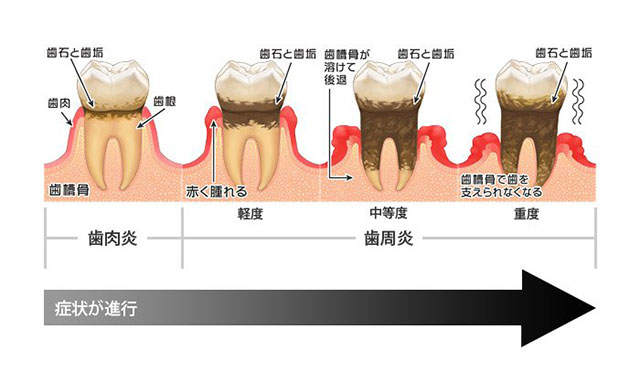
�� �����x��������ƁA�����a���i�s���₷���Ȃ�܂�
�i��{�I�Ɏ����a�͓��v�I�ɂ͒j����菗���̕��������늳���Ă��܂��܂��B�j
�܂��A����
�܂��A�z�������̒ቺ�ɂ���ĐS�g�Ƃ��ɃX�g���X�����܂�₷���Ȃ�܂����A���̉e���͂����̒��ɂ��o�܂��B
���t�̗ʂ������Ă����̒��������h���C�}�E�X�A����ɔ������L�A�オ�Ђ�Ђ肷����ɏ��A���o���ω��������o�ُ��Ȃǂ��N���蓾�܂��B
���t������������ɂ��Ȃ�₷���Ȃ�܂��B�i���t�̒��ɒ����ۂ��������Ɖu�זE�����邩��ł��j
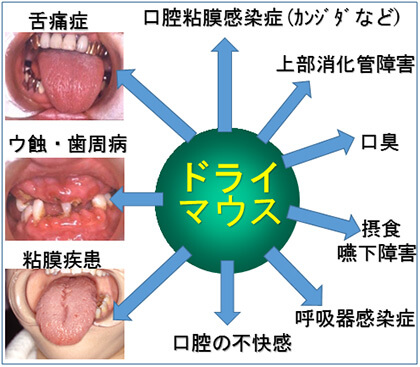
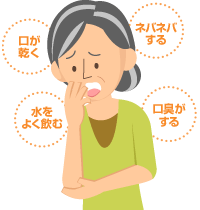
�����a�⒎���̏ꍇ�́A�X�N���̕��ɓK�Ȑf�f���ł��鎕�Ȉ�t�̌��Ŏ��Â���Α��v�ł��̂ł����S���������B
�܂��A�X�N���̕��̏ꍇ�A������������Ȃ��Ď����ɂޏꍇ����������܂��B
�ڂ������������܂��B
���̒ɂ݂��u�������Ɂi�Ђ����������j�v�ƌ����܂��I
�X�N���̕��ɑ����Ƃ���Ă��܂��B�܂��A���Ǝ��ȊO�̗����Ɍ�����������������܂��B
���Ȉ�@�ɂ���ẮA�f�f������Ă��܂��A������������Ȃ��̂ɁA�����������A�_�o���������A�ň����������邱�Ƃ�����܂��B
�������茴�������ɂ߂�\�͂̂��鎕�Ȉ�@��I�Ԃ��Ƃ����ɑ�ł��B
�ˑ傫��8�̌������l�����܂�
�� �W�̂ǂ�ɂ����Ă͂܂�Ȃ����͂�����
�����P�F �֘A��
�ɂ݂�������ƁA���̒ɂ݂͔]�ɓ`�����܂��B
�����āA�_�o�Ɛ_�o���ߐڂ��Ă�ꍇ�ł��ƁA���������ł͂Ȃ��̂ɁA���Ⴂ���N�����Ă��܂��A�����ɂ��悤�Ɋ�����̂ł��B�]�Ɛ_�o���֘A����ɂ��Ƃ������܂��B

�����Q�F �ؓ��̒ɂ�
���ނ��߂̋ؓ������ǂ��N�����Ēɂ݂��o��ƁA�����ɂ��Ȃ��Ĕ����ė~�����Ƃ������Ŏ��Ȉ�@�ɗ�����������܂��B
���������g�Q���⎋�f�A�G�f���ł�����Ă��˂��ɐf�@���Ă����Ɉُ킪�����Ȃ��̂ɁA���҂����̒ɂ݂��^���ꍇ�́A���̋ؓ��̒ɂ݂��l�����܂��B
���p��ŁA�u�E�ؖ������Ɂv�ƌ����܂��B
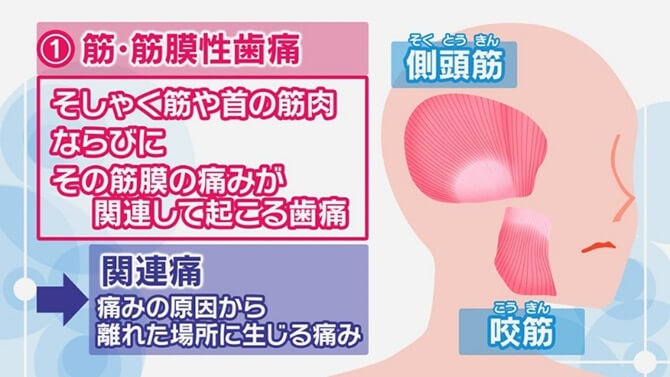
���ÂƂ��ẮA���������߂���A�}�b�T�[�W��������A�X�g���X�����炵����A�p���������Ȃǂ̐����K���̉��P��ڎw�����ƂɂȂ�܂��B
�����R�F �_�o���̂��̂���Q����Ă�ꍇ
1�̊֘A�ɂł́A���ȊO�̏ꏊ���ɂ��̂Ɏ����ɂ������܂������A�ɂ݂�`����_�o���̂��̂���Q�������ʁA�����ɂނ悤�Ɋ�����Ƃ����a�C�ł��B
�u�_�o��Q���u�Ɂv�ƌ����܂��B
���̓��A�ł������̂��u�O���_�o�Ɂv�ł��B�O���_�o�́A��A�S�≺�A�S�̐_�o�Ƀ_�C���N�g�ɂȂ����Ă��܂��̂ŁA���������ǂɈ��������ȂǏ�Q����Ǝ��Ɍ������ɂ݂��N�����܂��B
�ɂ��Ċ��Ȃ��A�Ђ����肪�ł��Ȃ��Ȃǂ̏Ǐo�܂��B
���Ö@�Ƃ��ẮA�Ö@��_�o�u���b�N�Ȃǂ̕��@������܂����A���o�O�Ȃ�]�_�o�O�ȓ��֏Љ�邱�Ƃ������ł��B
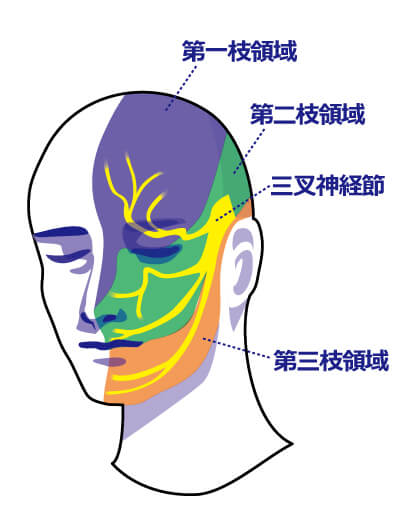
�����S�F ����
���ɂ̒��ł��Q�����ɂƌĂ�铪�ɂ�����܂��B
�Q�����ɂ͂P���ɉ��x���P���Ԃ��炢�N���܂��B���̓��ɂ͓��Ɏ��ɂƊԈႦ���₷���A�ԈႦ����m���͂P�P��������܂��B�ԈႦ����ƁA������Ă��܂�����A���̐_�o������Ă��܂����肵�܂��B
�Ȃ̂ŁA�T�d�Ȑf�f���K�v�ɂȂ�܂��B
���Ö@�́A�]�_�o�O�ȂɏЉ�邱�ƂɂȂ�܂��B

�����T�F ��{���ɉ��ǂ�����ꍇ
��{���́A���W���̒��̕@�̉��ɂ���ł��B���������ׂȂǂʼn��ǂ��N�����ƁA�������ɂނ��Ƃ�����܂��B������A��{�������ɂƌ����܂��B
���̏ꍇ�A�ʏ�͍��E�̕Е��̉������ɂ݂܂��B
���Ö@�́A��������������f�f���Č��ɂ߂āA��{�����̎��Â����邱�ƂɂȂ�܂��B
���Ȉ�@�����Ŏ���Ȃ��ꍇ�́A���@�Ȃɂ���`���Ă��炤���ƂɂȂ�܂��B
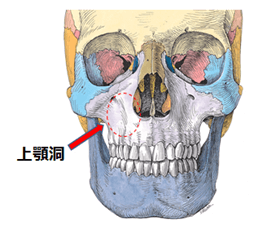
�����U�F �S���ɕa�C������ꍇ
�S�؍[�ǂ�A���S�ǁA�S�������Ȃǂ�����ꍇ�A���ɒɂ݂��y�ڂ����Ƃ�����܂��B
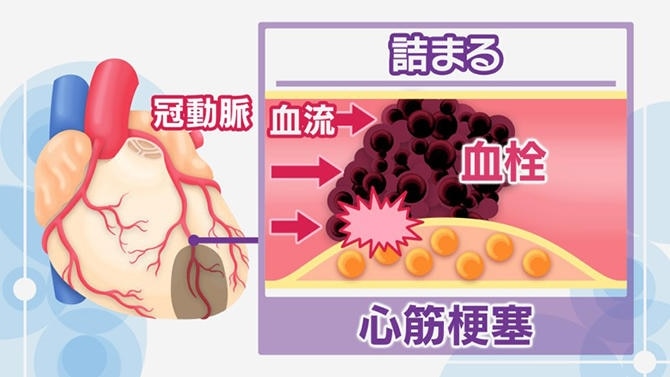
�����V�F �_�o���ǐ�����
���ɁA���ɕГ��ɂ̎��ɋN���鎕���ɂ��Ɗ����錻�ۂł��B
�������Ƃ����A���̐_�o�̉��ǂƒɂ݂����Ă邽�߁A���ʂ�����ł��B
�����W�F ���_�I�Ȃ��Ƃ�Љ�S���I�Ȃ��Ƃ������̏ꍇ
�s����X�g���X����������A���ɂȂ�����A���������ǂȂǂ̐��_�I�Ȏ��������Ŏ��ɒɂ݂��o�邱�Ƃ�����܂��B
���̗l�ɁA�����ɂ������͂�������܂��B
�K�Ȑf�f�����Ȉ�@�ŎāA�m���Ɏ������Ƃ��A���̎����̉����ɂȂ���܂��B
���߂Ɏ��Ȉ�@�Őf�Ă�����Ă��������ˁB
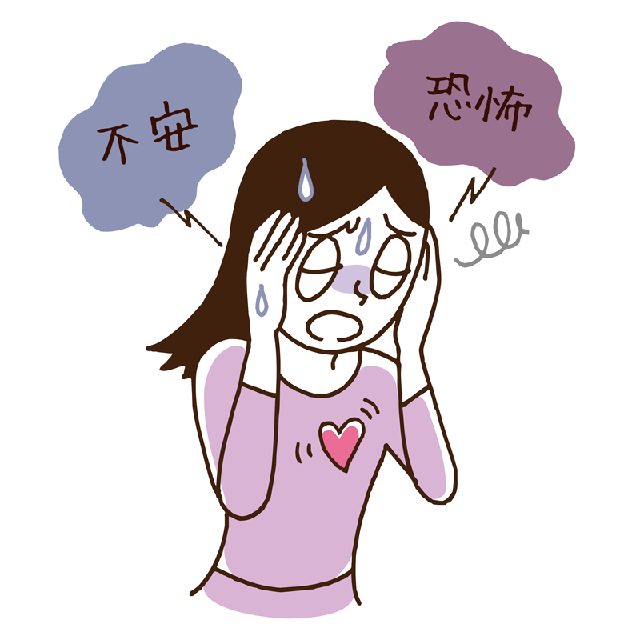
�����O�Ɏ����ɂނ��Ƃ͂悭����܂��B�����͏����z�������̃o�����X�̕ω��ɂ����̂ł��B

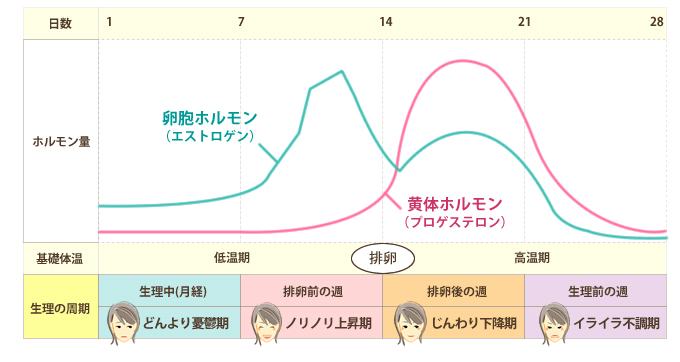
�������߂Â��������z�������̃A���o�����X���N���Ă��܂��B�G�X�g���Q���i���E�z�������j�ƃv���Q�X�g�����i���̃z�������j�̃A���o�����X�ł��B
�������I���������́A�G�X�g���Q���̕��������̂ł����A���̐������߂Â��ƃv���Q�X�g�����̕��������Ȃ��ăo�����X���t�]���āA�g�̂ɐF��ȕω����o�Ă��܂��B
��́A�����̂P�O���O�キ�炢�O���猑�ӊ��A�C���C���A�J���A���ɁA���ɁA�������ɁA�H�~�s�U�ȂǐF��ȕω����łĂ��܂��B�i���o�O�nj�QPMS�ƌ����܂��j
�����͐����O�ɂȂ�ƁA�q�{�����k�����Ďq�{�̒��̌��t��r�o�����u�v���X�^�O�����W���v�Ƃ����������������傳��܂��B
���̕������ɂ݂�U�����镨���ł��āA�������ɂ͂������A���ɂ��N�����܂��B�Ȃ̂ŁA���i�͒ɂ܂Ȃ��悤�ȏ����Ȓ����ł��ɂ肵�܂��B

�����O�ɋN����F��ȏǏ�̌��ʁA�X�g���X�A��J�A�����s���ȂǂɂȂ�A���̂��Ƃɂ�����Ɖu�͂������A�����̂��ۂł������������邱�Ƃ�����܂��B
�܂������z���������A�����|�P�b�g�Ƃ������Ǝ������̊Ԃ̂����Ԃ̖э��ǂ��炽�����傳��邱�ƂŁA�����z���������G�T�ɂ��Ă鎕���a�ۂ����������Ă��܂����Ƃ������ł��I
�i���ꂪ�����ŁA�����̕����j�����A�����a�ɂȂ�₷���̂ł��j

���Ö@
�����̐����O�̏Ǐ�͑S�Ă������̂����ł͂���܂���B�����ł����Ɉُ킪�������ꍇ�ɁA�����O�ɔ������邱�Ƃ��悭����܂��B�i�������A�������I������玡��ꍇ������܂��j
�����O�͕��i�ɂ܂Ȃ��悤�ȏ������������ɂނ��Ƃ�����܂��B�܂��A�����������͂������A���Ǝ��̊Ԃ̒����͔���������̂ŁA���Ȉ�@�Ŋm�F���Ă�����ĉ������B
�܂��A����������ꂽ�ꍇ�́A���⎕�C������Ă��炢�A�K�Ȏ������w�����Ă��������B
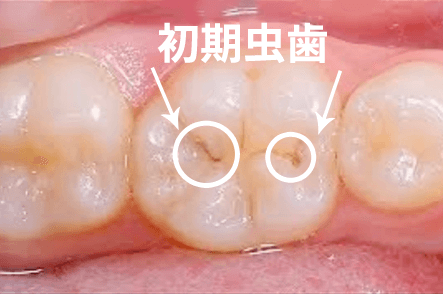
�ɂ݂��o�Ă��玕�Ȉ�@�ɍs�����Ƃ��A���i���玕�Ȉ�@�ɒ�����f�ōs���āA�m���Ɏ��C�⎕���Ƃ��Ă��炢�A�����N�������̒����L���C�ɂ��Ă��邱�Ƃ��ł��厖�ł��B
���Ƃɂ���āA�����O�̒ɂ݂��o�ɂ����Ȃ�܂��B�܂��A�������������������ꍇ�����߂ɔ����ł��Ď������Ƃ��ł��܂��B���ɁA�����������͂��܂莕����炸�ɊȒP�Ɏ�����̂Ŏ��ɂ��D�����Ƃ��������b�g������܂��B
����Ɏ������̎d�����`�F�b�N���Ă����̂Œ����ɂ��Ȃ�ɂ����Ȃ�܂��B

���i����A������ł̎������J�ɂ������ƂŁA�����̒�����ɐ����ɕۂ��Ƃ��厖�ł��B
�����O�ŁA�Ɖu�͂������Ă���A�����a�ۂ̃G�T�ɂȂ�z�������������������̒��ɕ��傳��Ă��Ƃ��Ă��A����������������ł��Ă���A�����������ǂ��N�����ɂ����Ȃ�܂��I
�܂��A�����a����������ɐi�s����̂ŁA�Q��O�̎������͓��ɔO����ɂ��Ă��������B

�����O�ɖƉu�͂������邱�Ƃ������̂ł����A���̎����ɁA�����l�߂Ďd����������A���������肵�āA�������Ԃ���������A�H���������Ǝ��Ȃ������肷��ƁA�]�v�ɖƉu�������Ă��܂��A���̒ɂ݂��o�₷���Ȃ�܂��B
���H���́A�r�^�~���𑽂��܂ޖ����������H�ׂ邱�ƂƁA���������߂��Ȃ����ƁA�܂��A�ߓx�Ȉ�����i���͂Ȃ�ׂ������Ă��������ˁB
�����O��PMS�i���o�O�nj�Q�j�́A��ςł͂���܂����A�Ȃ�Ƃ��Ώ����Ă��������ł��ˁB

�����ɂ��āA�ق��܂Ŏ�ꂽ���ςł���ˁI
�����ł́A���̌����ƑΏ��@�ɂ��Ă��������܂��B �P�Ɏ����ɂ������ł́A�ق��܂ł͎��Ȃ��ł��B
�ق��܂Ŏ���̂͏d�ǂ̏ꍇ�ł��B

�@�����������ŁA���̐_�o������ł������Ă��܂��ƁA�������̐�ɔ^�����܂��Ă��܂��B
���ʂ́A���̔^�͖��ɕ�܂�Ă���̂ŁA�������̐悾��������i����a���j���Ƃ͂����Ă��A�ق��܂Ŏ��邱�Ƃ͂���܂���B
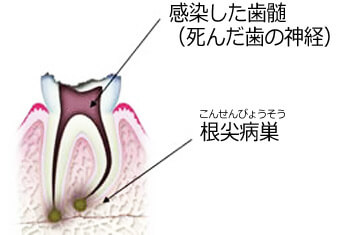
�Ƃ��낪�A���̔^���A���̎���̋ؓ���A�������̌����g�D�̑a�ȏ���ʂ��āA�ق���A�S�̉��ȂǂɍL���邱�Ƃ�����܂��B�����Ȃ�ƁA�ق��܂Ŏ���킯�ł��B
���̂悤�ɁA�^��������炸�ɁA�L�͈͂ɍL�����Ă������ǂ��A�I�|�D���i�ق�����������j�ƌ����܂��B

�A�����a�������ŗ��܂����^�ł��Ȃ�܂��B
�Ђǂ��ꍇ�́A���┭�ԁA�ɂ݂����łȂ��A�M���o����A���ӊ��⓪�ɂȂ��S�g�I�ȏǏ����o�Ă��܂��B
����ɂЂǂ��ꍇ�́A��A�S�̎��������̏ꍇ�́A���ǂ��]��ڂɋy�Ԏ�������A���A�S�̎��������̏ꍇ�́A���ʂ��Ĕx�܂ōs�����Ƃ�����܂��B�i�c�s���j
�^����ďo�����Â����Ȃ���A�R�������i���^�~�߁j������Ŏ����܂��B�R�������̓_�H�����邱�Ƃ�����܂��B
�����̎��̎��ẤA�܂��́A�R�������Ŏ����������Ă���s���ꍇ�ƁA�����ɍs���ꍇ������܂��B
���̐_�o������ł������Ă�ꍇ����ԑ����̂ŁA���̎��͍������̎��Â��s���܂��B

���Ö@
���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B
���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B
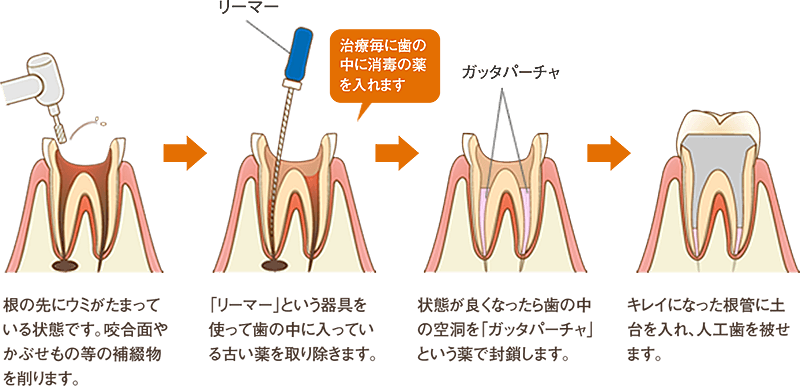
�������̎��ɁA���u���V�����ɓ������Ēɂ����Ƃ�����܂���ˁI
������u�m�o�ߕq�v�ƌ����܂��B
���̍����������茸���ĂāA�����Ɏ��u���V��������ƒɂނ̂ł��B
���Ö@���܂߂Ă킩��₷�����������܂��B
�₽�������P���ɂ��݂邱�Ƃ��u�m�o�ߕq�v�ƌ����܂��B
�_�o�ɉ��ǂ���������A����������킯�ł͂Ȃ��A�P�ɗ₽�����̂╗������������A���u���V��������Ƃ��݂��肷��Ǐ�ł��B
���̍����������茸�����A�����Ɏh���������ƋN����܂��B
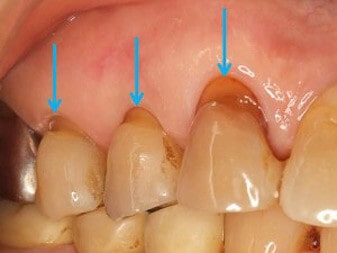
���̍����������茸�錴���͑傫��3����܂��B
���̍����������茸�錴���P�F
�����͂ł̃u���b�V���O
���̍����������茸�錴���Q�F
��������E�H������
���̍����������茸�錴���R�F
�����a�Ŏ��������������Ď��̍��������I�o����
���̓G�i�������Ƃ����d���w�ŕ����Ă��܂����A���̍������̓G�i���������_�炩���Z�����g���ɕ����Ă��܂��B
�����a�⋭���͂Ńu���b�V���O���s���ƁA���s�̈ʒu��������A�{�����s�ŕ����Ă��������Z�����g�����I�o���Ă��܂��܂��B
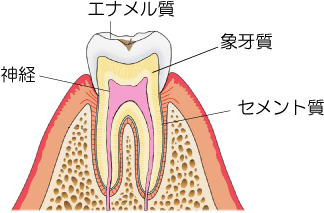
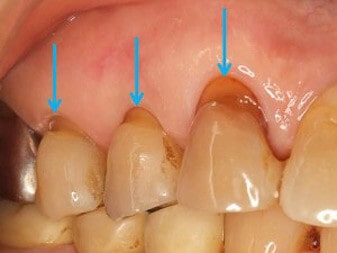
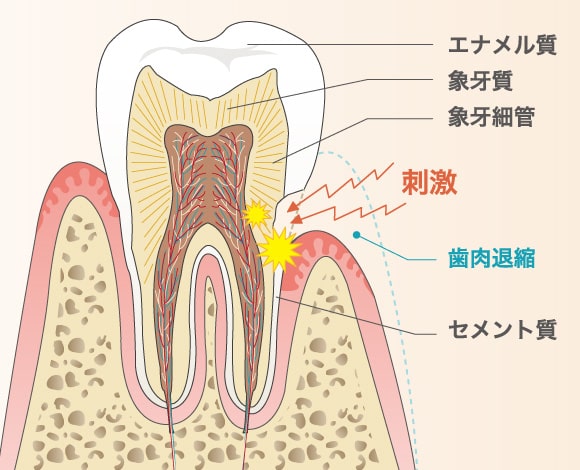
���̃Z�����g���͎��u���V�Ȃǂ��������������ƒP���ɃZ�����g�������茸���āA�ʐ^�̂悤�Ȏ��Ǝ��s�̊Ԃ����ڂ悤�ȏ�ԁi�����я��j�ɂȂ�܂��B
���̌��ʁA���̓����̏ۉ县�ɂ���ۉ�ǂƂ����_�o�ɂȂ���ׂ��������I�o���Ă��܂��A���̖����̌�����_�o�֎h�����`��邱�Ƃɂ���Ēm�o�ߕq���N����܂��B
�������������̕��@���s��Ȃ��ƏǏ������܂��B���@�ł͒��J�Ɏ������̎d�������������܂��B

���������H�����������ƁA�G�i���������_�炩���Z�����g���Ɏ�������̗͂��W�����邱�Ƃɂ��A�Z�����g�������茸���Ă��܂��܂��B
���̏ꍇ�́A�l�߂�Ƃ��������Âňꎞ�I�ɉ��P����܂����A���{�I�Ȍ��������P����Ȃ��ƁA�m�o�ߕq�̏Ǐ���Ĕ����Ă��܂��܂��B
���ׁ̈A���s���Ď��������H������̎��Ái�i�C�g�K�[�h�̍쐻�j���s�Ȃ��Ă������Ƃ����X����܂��B

���Ö@
�� �l�߂���@�F���茸���Ă���Ƃ���Ɏ������l�߂�Ȃǂ��Ď����܂��B

�� �R�[�e�B���O�F��p�̃R�[�e�B���O�܂����茸���������ɓh���āA�I�o�����ۉ县�ɉ����O������̎h����}���܂��B

�� �����̏����F���������̌������������߂ɁA���݂����w���A��������h�~���u�̃i�C�g�K�[�h�i�}�E�X�s�[�X�j���g���܂��B
�����a�ɂ�����ƁA�����a�ۂɂ�莕���x���鎕�������n������A�����ɂ��̏�ɂ��鎕��������ނ��A���̍����̏ۉ县���I�o���܂��B

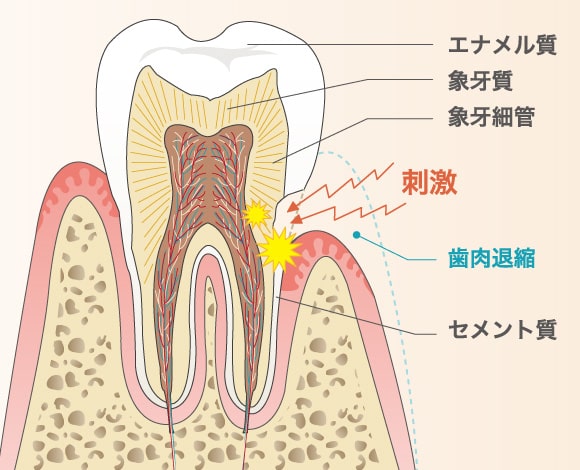
��������h�����_�o�ɓ`����Ă��݂邱�Ƃ�����܂��B���̏ꍇ�͎��C�A���̏����⎕�݂����w���Ȃǂ̎����a���Â����ĉ��P���Ă����܂��B
������菜�����ƂŁA�������Ƃ��Ƃ������Ă������̏ۉ县�̘I�o�������Ĉꎞ�I�ɒm�o�ߕq�̏Ǐ����Ă��܂����Ƃ�����܂����A���t�Ɋ܂܂��ĐΊD�������ɂ��A�ۉ�ǂ��ӂ�����A���X�ɉ��P����܂��B
���{�I�ȉ������ł��Ă��Ȃ��ƏǏi��ł��܂�������������܂ꂽ��A���������Ă��܂��Ƃ����[���ȏ�ԂɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����܂��̂ő��߂ɂ����k���������ˁB
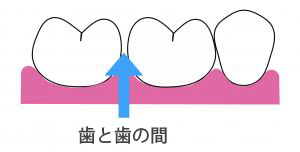
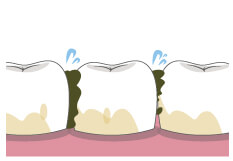
���Ǝ��̊Ԃ��ɂ����Ƃ��Ă���܂���ˁI
���̂�H�ׂ鎞�Ɍ��\�ɂ�������A���������ɂ����Ƃ��ĂĂ��ɂނ��Ƃ�����܂��B
����ɂ́A����������������܂����A�ő�̌����́A���Ǝ��̊Ԃɂ����Ԃ��ł��ĕ�����(�͂�)�܂��āA�����������������N�������ꍇ�ł��B
�������͖��O�̒ʂ�A�������̉��ǂł����A�����ɂ��Ɗ����Ă��܂��܂��I
���������Ă��܂��Ă����Ԃ��J�����Ƃ��悭����܂��B �������������Ƃ��ẮA������������u���Ă��ꍇ�ɁA���������̑O��̎����x���������Ȃ��ē����Ă��܂����Ƃł��B
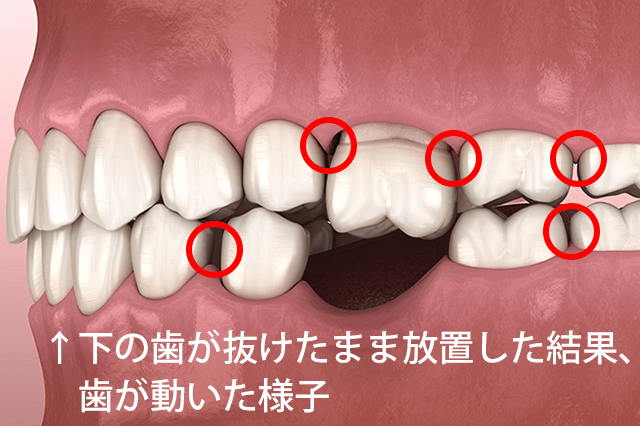


���Ǝ��̊Ԃɒ����ł����Ԃ��ł���ƁA�����l�܂��Ď������ɂȂ�܂��B
�������͖��O�̒ʂ�A�������̉��ǂł����A�����ɂ��Ɗ����Ă��܂��܂��I
�����a�ɂȂ�ƁA�����x���Ă鍜���n���܂��̂ŁA���������Ă����Ԃ��ł�����A���������������Ă��܂��Ď��Ǝ��̊Ԃɂ����Ԃ��ł��邱�Ƃ��悭����܂��B
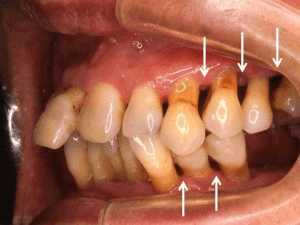
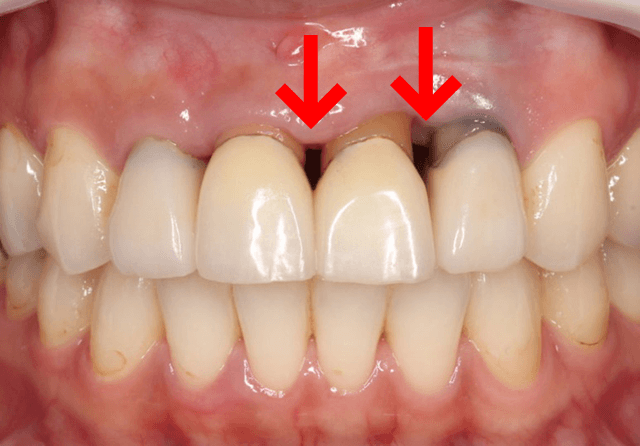
���Ȏ��ÂŁA�l�ߕ��₩�Ԃ������������ɁA�ׂ̎��Ƃ̐ڐG����邭�āA�����Ԃ��J���Ă��܂����Ƃ�����܂��B
����́A�c�O�Ȃ��玕�Ȉ�t�̎��Â��K�łȂ��������߂ł��B

�P�F������������u���Ď����������ꍇ�̎��Ö@
�P. �܂��́A�����Ăł����X�y�[�X�߂܂��B
�Q. ���̎��ɁA���̑��̂����Ԃ߂܂��B
�R. �Ⴂ�����ƁA�������Â����Ď������Ă����Ԃ߂邱�Ƃ������ł��B
���߂���@�́A���ʂ̓u���b�W���C���v�����g�ł��B
���u���b�W
���������̗��T�C�h�̎�������Ă���A���n���̎���킹�܂��B

���C���v�����g
�����������ӏ��̃A�S�̍��̒��ɁA�l�H�̎��ߍ��݂܂��B

�����Ԃ߂�ɂ́A�傫���Q���@������܂��B
���l�ߕ�������
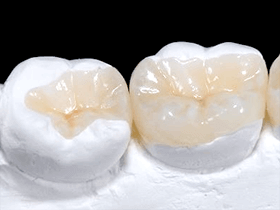

�����Ԃ���������




�Q�F���Ǝ��̊Ԃɒ������ł��Ă����Ԃ��ł����ꍇ�̎��Ö@
���R�A�����̎��Â����܂��B
�P. �ɂ݂��o�ɂ�������
�Q. ���ʂ͍ŏ����ɂ��A����ɒ��������c���Ȃ�
�R. ���̐_�o�͂Ȃ�ׂ��c��
�S. ��x���Â��������Ăђ����ɂȂ�Ȃ�
�T. �����������́A�����Œ��ڋl�߂�
�� �������Â̒ɂ݂��S�z�ȕ���

���@�ł��ɂ݂��o�ɂ������@�Œ������Â����Ă��܂��B
�����������A�������Ă��ɂ��Ȃ��̂ł����A
���̖������ɂ������̂ł͍���܂��B
���@�ł́A������ɂ��Ȃ�����Q�̕��@���s���Ă��܂��B
�P. �����̒��˂̐j���h�������ɂ݂��Ȃ���

���ƌ����Ă��A�j���h�����̒ɂ݂�h�����Ƃ��厖�ł��B
�����ɍׂ̐j���g���Ă���
�ːj�����ׂ��̂ŁA�h�������ɂ��킩��ɂ����B
���ɂ݂�������זE(�ɓ_)�̏��Ȃ��ӏ��ɍŏ��ɑł�
�˒ɓ_�����Ȃ��̂Œɂ݂ɂ����ł��B
���j���h���u�Ԃ́A�������̔S���ۂ̊v�̂悤�ɁA�s���ƒ����Đj����C�Ɏ������ɓ���悤�ɂ���B
�˂��̂悤�ɂ���ƒ��ːj���h�������Ƃ��킩�炸�A���҂���ɂ́A�u�ŋ߂̖����͒��˂���Ȃ���ł����H�v�ƕ�����邱�Ƃ������ł��B
�Q. ������𒍓�����Ƃ����ɂ݂��Ȃ���

������͉t�̂Ȃ̂ʼn��x���Ⴂ�̂ł����A�������鎞�ɉ��x���Ⴂ�ƁA�̂��₽�������Ă��܂��Ɠ����ɒɂ������Ă��܂��܂��B
���@�ł͂��炩�����������̉����炢�ɉ��߂Ă��܂��̂ŁA������𒍓����Ă��������ꂽ�����̂ɋC�t����܂���̂ŁA�ɂ݂������Ȃ��킯�ł��B
����ƁA�����̃X�s�[�h�����Ȃ������肵�Ă��܂��B�}���Œ�������ƁA���������Ă��܂��ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
���@�ł́A�P�H���P�b���炢�̂������Ƃ����X�s�[�h�Œ������Ă��܂��̂ŁA�������̂ɋC�t����܂���B
�R. �ǂ����Ă��|����̕��ɂ��C����
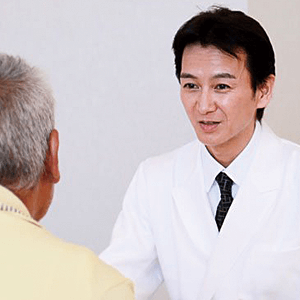
�ǂ����Ă��|����̕��ɂ́A�C�����ƌ����āA�@����C�Ƃ����K�X���z���Ă��炢�܂��B
�C���z���ƁA�����₩�Ń����b�N�X�����C���ɂȂ��A������Ƃق됌���C���ɂȂ����ɂ݂������ɂ����Ȃ�܂��B
�ȒP�ɂł��܂��B�ی����Âłł��܂��B
���C�����̓N���j�b�N�ɂ���đΉ����Ă��Ȃ���@���������܂��B���O�ɂ��₢���킹���������B
�Q. ���ʂ͍ŏ����ɂ��A����ɒ��������c���Ȃ�

���ʂ��ŏ����ɂ���ׂɂ́A���m�ɒ����̂��镔�������ɂ߂Ȃ��Ƃ����܂���B �����́A����őS��������킯�ł͂Ȃ��̂ł��B
���������܂�t�́i���I���m�t�j��h���Ē�������ߏo���܂��B


���������܂�������������T�d�ɍ���A�����ȊO�̕��������Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B����������čs���A�������Ăт��I���m�t�Œ�������ߏo���܂��B
���̍H����������J��Ԃ��A���������܂�Ȃ��Ȃ�܂ŐT�d�ɁA���m���ɒ����������܂��B
�������Ē��J�ɂ��邱�Ƃɂ���āA���Ƀ_���[�W��^�����A�����������c���Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B
�����A���������ۂɎ��c���Ă��܂��Ǝ��c���ꂽ�������傫���Ȃ�A������x���Â��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ�A�ꍇ�ɂ���Ă͐_�o�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ����肵�܂��B
�R. ���̐_�o�͏o�������c��
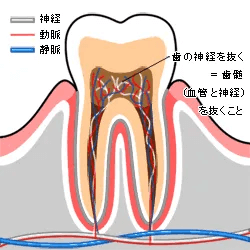
�����̑傫���������炢�Ȃ̂ɁA�����ɐ_�o����鎕�Ȉ�t�������ł��B
�_�o���Ƃ��Ă��܂��ƁA���ɂ͌����ʂ�Ȃ��Ȃ�̂ŁA���ɉh�{�����Ȃ��Ȃ��A���̋��x�������Ă��܂��܂��B
�܂��A���̒��ɂ���Ɖu�זE�����̓������炢�Ȃ��Ȃ�ׁA���ۂ��������₷���Ȃ�܂��B
���̐_�o����邱�Ƃ́A���̎������k�߂Ă��܂��̂ł��B
���ׁ̈A���@�ł��o������莕�̐_�o�͎��Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B
�S. ���Â��������Ăђ����ɂȂ�Ȃ�
�c�O�Ȃ���A��x���Â��������Ăђ����ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B���@�ł́A�����Ȃ�Ȃ��悤�Ȏ��Ö@�����Ă��܂��B
�� ���@�̂������̋l�ߕ��̎��Ö@
1. �����Ԃ̂ł��Ȃ��l�ߕ�������Ă���
�l�ߕ��Ǝ��̊Ԃɂ����Ԃ��ł���ƒ����ɂȂ�₷���ł��B
�N���[�o�[���Ȃł́A���̂悤�Ȃ����Ԃ��ł��Ȃ��悤�Ȏ��̍��������A�^���J�ɂ��A���l�ߕ����M���̂�����Z�H���ɏo�����Ƃɂ�����ɗ͂����Ԃ̂ł��Ȃ��l�ߕ�������Ă��܂��B
�˂������邱�Ƃɂ���āA������h���ł��܂��B
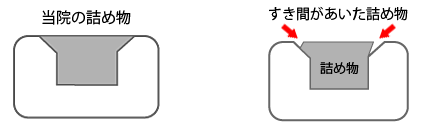
�Q. �t�b�f���܂ڒ��܂��g���Ă���
���t�b�f�͒����ۂ��t���Ȃ��Ƃ�������������܂��̂ŁA�t�b�f���܂ڒ��܂��g�����Ƃɂ���āA����ɓ����ɂȂ�ɂ������Ă��܂��B

�p�i�r�A�t���I���Z�����g
�i�t�b�f����̐ڒ��܁j
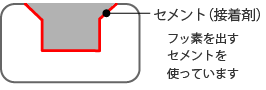
�R. ���Ƌl�ߕ��̐ڒ��͂𑝂��āA�����Ԃ����炷���߂ɁA���i�ۉ县�j�Ƀv���C�}�[�Ƃ����O�������h���Ă���B
�˃v���C�}�[�ɂ��A���i�ۉ县�j�Ƌl�ߕ��̐ڒ��͂��啝�ɃA�b�v���A�l�ߕ��Ǝ��Ƃ̊Ԃ̌��Ԃ����Ȃ�ł��ɂ���

�v���C�}�[
�S. �����̋l�ߕ�������ꍇ�ɂ́A������p�̃v���C�}�[�Ƃ����O�������h���Ă���B�i�ŋ߂͋������l�߂�@��͌���܂����j
�ˋ�����p�̃v���C�}�[�������ɓh�邱�ƂŁA�����Ǝ��i�ۉ县�j�̐ڒ��͂��啝�ɃA�b�v���A�l�ߕ��Ǝ��Ƃ̊Ԃ̌��Ԃ����Ȃ�ł��ɂ����B

������p�̃v���C�}�[

�C�����[�̗����ɁA������p�̃v���C�}�[���g�p���Ă��܂��B
�T. �����������́A�����Œ��ڋl�߂�

�������������������ŁA�����̕����̌^�������āA������v���X�e�B�b�N�̋l�ߕ������鎕�Ȉ�t�������̂ł����A���������l�ߕ�������ׂɂ́A�{�����������镔�������]���Ɏ������Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ł��B
�����h�����߂ƁA�����̋l�ߕ����ƌ��h���������̂ŁA���@�ł́A�����������̏ꍇ�́A����������Ɏ����i���ȗp�̃v���X�e�B�b�N�j���l�߂��悤�ɂ��Ă��܂��B
�T�F��������Ŏ��������Ă��܂��Ă����Ԃ��ł���ꍇ�̎��Ö@
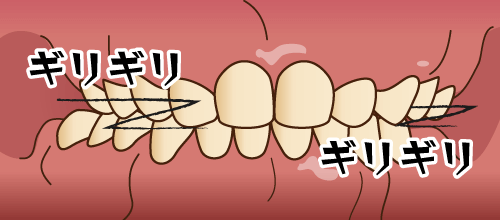
���̏ꍇ�́A��������̌������m�F���Ď��Â��邱�Ƃ��d�v�ł��B
�P. �X�g���X�i��������̌����̑唼�ƌ����Ă��܂��j
�X�g���X������ƁA�͔̂������Ă��܂��Ď���������N�����₷���Ȃ�܂��B�i�����A�X�g���X���U�ׂ̈Ɏ�������͂�����x�K�v�ł�����܂��B�ł����A�Ђǂ���������͍���܂��j
�˃X�g���X�����߂Ȃ������ɕς��邱�Ƃ��K�v�ł��B

�Q. ���ݍ��킹������
�� ���Ö@�P
���̂��ݍ��킹���ǂ��Ȃ��āA�㉺�̎������������鏊���������ꍇ�A���������茸�����犚�ݍ��킹���ǂ��Ȃ�̂ŁA���茸�炻���Ƃ��āA�m�炸�m�炸�Ɏ�����������Ă��܂��܂��B
�˂Ȃ̂ŁA���Ö@�Ƃ��ẮA���ݍ��킹�̐f�f�����āA�����I�ɋ���������Ƃ�����ق�̏������Ȃǂ��Ď����܂��B
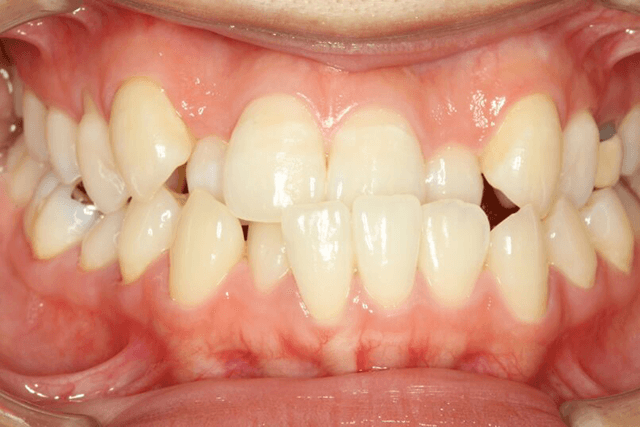
�� ���Ö@�Q
�}�E�X�s�[�X�Ŏ��� �i�ی��������܂��j
�}�E�X�s�[�X��t���邱�Ƃɂ���āA���ݍ��킹�̂ł��ڂ��̃A���o�����X���Ȃ����A�����S�̂̊��ݍ��킹���ϓ��ɂȂ�A�X���[�Y�Ɋ��ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B�����Ȃ�ƁA�P�{�P�{�̎��ւ̕��S������A�܂��A�S�̊߂ɂ����镉�S������܂��B
��Q�鎞�͕K���t���܂��B�������p�\�R���Ƃ��C�������d���̎����t����Ɨǂ��ł��B
���X�ɁA��������A�H�����肪���܂��Ă��܂��B

�R. �����ɋN���鎕�������
�����Ɏ�����������Ă�ƋC�t������A�Ƃɂ������̗͂��ĉ������B
�㉺�̎������킳���ɗ����ĉ������B�H�ׂ���A���肷��Ƃ��ȊO�͋ɗ͎������܂Ȃ��悤�ɋC��t���ĉ������B
�����āA�A�S�̗͂������āA�����y�ɂ��ăX�g���b�`���ĉ������B
�ӎ��I�ɂ���𑱂��邱�Ƃ����ʂ�����܂��B
�S. ��Q�Ă鎞�̐H�������
��Q��O�́A�[���Ȃ��Ƃ͍l�����ɁA�y�������Ƃ��l���ă����b�N�X���Ă��������B
���̗ǂ��������Ƃ邱�Ƃ��H������\�h�ɂȂ�܂��B

���S�̂��ɂ�������A�ǂ̎����ɂ��̂��킩��Ȃ������肷�邱�Ƃ��Ă���܂���ˁI
�F�l�͕s�v�c�Ɏv����ł��傤���A���ۂɂ͂悭���鎖�Ȃ�ł��B
���R���킩���Ă��܂��B�����āA���ۂɂǂ̎����ɂ��̂����ɂ߂���m���͌��\�����ł��B
�P�F�㉺�̒ɂ݂��ԈႦ��
�@�@�{���͏�̎��������Ȃ̂ɉ��̎����ɂ��Ɗ�����ꍇ
�Q�F�����̏ꍇ�͋�̓I�ɂǂ̎����ɂ��̂��킩��Ȃ�
�R�F�ׂǂ����̎��͒ɂ݂��ԈႦ�₷��
�S�F�{���ɑS�̂ɒɂ݂��g�����Ă�
���̒ɂ݂�������_�o�́A�O���_�o�i�������j�ƌ����܂��B
�]����o���_�o�ŁA���̂����肩��O�����ɕ�����ĕ��z���Ă��܂��B
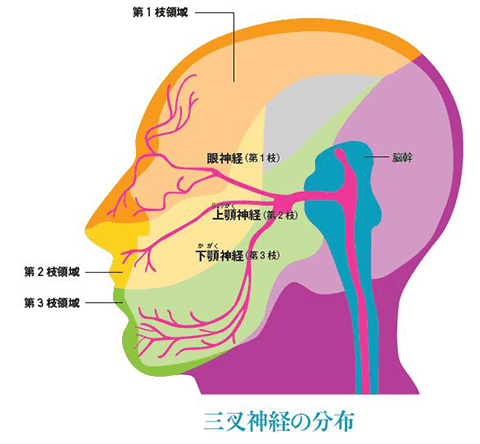
�����āA��P�`�R�}�̎x�z�̈悪�ȉ��̒ʂ�ł��B
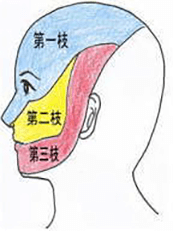
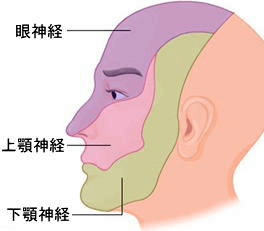
�ɂ݂͉��ɍs���s���قǁA�O���_�o�̕���_�ɋ߂Â��A�ɂ݂���Q�}�Ƒ�R�}�̂ǂ���ɂ������킩��Ȃ��Ȃ�̂ŁA�㉺�̒ɂ݂��Ԉ���Ă��܂��̂ł��B
�����̒ɂ݂��㉺�ԈႤ���Ƃ͖{���ɂ悭����܂��I
�܂��A���ɉ����ׂ͗ǂ����̎��̒ɂ݂������݊��ɂȂ�ǂ̎����ɂ��̂��ԈႢ�₷���ł��B
����ɁA�O���ł��ׂǂ����̎��̏ꍇ�͂킩��Â炭�Ȃ�܂��B
�����āA�ɂ݂��ق��Ă����ƁA�_�o��`����đS�̂��ɂ��悤�Ɋ����Ă��܂��܂��I
�Ώ��@�i���Ö@�j
�ǂ̎����ɂ���������������@�����������܂��B
��������������A���ۂ��������Ĕ^���o�Ă�����A�����a�Ŏ����������Ă��肵�Ă�ꍇ�͖ڂŌ��ĕ���܂��B

�ڂŌ��ĕ���Ȃ��ꍇ�������ł��B
����Ȏ��́A�������Ԃɂ���������A���Ă���A���蔢������ł�������肵�āA���������邩�ǂ�����f�܂��B
�܂��A�g�勾���g���Đf�邱�Ƃ�����܂��B

�����āA�ɂ�ł鎕����肵�āA���̌����̎��Â����Ă����܂��B
�����A�����a�A�������̉��ǁA�_�o�̉��ǁA��������Ă�ȂǁA�������������ēI�m�Ȏ��Â����Ēɂ݂����₭��������悤�Ȏ��Â����܂��̂ł����S���������ˁI
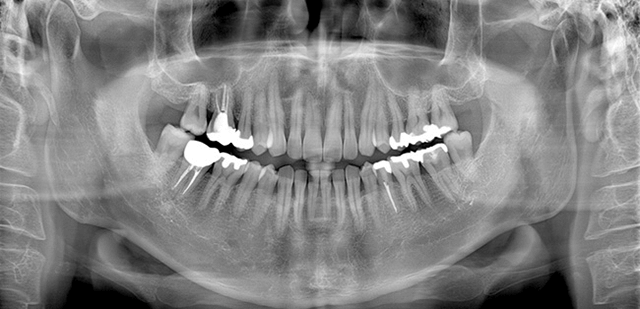

���Â��ɂ��̂ł́A���Â������Ȃ��Ȃ�܂����A����҂ɍs���̂�����ɂȂ�܂���ˁB
�N���[�o�[���Ȃł́A���S���Ď��Â��Ē������߂ɁA�ɂ݂ɔz���������Â�S�����Ă��܂��B

�N���[�o�[���ȃN���j�b�N�~���g�_�ˉ@�A�_�˃}���C�@�ɂ̓h�N�^�[��7���ݐЂ��Ă���A���̕��@�̃h�N�^�[���܂߂��85���ɂȂ�܂��B�ۑ��A��ԁA�����a�A�C���v�����g�A�������ȁA�R�����ȓ��A�S�h�N�^�[�ŘA�g���Ƃ�Ȃ���f�Â�i�߂邱�Ƃ��ł��܂��B
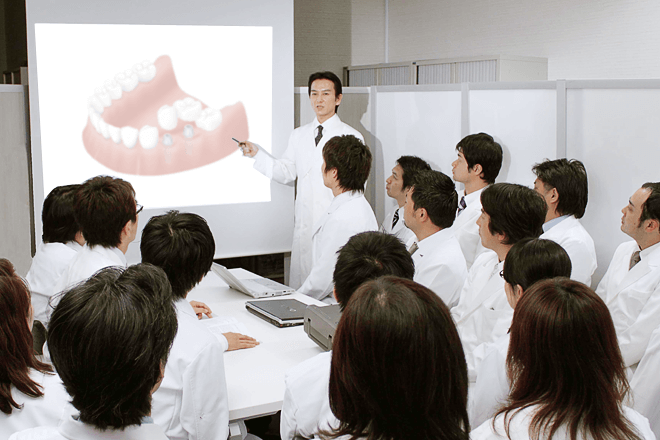
���Ȉ�w�̕���́A���i�������������ǂ�ǂ�i�����Ă���܂��B���@�̃h�N�^�[�͖��T�̂悤�ɁA�u�K��A�w��A�u����A����ɏo�Ȃ��邢�͔��\���Ă���܂��B
��ɕ���ӂ炸�A�h�N�^�[���u���݂��ɐ����������ĕ����Ă���܂��B

�����g���������³��B
�������Ƃ��������J�ɐ������Ă����
���D�����ڂ��Ă����
�����Â͍Ő�[�̂��̂���Ă����
�����҂̋C���������ċ������Ă��炦��
����Ɉ����ė~����
���ɂ��Ȃ��悤���Ă����
���Ȃ�ׂ��������ɂ��Ă����
������Ẩ����t�������ė~�����Ȃ�
�����������鎡�ÁA���N�ɗǂ����ÁA�⎕�ȊO�̎��Â����ė~����
�������ԁA�����J���Ȃ��Ă������Â����ė~����
����Ȏ��Â�ڎw���Ă��܂��I

���җl�ɏ\���Ȑ��������A���ӂ��Ă��玡�Âɂ������Ă���܂��B���җl�ɖ{���ɗ������Ē����A�K���[�����Ē����Ă��玡�Â����Ă����܂��B
���̂悤�ɓ��@�ł͊��җl�Ƃ̃R�~���j�P�[�V��������ɏd�v�����Ă���܂��B���҂�����S�ƐM������悤�ɓw�͂��Ă���܂��B
6.�Q�T�N�̎���

��Ö@�l�^����ɂ͊J��25�N�̎���������܂��B��������̊��җl�����Â��Ă���o���E�Z�p��ςݏd�˂Ă��܂����B
�܂��A�h�N�^�[��4���ݐЂ��Ă��邽�߁A�F��Ȏ��ȕ���ɂ��Ή��ł��܂��i���@���܂߂�ƃh�N�^�[��85���ݐЂ��Ă��܂��j�B

�u�O���S�i���ȊO���f�È�È��S��j�E�O�����i���ȊO���f�Ê�����j�v�Ƃ́A���Â̍ۂً̋}���̑Ή��ƁA�����Ǒ�Ƃ��Ă̑��u�E���̐ݒu�Ȃǂ̎��g�݂��s���Ă���̐��̂��Ƃł��B
���҂���ɂƂ������S�E���S�Ȉ�Ê��Â���ɓw�߂Ă���܂��B

���҂���ɂ��悢���Â������邽�ߗl�X�Ȑݔ��𐮂��Ă��܂��B

���m�E���S�ɃC���v�����g���s�����߁A������p�x����B�e�ł���b�s�����Ă���܂��B�����g�Q���ł͌����Ȃ������������m�F���邱�Ƃ��ł��܂��B

���̐_�o�̎��Â⎕�Ƀq�r�������Ă�ꍇ�̎��ÁA����Ɏ����a�̎����Ȃǂ̎��ɁA�����P�Q�{�Ɋg�債�Ď��Â��s���Ă��܂��B
���Ɏ��̐_�o���Ái���ǎ��Áj�Ɋւ��ẮA�P�Q�{�Ɋg�傷�邱�Ƃɂ���āA���Â̐��������i�i�ɏオ��A���̎������������Ƃ��ł��܂��B
���ǎ��Â����܂��s���Ȃ���A�����Ƃ����P�[�X�͕��ʂɂ���܂��B

���@�ł̓Z���b�N�����Ă���܂��B3D�̃R���s���[�^�[�ŃZ���~�b�N�̃u���b�N������ăN���E���i���Ԃ����j�����V�X�e���ł��B

�~���g�_�ˉ@�E�_�˃}���C�@�Ƌ��Ɋe���O�{�w����k�������B�����ւ�֗��ȗ��n�ł��B
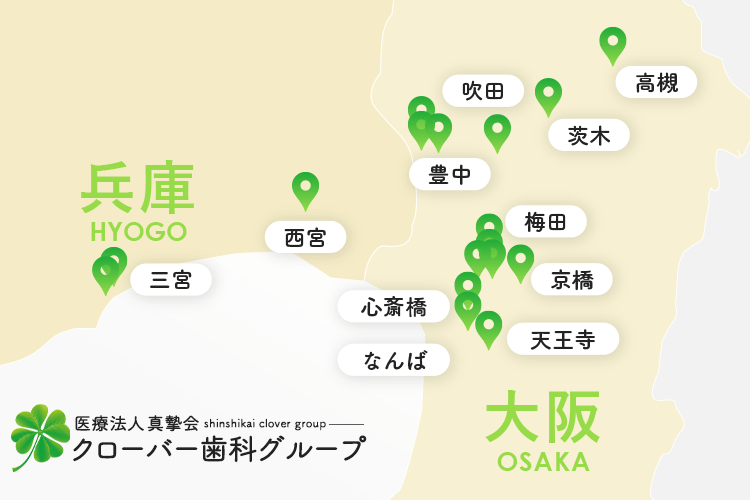
���E���ɂ�17�@�������{�ő�(���{1��)�̎��Ȉ�Ö@�l�Ȃ̂Ŋm���Ɉ��S�ł��B
(�鍑�f�[�^�o���N����)
�܂��A�鍑�f�[�^�o���N�ɂ��ƁA�N���j�b�N�̓��e�������]�_��69�_�ƁA�S���Ń_���g�c1�ʂƂȂ��Ă���܂��B(�S��2�ʂ�62�_)
�Ȃ̂ŁA���җl�ɂ͎��ÂɊւ��đ�ψ��S���Ē����Ă���܂��B
�����Ă��������z�����ꂽ�Ƃ��Ă��A���ߏ��̃N���[�o�[���ȃN���j�b�N�Ŏ��Â��p�����邱�Ƃ��ł��܂��B
�y�ڂ����͂����灨�z

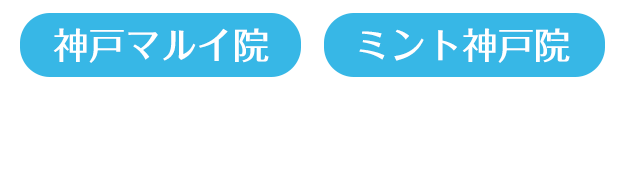
�N���[�o�[���ȃN���j�b�N
�_�˃}���C�@
�_�ˎs������O�{��1-7-2 �_�˃}���C5F
�f����
���`�y
11�F00�`13�F00�^14�F00�`20�F00
�x�f���F���E�j

�O�{�N���[�o�[���ȃN���j�b�N
(�~���g�_�ˉ@)
�_�ˎs������_���7-1-1 �~���g�_��15F
�f����
���`�y
9�F00�`13�F40�^14�F40�`20�F00
�x�f���F���E�j


�N���[�o�[���ȃN���j�b�N�_�˃}���C�@ �@��
�����@���@IMAFUKU TAKASHI
�o���ڍ�

�O�{�N���[�o�[���ȃN���j�b�N �@��
��� �O�q�@SAKANO HIROKO
�o���ڍ�